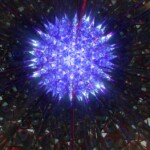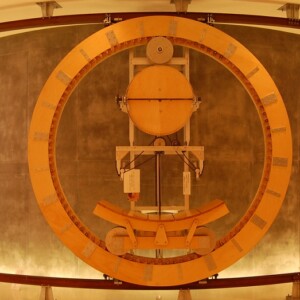ディーゼル車なのに架線の下だけを走った特急・急行列車(常磐線編)
目次
今回は、常磐線を走っていた特急・急行列車の中から、始発から終点までの全区間が電化されているのに気動車(ディーゼル車)で運行された列車を紹介します。
なお、臨時列車に気動車が投入されたというケースは多数存在(※)し、調べ尽くすことが困難なので、定期列車のみの紹介です。
※1985年のつくば科学万博の観客輸送のために運行された臨時列車が好例です。
「気動車」や「電化」とは何かといったことは、以前の「東北本線編」で解説しておりますので、記事をご覧ください。
常磐線

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9381873による
常磐線は、東京都の日暮里駅から宮城県の岩沼駅までを、茨城県の水戸駅や、福島県のいわき(1994年までは平)・原ノ町・相馬といった駅を経由して結んでいる路線です。
ただし、日暮里駅や岩沼駅を始発・終点とする列車は基本的には存在しません。
常磐線を走る列車は、東京都側では上野駅や品川駅(品川駅までの運行開始は2015年3月)まで、宮城県側では東北本線に乗り入れて仙台駅まで直通しています。
以前は仙台駅を越えて盛岡・青森方面へ運行された列車もありました。
本記事では基本的に、上野駅~日暮里駅間や岩沼駅~仙台駅間も、常磐線として扱います。
常磐線は、取手駅(茨城県)以南の電化が1949年6月までに行われました。
1961年6月に勝田駅まで、1962年10月に高萩駅までが電化されます。
1963年5月に平駅までが電化されて、電化区間が東北地方に到達しました。
以後、1963年9月に草野駅までが電化されて、1967年8月に終点の岩沼駅までの電化が完了しています。
1967年8月時点では、東北本線は盛岡駅まで電化されていたので、盛岡駅までならば東北本線・常磐線のいずれの経由でも電車が運行できるようになりました。
1968年8月に、東北本線の終点青森駅までの電化が完了しています。

急行「ときわ」(気動車で急行列車として運行されたのは上野駅~水戸駅・平駅・原ノ町駅)
「ときわ」は、1955年に上野駅~水戸駅間の快速列車として設定されました。
1958年に準急列車に昇格して、運行区間が平(たいら、現在のいわき)駅までに延伸されています。
常磐線の電化は、1963年に平駅まで進展し、大部分の「ときわ」は電車による運行に変更されます。
しかし、1日の内2往復の「ときわ」が気動車のままだったので、上野駅から水戸駅、または上野駅から平駅まで、架線下だけを走る気動車準急列車が誕生します。
上野駅から平駅までの211.6kmにかかった時間は、電車の場合で3時間10分程度、気動車の場合でも3時間20分程度でした。
電車の「ときわ」と比べてあまりそん色がないので、気動車列車にしては速い方だったといえるでしょうか。
一部の「ときわ」だけが気動車で運行されていた理由は、気動車列車と連結して運行するためです。
気動車と電車が連結して運行することは、ごく一部の例外を除いて行われないのです。
「ときわ」の場合は、水戸駅から水郡線という非電化路線に乗り入れる「奥久慈」や「久慈川」と、上野駅~水戸駅間で連結して運行されていました。
気動車と連結して運行する「ときわ」については、電化されている常磐線を走る列車なのに、気動車で運行する必要があったのです。
なお「久慈川」は1968年10月に「奥久慈」へ改称・統合されます。
1966年3月に「ときわ」は急行列車に昇格。
1967年10月の時刻表を見ると、気動車で運行されていた「ときわ」の内の1往復が、下りは相馬駅まで(ただし原ノ町駅~相馬駅間は普通列車扱い)、上りは原ノ町駅から、運行されていたことが確認できます。
したがって「ときわ」が「気動車によって、急行列車として」架線の下を運行された最長区間は、上野駅~原ノ町駅間ということになります。
ただし、この原ノ町駅の方まで運行される「ときわ」は、翌1968年の10月の時刻表によると、電車での運行に置き換わっています。
1978年10月には別の常磐線の急行列車である「そうま」が「ときわ」に統合されます。
その結果、水戸駅から仙台駅まで運行される下り列車や、仙台駅から上野駅までを走破する上り列車も誕生したのです(いずれも電車での運行です)。
急行「ときわ」は長きにわたって活躍したものの、1985年3月のダイヤ改正で、特急「ひたち」に格上げされる形で廃止されました。
気動車の「ときわ」と連結していた気動車急行「奥久慈」も、同時に廃止されています。
かつての急行「ときわ」は廃止されましたが、2015年からは常磐線の特急列車として「ときわ」という列車が走っています。
2025年3月時点のダイヤでは、1日18往復が運行されています。
ただし現在の「ときわ」の運行区間は、品川駅または上野駅から、土浦・勝田・高萩といった茨城県の駅までです。
「ときわ」は旧国名の常陸(ひたち:現在の茨城県)と磐城(いわき:現在の福島県東部)から1文字ずつ取った「常磐(じょうばん、ときわ)」に由来する名前なのに、列車は福島県まで行かないという、少しおかしな状態になっています。
なお、かつての快速・準急・急行列車の「ときわ」も、水戸駅止まりの列車については同様に「『ときわ』なのに福島県へ行かない」というツッコミどころがあります。
急行「そうま」(水戸駅→仙台駅、仙台駅→上野駅)
「そうま」は「ときわ」よりも一足遅く、1960年6月に水戸駅~仙台駅間の準急列車として運行を開始しました。
所要時間は4時間10分から20分程度。
1966年3月には「ときわ」共々急行列車に昇格しました。
名前の由来は、福島県の浜通り北部の相馬市を通るからだとしか思えません。
相馬駅にはもちろん停車します。
1967年8月には常磐線の電化が完了しますが、引き続き気動車で運行されたため、全区間で架線下を走る気動車急行となりました。
そして遅くとも1967年10月には(時期について確たる情報が得られませんでした)、仙台発・水戸行きだった上り列車の運行区間が上野駅まで延伸され、常磐線の全区間を走破する列車となりました。
仙台駅から上野駅までの所要時間は6時間18分。
「そうま」が気動車のままだったのも、気動車列車との連結が理由です。
水戸発・仙台行きの下りの「そうま」は、水戸駅から平駅までの間で、気動車急行「いわき1号」と連結していました。
「いわき1号」は、平駅で「そうま」と切り離されると磐越東線に乗り入れて、福島県の郡山駅に到着すると急行「あいづ」(1968年10月からは急行「いなわしろ」に改称)と連結して、仙台駅へ行く列車でした。
なお、急行「いなわしろ」は、国鉄(JRの前身)時代らしい変わり種の列車でした。
「いなわしろ」の解説記事もぜひご覧ください。
ところで「いわき」との連結を行っていたのは下りの「そうま」だけです。
上りの「そうま」は、他の気動車列車と連結するわけでもなく単独で、仙台駅から上野駅まで延々と架線の下を、軽油を燃やしながら走っていました。
ちょっともったいないです。
1968年10月には、電車で運行される「そうま」も誕生しましたが、1972年3月のダイヤ改正で運行区間を上野駅~盛岡駅間に延長して、急行「もりおか」に改称されたため、電車の「そうま」は消滅しています。
そして残った気動車の「そうま」も、1978年10月に急行「ときわ」に改称・電車化される形で消滅しました。
「ときわ」も、既に述べたように1985年3月に廃止されています。
特急「ひたち」(気動車で運行されたのは上野駅→平駅、平駅→東京駅)
「ひたち」という名前の列車の登場は「そうま」よりもさらに遅く、1963年10月のこと。
上野駅~平駅間で運行される準急列車として運行を開始して、当初から電車での運行でした。
名前の由来は茨城県の旧国名である「常陸」より。
茨城県の日立駅には「ひたち」の設定当初から停車しますが、こちらが名前の由来ということではないようです。
1966年3月には「ときわ」「そうま」と共に急行列車に昇格したものの、1967年10月に「ときわ」に統合されてしまったので「ひたち」の愛称は一度消滅しています。
そして約3年半後の1969年10月に、特急「ひたち」が上野駅~平駅間で運行される列車として誕生しました。
所要時間は3時間程度。
当初は季節を限定して運行される列車でしたが、翌年の1970年10月に、毎日運転される定期列車になりました。
常磐線は既に全区間が電化されていましたが、当初の「ひたち」は、国鉄初の特急列車用気動車であるキハ81系気動車による運行でした。
これは、上野駅と秋田駅を日本海側を経由して結ぶ特急「いなほ」に使用されるキハ81系気動車を、使い回す形で「ひたち」が運行されていたからです。
1969年10月当時は、羽越本線(新津駅~秋田駅)が電化されていなかったので「いなほ」は気動車で運行する必要があったのです。
特急「いなほ」の詳細は、下記の記事でご覧ください。

著作者:Gohachiyasu1214 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76865625による
「いなほ」に使用されるキハ81系は、朝に秋田駅を出発して夕方に上野駅に到着したら、翌日の午後に上野駅を出発して秋田駅へ向かうという運用になっていました。
これでは夕方から翌日の午後まで、東京の車庫で休んでいることになってしまい非効率的なので、上野駅に到着したキハ81系は特急「ひたち」として夜に上野駅から平駅まで、翌朝に平駅から上野駅まで、1往復走行していたのです
(このような車両の活用方法を「間合い運用」と言います)。
というわけで「ひたち」が気動車で運行されたのは「いなほ」の合間に運行されていたからなのですが、気動車で運行することにはもう1つ合理的な点がありました。
常磐線は、全区間が電化されているものの、途中から電化方式が変わります。
具体的には茨城県内の取手駅~藤代駅間を境に、南側は直流1,500Vを電車の走行用電源とする方式で電化されていて、北側は交流50Hz, 20,000Vの方式で電化されているのです。
「ひたち」を電車で運行するためには、直流と交流の両方に対応できる、高価な交直両用電車を用意する必要があります。
その一方で、気動車で運行すれば、電化方式の違いに関係なく走れてしまうというわけです。
なお、同様の理由で気動車列車が運行されている路線は、JR羽越本線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインなど、現在もあります。
1971年4月には「ひたち」の上り列車のみ、終点が上野駅から東京駅に変更されて、運行区間が延伸されます。
気動車による「ひたち」の運行は長くは続きませんでした。
羽越本線の電化が完了したので、1972年10月のダイヤ改正で「いなほ」が、国鉄時代の代表的な特急列車用車両である485系電車に置き換えられることになりました。
なお、羽越本線も途中で電化方式が変わるので、485系はもちろん交直両用電車です。
そして「いなほ」の電車化と同時に「ひたち」も485系電車での運行に変更されたのです
(キハ81系時代に行われていた「いなほ」と「ひたち」の車両の共用は解消されました)。
「ひたち」は増発も行われて、一部列車の運行区間は原ノ町駅や仙台駅まで延伸されました。
現在も運行されている、常磐線の全区間を走破する「ひたち」が誕生した瞬間です。

著作者:spaceaero2 – 自ら撮影, CC 表示 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10650012による
以後も特急「ひたち」は増発が繰り返されていき、常磐線の看板列車としての地位を不動のものとしていきます。
車両の代替わりなどを経て、現在も存続しており、2025年3月時点のダイヤでは、品川駅~いわき駅間で1日12往復、品川駅~仙台駅間で1日3往復の特急「ひたち」が運行されています。
キハ81系が3時間程度かけて走っていた上野駅~いわき駅間の所要時間は、2時間10分前後にまで短縮されています。
「ひたち」をはじめとした、常磐線の特急列車については、下記の記事でご覧ください。

おわりに
個人的な事情ではありますが、筆者は常磐線の沿線に住んでいた時期があります。
今回のような記事を書くために時刻表を見ると、昔はこんなに面白い列車が走っていたのか、見たかったなあと思ったことは一度や二度ではありません。
今後の常磐線にはどのような列車が走ることになるのでしょうか。