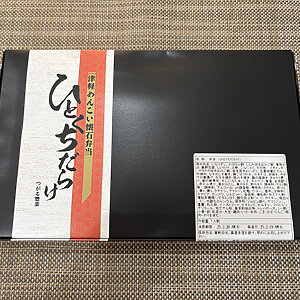ディーゼル車なのに架線の下ばかりを走った急行列車(奥羽本線・仙山線編)
目次
今回は、奥羽本線・仙山線を走っていた急行列車の中から、始発駅から終着駅までの全区間が電化されているのに気動車(ディーゼル車)で運行された列車を紹介します。
なお、臨時列車に気動車が投入されたというケースは多数存在し、調べ尽くすことが困難なので、主に定期列車を紹介します。
また、始発駅・終着駅が複数ある列車の内、一部の編成だけが全区間架線下を走るというケースは対象外とします。
《今回の路線では、急行「千秋(せんしゅう)」が対象外となります。
「千秋」は、仙台駅と青森駅を結ぶ編成に加えて、米沢駅と青森駅を結ぶ編成を連結している列車がありましたが、前者が非電化の陸羽東線を通るためです。》
「気動車」や「電化」とは何かといったことは、以前の「東北本線編」で解説しておりますので、記事をご覧ください。
前回記事の「常磐線編」はこちらです。
奥羽本線

著作者:日本語版ウィキペディアのLincunさん, CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4901440による
奥羽本線は、福島県の福島駅から、山形県の米沢駅・山形駅・新庄駅や、秋田県の横手駅・大曲駅・秋田駅・東能代駅・大館駅、青森県の弘前駅・新青森駅といった駅を経由して、青森駅までを結んでいる路線です。
福島駅~秋田駅間と秋田駅~青森駅間で、路線が果たしてきた役割には若干違いがあることから、今回は前者の福島駅~秋田駅間を経由していた列車に焦点を当てます
(後者の区間を経由していたものの前者の区間に乗り入れない列車は、今後の記事で扱います)。
1982年に東北新幹線が開業するまでの奥羽本線は、首都圏や福島県と、山形・秋田・青森の3県を結びつける役割を果たしてきました。
東北新幹線の開業や、その後の山形新幹線や秋田新幹線の開業を経て、首都圏と東北地方を結ぶメインルートの1つという役割は低下しました。
しかし、一部区間は山形新幹線の「つばさ」や、秋田新幹線の「こまち」の経路となっており、今もなお重要性は失われていません。
なお、山形新幹線や秋田新幹線という名称は正式な路線名ではなく、これらの列車が経由している区間(福島駅~新庄駅間と大曲駅~秋田駅間)も、正式名称は奥羽本線のままです。
奥羽本線は、まず1949年4月に福島駅~米沢駅間が直流電化されました。
続いて、1960年11月に山形駅~羽前千歳駅間が直流電化されました。
1968年9月には、既に直流電化されていた区間が交流電化へ変更されて、さらに米沢駅~山形駅間が交流電化されます。
1971年8月に秋田駅~青森駅間が交流電化されました。
そして、1975年10月に羽前千歳駅~秋田駅間が交流電化されて、全区間の電化が完了しました。
直流と交流に関する詳しい説明は省きますが、直流電化区間と交流電化区間では電車の走行用に用いる電源の種類が違うので、一方の電化方式にしか対応していない電車は、双方の電化区間の直通は不可能です。
奥羽本線は、2024年7月に発生した豪雨によって被災したことに伴い、2025年4月に新庄駅から秋田県の院内駅までの区間の電化設備が撤去された状態で、列車の運行が再開されました。
したがって現在の奥羽本線は、全区間が電化された状態ではなくなっています。
電化設備の撤去に踏み切れた背景には、まさに先ほど述べたように、奥羽本線がもはや首都圏と東北地方を結ぶメインルートではなくなったことがあげられます。

急行「ざおう」(上野駅~山形駅)
1960年6月に、東京都の上野駅と山形県の山形駅を、東北本線・奥羽本線経由(途中、埼玉県の大宮駅・栃木県の宇都宮駅、福島県の福島駅といった駅を経由)で結ぶ急行列車が誕生し「蔵王(ざおう)」という愛称が付けられました。
宮城県と山形県の県境にそびえる蔵王連峰が愛称の由来だと思われます。
登場当初の「蔵王」は、機関車が客車をけん引するという伝統的なスタイルの列車でした。
また、上野駅から福島駅までの間では、東北本線の急行「松島」と連結して運行されていました。
「松島」の運行区間は上野駅~仙台駅間でした。
後に東北新幹線「やまびこ」(主に東京駅~仙台駅)と、山形新幹線「つばさ」(東京駅~山形駅・新庄駅)が、東京駅~福島駅間で連結して運行されるようになるのと、同じような形で運行されていたことになります。
1963年10月には「蔵王」から「ざおう」に改称。
また、1日1往復だったのが増発されました。
気動車を使用した「ざおう」も登場し、1964年9月の時刻表では、1日2往復が気動車による定期列車(毎日運転される列車)、1往復が客車による季節列車(季節を限定して運転される列車)となっています。
上野駅~山形駅間の所要時間は、気動車列車で6時間10分~30分ほど、客車列車は7時間30分ほどでした。
上野駅から福島県の郡山駅までの間では、磐越西線に直通する「いいで」や「ばんだい」といった急行列車と連結して運行されました。
翌月1964年10月の時刻表では、気動車定期列車が1日1往復、客車定期列車が1往復となり、気動車列車が減らされた代わりに、同じ上野駅~山形駅間を結ぶ気動車特急「やまばと」が誕生しています。
1968年に、福島駅から山形駅までの電化が完成したことから、10月のダイヤ改正で一部の「ざおう」が、455系電車での運行に変更されました。
電車で運行される「ざおう」の、上野駅~山形駅間の所要時間は5時間ほどにまで短縮されたのです。

電車が2往復、気動車が1往復という体制になっています。
気動車の列車が、始発駅から終着駅までの全区間で架線下を走る気動車急行列車ということになりました。
気動車の「ざおう」が残ったのは、上野駅~郡山駅間で気動車急行「いいで」と連結を行っていたためです。
気動車と電車を連結して運転することは、ごく一部で実例がありますが、一般的には行われません。
運行区間がたとえ全て電化されていても、気動車列車と連結して運行される列車であれば、気動車で運行する必要があったのです。
なお「いいで」は上野駅と新潟駅の間を、東北本線・磐越西線・信越本線を経由して運行される列車でした。
磐越西線の内、福島県の喜多方駅から新潟県の新津駅は電化されていなかったので「いいで」を電車にすることは不可能でした
(2025年現在の磐越西線は、電化区間が郡山駅から会津若松駅までに短縮されています)。
1972年3月のダイヤ改正で「ざおう」の定期列車はなくなり、全列車が季節列車、または多客期のみ運行される臨時列車となりました。
「ざおう」の運行が縮小されていったのは「ざおう」が同じ区間を走る特急「やまばと」に格上げされたことが大きな要因でした。
その後、しばらく大きな動きがなかったものの、東北新幹線が1982年6月に開業したことに伴い、11月15日に実施されたダイヤ改正で「ざおう」の定期列車が1日1往復誕生しています。
この時期の「ざおう」は、かつて連結を行っていた「まつしま」を、上野駅~福島駅間で連結していたことも特筆されます。
また、福島駅~山形駅間で運行される季節列車の「ざおう」も1往復設定されました。
ただし、この1982年11月のダイヤ改正で気動車の「ざおう」は消滅しています。
気動車の「ざおう」の連結相手だった「いいで」も廃止されました。
1985年3月には「ざおう」の定期列車が再び消滅し、臨時列車のみの運行に。
運行区間は上野駅~山形駅間、または上野駅~新庄駅間となっています。
また、少なくともこの月の時刻表に掲載されている臨時列車の「ざおう」は、全て客車列車でした。
臨時急行列車としての「ざおう」も、奥羽本線に山形新幹線「つばさ」が通れるようにする工事を行うために1991年8月に廃止されました。
しかし、11月に福島駅から山形駅までの区間を走る快速列車の名称として「ざおう」が復活。
快速「ざおう」は1999年頃まで活躍したとのことです。
なお、現在の福島駅~山形駅間では、快速列車の運行は行われていません。
急行「おが」(気動車で運行されたのは上野駅~秋田駅)
1961年10月に、東京都の上野駅と秋田県の秋田駅を、東北本線・奥羽本線経由(大宮・宇都宮・福島・山形といった駅を経由)で結んでいた夜行列車が、急行「男鹿」に昇格しました。
愛称の由来は、秋田県の男鹿半島でしょう。
2年後の1963年10月に、急行「おが」に改称されます。
1968年までの「おが」は、機関車が客車をけん引して走る夜行列車でしたが、1968年10月に大きな変化が訪れます。
気動車を使用した昼行列車(夜をまたがず運行する列車)の急行「おが」が1日1往復設定されたのです。
気動車列車は、登場してから数年間は、上野駅~福島駅間で、東北本線の上野駅~青森駅間等を走る急行「八甲田」と連結して運行されることがあったようです。
昼行気動車列車の「おが」の上野駅から秋田駅までの所要時間は10時間を超えました。
同じ区間を走る夜行列車や、特急「つばさ」などもある世の中で、昼行の「おが」を全区間利用する人が果たしていたのだろうかと思います。
「おが」の経路である奥羽本線の電化は1975年10月に完了したので、以後は気動車で運行されていた列車を電車に変更できるはずでした。
しかし、電化完了後も引き続き気動車で運行されたので、全区間架線下気動車急行となったのです。
「おが」が電車に置き換えられなかったのは、途中で電化方式が変わるためだと考えられます。
「おが」が走行する東北本線は、栃木県の黒磯駅を境に、南側は電車の走行用電源が直流1,500Vで、北側は交流20,000Vとなっていました
(現在の境界は、黒磯駅の構内ではなく黒磯駅の北側に移っています)。
両方の電化方式をまたいで走行するためには、両方に対応した電車が必要になるのです。
一方、気動車ならば、電化方式に関係なく直通できるというわけです。
とはいうものの、先ほど紹介した「ざおう」も東北本線を経由する列車ですが、しっかりと交直両用電車である455系電車に置き換えられました(「いいで」と連結している列車は除く)。
では、他の気動車列車と連結するわけでもない「おが」がなぜ気動車のままだったのかというと、交直両用電車が高価で、おそらく車両数が不足していたのでしょう。
「ざおう」は電車化できても「おが」に使用する電車までは工面できなかったとか、そういった事情があったのだと思います。
1982年には東北新幹線・上越新幹線が開業したことから、東北地方の在来線を走る特急・急行列車の大規模な整理が行われます。
1982年11月15日のダイヤ改正で、昼行気動車急行の「おが」は廃止されました。
1968年に設定されてから14年間という短い期間の運行で、廃止されるその時まで、気動車での運行に変更はありませんでした。
「おが」は客車による季節夜行列車1往復のみの運行になりました。
残った客車列車の「おが」も、1985年には多客期のみ運行される臨時列車に変更され、1995年の年始頃を最後に、一切運行されなくなってしまいました。
「おが」については、下記の記事で解説しているので、詳細は記事をご覧ください。
急行「こまくさ」(山形駅~秋田駅・青森駅)
急行「こまくさ」は、1970年10月のダイヤ改正で登場しました。
運行区間は山形駅~秋田駅間で、所要時間は4時間ほど。
登場当初から気動車での運行でした。
なお、コマクサとは蔵王連峰などに自生する高山植物の名前です。
1975年10月には「こまくさ」の運行区間の電化が完了しましたが、引き続き気動車で運行されたので、全区間架線下気動車急行となりました。
1978年10月には、運行区間が山形駅~青森駅間に変更されました。
奥羽本線の秋田駅から青森駅までの電化は1971年8月に完了していたので「こまくさ」は引き続き全区間架線下気動車急行です。
なお、山形発・青森行きの下り列車の所要時間は6時間42分ですが、上り列車の所要時間は7時間41分と、なぜか59分も異なっています。
青森駅では、青森駅と北海道の函館駅とを結ぶ「青函連絡船」と乗り継げるダイヤとなっていました。
青函連絡船については、下記の記事をご覧ください。
「こまくさ」が気動車のままだったのは、連結する相手の列車が気動車だったことが理由だと思われます。
山形発・青森行きの下り列車は、山形駅~新庄駅間で急行「月山(がっさん)1号」を連結していました。
月山1号は、新庄駅から陸羽西線を経由し、余目(あまるめ)駅からは羽越本線を南下し、山形県の日本海側にある鼠ケ関(ねずがせき)駅まで行く列車でした。
陸羽西線は非電化なので「月山」を電車にすることはできません。
ちなみに「月山1号」は、余目駅から終着の鼠ケ関駅までは、秋田発・新潟行きの急行「羽越(うえつ)2号」と連結していました。
この「羽越」も全区間架線下気動車急行だったので、後日記事でとりあげる予定です。
青森発・山形行きの下り列車は、途中の秋田駅から大曲駅までの区間で急行「たざわ4号」と連結していました。
また、新庄駅から山形駅までは、鼠ケ関発・山形行きの「月山6号」と連結していたのです。
「たざわ4号」は秋田駅始発で、大曲駅からは田沢湖線を経由し、盛岡駅から東北本線を南下して仙台駅まで行く列車でした。
田沢湖線は当時非電化だったので「たざわ」の電車化も不可能です。
なお、田沢湖線は1982年に電化されており、現在は秋田新幹線「こまち」の経路にもなっています
「たざわ」が「こまち」の前身のような列車という見方もできます。
1982年11月15日のダイヤ改正で「こまくさ」は、奥羽本線の特急「つばさ」に吸収される形で廃止されました。
最後まで1日わずか1往復の気動車による運行だったようです。
山形新幹線開業前の特急「つばさ」については、下記の記事で解説しているので記事をぜひご覧ください。
急行「こまくさ」の廃止からおよそ10年後の1992年7月に、山形新幹線の「つばさ」が東京駅~山形駅間で運行を開始しました。
「つばさ」が発着する山形駅からは、新庄駅または秋田駅まで運行される特急「こまくさ」が、新たに運行を開始。
しかし、1999年12月の山形新幹線の新庄駅延伸開業を前にして、1999年3月に特急「こまくさ」は新庄駅以北の運行に改められたうえで快速列車に変更されました。
2002年12月には快速「こまくさ」も消滅しています。
なお、現在の新庄駅~秋田駅の区間で運行されている快速列車は、新庄発・横堀行きの下り列車が2本、横堀発・新庄行きの上り列車が1本、湯沢発・秋田行きの下り列車が1本のみです。
仙山線

Lincun – Map: 投稿者自身による著作物Data used: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism National Land Numerical Information (Administrative Area (N03), Railway (N02), Lake (W09))使用データ: 国土交通省 国土数値情報(行政区域(N03)・鉄道(N02)・湖沼(W09)), CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97569553による
仙山(せんざん)線は、宮城県仙台市の仙台駅から、山形県山形市の羽前千歳駅までを結んでいる路線です。
ただし、羽前千歳駅を始発・終着とする列車はなく、列車は奥羽本線に乗り入れて、山形駅まで直通しています。
事実上は、仙台駅と山形駅を結ぶ路線です。
現在の仙山線は主に仙台都市圏の通勤・通学輸送を担っています。
仙台市と山形市を結ぶ役割も果たしてはいるものの、高速バスの方が優勢と見受けられる状況です。
ただし、かつては仙山線・奥羽本線・米坂線といった路線を経由(山形・米沢・新潟県の坂町といった駅を経由)して、仙台と新潟を結ぶといった役割も果たしていました。
仙山線の電化は、まず1937年11月に作並駅~山寺駅間が直流で実施されました。
一方、1955年8月に陸前落合駅~熊ケ根駅間が日本の鉄道では初めて交流で電化され、仙山線は直流電化と交流電化が混在した状態となります。
1957年9月には仙台駅~陸前落合駅間と熊ケ根駅~作並駅間が交流電化。
作並駅構内が、直流電化と交流電化の境界となりました。
1960年11月には山寺駅~羽前千歳駅間が直流電化。
同時期に奥羽本線の山形駅~羽前千歳駅間も直流電化されたので、仙台駅から山形駅までの区間が電化された状態になりました。
また、1968年11月に、直流電化されていた区間が交流電化に変更されたことから、仙山線は全区間が交流電化された路線となり、今に至っています。
仙山線が当初は直流で電化されたにもかかわらず、あとから交流電化が行われたのは、交流電化の実用化を目指す実験場として仙山線が選ばれたからです。
仙山線の試験で得られたデータや技術によって、その後、東北・北陸・九州地方を中心に、幹線の電化が交流で行われるようになります。
また、仙山線や奥羽本線の既に直流電化されていた区間も、周辺の路線の電化方式と同様の交流電化に変更されたのです。
そして、1964年に開業した東海道新幹線をはじめとした各新幹線の路線は、1つの例外もなく交流で電化されています。
仙山線で得られた試験の成果は、新幹線の誕生にもつながっているのです。
急行「仙山」(気動車で架線下を運行されたのは仙台駅~山形駅)
「仙山(せんざん)」は、1963年10月のダイヤ改正で、仙台駅~山形駅・上ノ山駅(現:かみのやま温泉駅)間を仙山線・奥羽本線経由で結ぶ列車として運行を開始しました。
気動車によって運行され、当初は準急列車でした。
仙山線および奥羽本線の山形駅~羽前千歳駅間は既に電化されていました。
そのため、1日2往復運行されていた仙台駅~山形駅間の「仙山」は、当初から全区間架線下気動車準急でした。
また、1日1往復運行されていた仙台駅~上ノ山駅間の列車についても、非電化区間は山形駅から上ノ山駅までのわずか12.1kmの区間だったことになります。
1968年10月に「仙山」は急行列車に昇格。
そして1日3往復の全列車が仙台駅~山形駅間の運行となります。
また、上下いずれの列車も、1号と2号は電車に置き換えられました。
3号は引き続き、全区間が電化されているものの気動車での運行です。
気動車のまま残った理由は、電車が足りなかったか、3号に使用される気動車を、別の気動車列車に使い回していたかのどちらかだと推測します。
仙台駅~山形駅間の所要時間は、電車の場合で1時間10分程度、気動車の場合で1時間40分程度と、結構な差がありました。
急行昇格から10年後の1978年10月には、気動車で残っていた1往復も電車化されたので、1963年以来15年間続いてきた全区間架線下気動車急行としての歴史は終わりました。
1982年11月15日のダイヤ改正で「仙山」は快速列車に格下げされたので、急行列車としての歴史も終了しました。
1985年3月には、普通列車も含めて仙山線を走る全ての定期列車が電車化されており、かつての気動車や客車列車が運行されていた面影はもはやありません。
快速の「仙山」はしばらく存続しましたが、2004年に愛称がなくなりました。
ただし、仙山線の快速列車は2025年現在も存続しています。