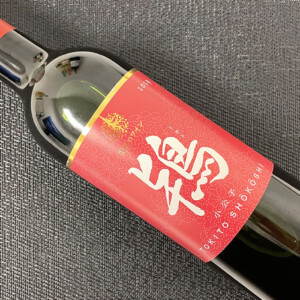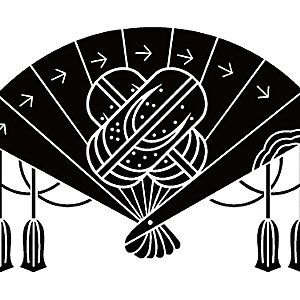なぜか珍名が多い?奥羽本線の駅名【福島・山形・秋田】
目次
「奥羽本線」は、福島駅から山形駅、秋田駅といった駅を経て青森駅に至るJR東日本の路線です。
東北地方を南北方向に貫く幹線の1つで、かつては全区間を走破する特急列車も運行されていました。
現在も一部区間が山形新幹線の「つばさ」や、秋田新幹線の「こまち」や、特急「つがる」といった列車の経路になっています。
この奥羽本線では、なぜか変わった名前の駅が目立つので、今回はその珍名駅を紹介します。
奥羽本線は東北地方の一大幹線
「奥羽本線」は福島県の福島駅から、山形県の山形駅、秋田県の秋田駅を経て、青森県の青森駅に至る、全長484.5kmにも及ぶJR東日本の路線です。
東北地方の幹線といえば東北本線が思い浮かぶこともあるかと思いますが、奥羽本線の特徴は、東北地方の中で完結している幹線だという点にあります。
東北6県の内、実に4県もの県庁所在地を経由していることが、東北地方の中での重要性を示しているようです。
県庁所在地以外にも、米沢、新庄、湯沢、横手、大曲、能代、大館、弘前といった都市を経由しています。

著作者:日本語版ウィキペディアのLincunさん, CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4901440による
かつては奥羽本線の全区間を走破する急行や特急列車も運行されていました。
現在も福島駅から山形駅を経て新庄駅までの区間には、山形新幹線の「つばさ」が運行されていて、大曲駅から秋田駅までの区間には、秋田新幹線の「こまち」が運行されています。
奥羽本線という路線の存在や名前は知らなくても、利用したことがある人は多いことでしょう。
それでは、ここからは奥羽本線の珍名駅を紹介していきます。
峠駅(山形県米沢市)

最初に紹介するのは、山形県米沢市大字大沢字峠にある「峠(とうげ)駅」です。
峠です。国土の面積の約75%が山地というこの日本で「峠」です。駅が山地にあること以外何も伝わらない名前です。
この峠というのは福島県と山形県の間にまたがる「板谷峠」のことを指しています。
峠駅は標高が626メートルと奥羽本線の中で最も高く、この駅を境として線路は福島方面・青森方面の双方とも下り坂になります。
峠駅を越えることは駅名通り「峠を越える」ということなのですね。

板谷峠を鉄道で越えることは昔の技術では難しく、屈指の難所として知られていました。そんな板谷峠も、現在は山形新幹線の「つばさ」がスイスイと登っていきます。ただし「つばさ」は峠駅には停車せず通過してしまいます。
峠駅で降りるためには山形線とも呼ばれる普通列車を利用する必要があります。
峠駅は山中にあることから、列車を使用する以外の方法で到達することはなかなか難しく、秘境駅としても知られています。
駅員もいませんが、しかしこの駅では今となっては珍しい食品の立ち売りが行われています。
立ち売りで売られている「峠の力餅」は、峠駅の名物です。
※駅を訪問する際には最新の情報をご確認ください。
高擶駅(山形県天童市)

著作者:Mister0124 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147374856による
続いては山形県天童市大字長岡にある「高擶(たかたま)駅」です。「擶」という字が大変に珍しく、普通は読めないことでしょう。
駅名は1952年に駅が開業した当時の自治体名である「高擶(たかだま)村」から取られています。
自治体名は「たかだま」と濁っているのに、駅名は「たかたま」と濁っていないのですが、こういったケースは、特にJRの駅では全国的に見られるものです。
知らなければ読めない「擶」という字は、樹木のニレに由来しているとのことです。
その由来にちなんでいるのか、駅の待合室は木材を中心とした作りになっています。
高擶駅も、山形新幹線の「つばさ」は通過してしまいますので、下車するためには山形線の普通列車で訪れる必要があります。
及位駅(山形県最上郡)

著作者:Mister0124 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147726137による
続いては山形県最上郡真室川町大字及位にある「及位(のぞき)駅」です。珍名以前に、知らなければまず読めない駅名で、日本屈指の珍名&難読駅として知られています。
「及位」と書いて「のぞき」と読む地名の由来は諸説あるそうですが、定説となっているのは以下のようなものです。
かつてこの付近の山で修験者たちが、険しい断崖で宙づりになって崖の横穴をのぞき込む「のぞきの行」という修行を行っていました。
そしてのぞきの行をして高い「位」に「及」んだ修験者がいたことから「及位」という地名が生まれたというのです。名前から受ける第一印象に反する、大変高尚な由来です。
及位駅が位置する新庄駅~大曲駅間には特急列車は走っていませんので、列車での訪問は普通列車を利用することになります。
醍醐駅(秋田県横手市)

著作者:Mister0124 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147816979による
続いては秋田県横手市平鹿町醍醐字太茂田(たもでん)にある「醍醐(だいご)駅」です。醍醐という地名の由来は、牛乳を煮詰めた醍醐という乳製品だと思われます。かつてはこの一帯が牛の放牧地だったのでしょうか。
醍醐が具体的にどのような乳製品だったのかはわかっておらず、バター、カルピス、あるいはヨーグルトのようなものだったといった諸説があるようです。
しかし醍醐を語源とした「醍醐味」という言葉はよく知られていると言えるでしょう。
1976年にリリースされたアリスのシングル「遠くで汽笛を聞きながら」のレコードジャケットには、醍醐駅のプラットホームの写真が用いられています。
醍醐駅にも特急列車はなく、また朝に設定されている快速列車も停車しないので、訪問は各駅に停まる普通列車で。
後三年駅(秋田県仙北郡)

著作者:Bramble – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25863857による
続いては秋田県仙北郡美郷町飯詰字東山元にある「後三年(ごさんねん)駅」です。駅名の由来は、日本史に詳しい方ならすぐにわかることでしょう。周辺一帯が「後三年の役」の古戦場であったことによります。ちなみに現在の教科書等では「後三年の役」ではなく「後三年合戦」と記す方が主流のようです。「役」を「駅」と誤変換することを防ぐためにも、以後それに従います。
後三年合戦は、永保3年(1083年)から寛治元年(1087年)にかけて奥羽地方で行われた戦いです。
「後」とつく合戦が存在することから容易に想像がつくように「前」がつく合戦もありました。
「前九年合戦」という戦いです。
後三年合戦は、出羽国の豪族である清原氏の内紛に、陸奥守である源氏の源義家が介入し、勝利したという戦いでした。
源義家の助力を経て勝利した清原清衡は、実父の姓である藤原姓に復帰し、奥州藤原氏の初代当主となったのです。
後三年駅にも特急列車はなく、快速列車も停まりません。
後三年の役古戦場 標柱<Information>
- 名称 後三年の役古戦場 標柱
- 所在地 秋田県仙北郡美郷町飯詰東西法寺
Google MAP
井川さくら駅(秋田県南秋田郡)

著作者:掬茶 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79222272による
続いては秋田県南秋田郡井川町浜井川字新堰にある「井川さくら(いかわさくら)駅」です。駅名の由来は、近くに桜の名所である「日本国花苑」があることに由来します。井川町と「さくら」を合わせた駅名ということです。
しかし「人名のような駅名だ」と感じられることは否定しようがありません。
2008年と2018年にgooランキングで開催された、人名のように感じられる駅名への投票では「武豊(たけゆたか……ではなく、たけとよ)」「中山香(なかやまが)」「近江舞子(おうみまいこ)」「飯山満(はさま)」「千葉みなと(ちばみなと)」「吉川美南(よしかわみなみ)」といった駅名を抑えて、1位になっています。
・芸名・人名だと勘違いしそうな実在の駅名ランキングTOP29 – gooランキング
・人名じゃないのかよ!とツッコミたくなる駅名ランキング – gooランキング
1996年に井川さくら駅が開業した際には、井川町が当時小学生になったばかりだった「井川さくらさん」を町に招待したとのことです。
なお、井川さくら駅には特急「つがる」「スーパーつがる」や、快速「リゾートしらかみ」は停車しないので、訪問の際には普通列車や、名前のない快速列車を利用する必要があります。
余談ですが、本当に人名がつけられた駅としては、岡山県美作市今岡にある智頭(ちず)急行智頭線の「宮本武蔵(みやもとむさし)駅」があげられます。
付近が剣術家・宮本武蔵の生誕地であるという説があることから命名されました。
また、神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目にある、JR鶴見線の「浅野(あさの)駅」も、鶴見臨港鉄道(鶴見線の前身)の設立者で、浅野財閥創設者でもある浅野総一郎にちなんで名づけられたので、これも人名である駅名と言えます。
日本国花苑<Information>

- 名称 日本国花苑
- 所在地 秋田県南秋田郡井川町浜井川二階102-1
- 入場時間 24時間可
- URL 日本国花苑 | 秋田県井川町ホームページ
Google MAP
大鰐温泉駅(青森県南津軽郡)

続いては青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田にある「大鰐温泉(おおわにおんせん)駅」です。大鰐は駅がある場所の地名です。
ワニがいない日本に大鰐という地名がある時点で、珍しい名前だと言わざるを得ないでしょう。
地名の由来には諸説あり、以下はその一説です。
この地には大きな阿弥陀如来坐像があったことから「大阿弥陀(おおあみだ)」と呼ばれていました。
それが徐々に「大阿弥(おおあみ)」→「大阿子(おおあね)」→「大安国寺(おおあに)」→「大姉(おおあね)」といったように変形し、やがてワニが仏教の守護神であることと結びつき、「大鰐」と呼ばれるようになった、と言われています。
あるいは鰐とはいわゆるワニのことではなく、大きなサンショウウオではないかとも言われているようです。
ともあれ、大鰐町と仏教との縁は現在でも深く、国の重要文化財にも指定された阿弥陀如来坐像が、大鰐温泉駅から近いところにある大円寺にまつられています。
大鰐温泉駅には、普通列車が停車することに加えて、秋田駅~青森駅間を結ぶ特急「つがる」「スーパーつがる」も停車します。
大円寺<Information>
- 名称 大円寺
- 所在地 青森県南津軽郡大鰐町蔵館村岡12
- 問い合わせ番号 0172-48-2017
- URL 大円寺 – 大鰐町ホームページ
Google MAP
撫牛子駅(青森県弘前市)

著作者:にっしーーー – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135802487による
続いては青森県弘前市大字撫牛子一丁目にある「撫牛子(ないじょうし)駅」です。ワニの次はウシです。難読駅名であり、そして読めたところで「牛をなでる……だから何なの?」と思ってしまいます。
撫牛子という地名の由来については、「撫で牛」が津軽地方方言になまった「ナンデ・ウシィ」「ナンデ・ウシィ・ッコ」が由来になっているという説や、アイヌ語の「ナイ(川や沢)・チャシ(砦や柵)」から来ている(この場合、牛とは何も関係ないということになります)という説などがあり、決定的な説はないようです。
撫牛子駅には普通列車のみが停車します。
特急「つがる」「スーパーつがる」や快速列車は停車しません。
番外編 牛坂踏切
駅ではありませんが、秋田県潟上市天王追分にある、奥羽本線(追分駅~大久保駅間)の踏切である「牛坂(べこさか)踏切」の存在を知った筆者は、紹介せずにはいられませんでした。
さすがは奥羽本線、踏切の名前まで難読です。
ちなみに踏切の付近に同名のバス停もあります。
牛坂を「べこさか」と読めなければよそから来た人だとばれてしまうという程度には、地元では有名な地名のようですが、その由来は地元でもはっきりしていないようです。
牛か牛車がよく通る坂であった、といったところではないかとは思いますが。
Google MAP
まとめ
奥羽本線の駅は101もあり、今回紹介した駅はその1割にも満たないものです。
とはいえ、これだけの数の駅がある上で1割近い駅が珍名という路線は、全国的にも珍しいのではないでしょうか。
記事中で説明したように、駅名・地名にはその土地が歩んできた歴史の一端が刻まれています。
奥羽本線はただ人や物を運んでいるだけではなく、東北地方各地の歴史の一端を今に伝える役割も担っているともいえるのではないでしょうか。
そして旅をする際には、その土地の歴史にも着目すると、旅がぐっと面白くなりますよ。