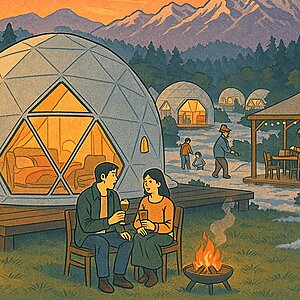ディーゼル車なのに架線の下だけを走った急行列車(日本海縦貫線編)
目次
今回は、日本海縦貫線と総称される路線の内、東北地方を通る区間を走っていた急行列車の中から、始発駅から終着駅までの全区間が電化されているのに、電車を使わずに気動車(ディーゼル車)で運行された列車を紹介します。
なお、臨時列車に気動車が投入されたというケースは多数存在し、調べ尽くすことが困難なので、定期列車のみの紹介です。
また、始発駅・終着駅が複数ある列車の内、一部の編成だけが全区間架線下を走るというケースは対象外とします。
《今回の路線では、急行「千秋(せんしゅう)」が対象外となります。
「千秋」は、仙台駅と青森駅を結ぶ編成に加えて、米沢駅と青森駅を結ぶ編成を連結している列車がありましたが、前者の編成が非電化の陸羽東線を通るためです。》
「気動車」や「電化」とは何かといったことの詳細は、シリーズ初回の「東北本線編」で解説しておりますので、記事をご覧ください。
以下、前回までの記事です。
日本海縦貫線
日本海縦貫線とは、複数の路線の総称であり、正式な路線名ではありません。
主に、大阪府の大阪駅から、日本海沿岸を通って青森県の青森駅までを結ぶ路線郡が、日本海縦貫線と呼ばれます。
近畿地方と青森県・北海道を結ぶ最短経路であることから、古くから貨物輸送で活躍してきました。
また、1961年から2001年までは大阪駅と青森駅を結ぶ特急「白鳥」が運行されていたように、日本海縦貫線を走破する旅客列車もかつては存在しました。
日本海縦貫線に含まれる路線の内、東北地方を通っている路線は、以下の2路線です。
- 羽越本線:新潟県新潟市秋葉区の新津駅から秋田県秋田市の秋田駅まで
- 奥羽本線(一部):秋田駅から青森県青森市の青森駅まで
新津駅から青森駅までの長い道のりの途中で、新潟県の新発田(しばた)、坂町、村上、山形県の鼠ケ関(ねずがせき)、余目(あまるめ)、酒田、秋田県の羽後本荘、秋田、大館、青森県の碇ケ関、大鰐温泉(おおわにおんせん)、弘前(ひろさき)、川部、新青森といった駅を通ります。

羽越本線や奥羽本線では、日本海側の各県を結ぶために昔から多数の急行列車や特急列車が運行されてきました。
並行する新幹線の路線が存在しないこともあって、現在も新潟駅~酒田駅・秋田駅を結ぶ特急「いなほ」や、秋田駅~青森駅を結ぶ特急「つがる」「スーパーつがる」が運行されています。
なお、新潟市の中心的な駅である新潟駅は羽越本線上にはありません。
「いなほ」のような新潟駅を発着する列車は、新潟駅と新発田駅を結ぶ「白新線」を経由して、新発田駅から羽越本線に乗り入れてきます(新津駅~新発田駅間は経由しない)。
奥羽本線の秋田駅~青森駅間の電化は1971年8月に行われました。
また、羽越本線の電化は1972年8月に行われました(白新線も同時に電化)。
羽越本線の電化をもって、日本海縦貫線の大阪駅~青森駅間全区間の電化が完了したのです。
羽越本線は新津駅から村上駅が直流1,500V、村上駅(駅構内含まず)から秋田駅までが交流50Hz・20,000Vで電化されていて、電化方式が途中で変わる路線です。
そのため、電車・電気機関車を直通させるためには、両方の電化方式に対応している車両を使う必要があります。
一方、奥羽本線の秋田駅から青森駅までは、交流50Hz・20,000Vです。
急行「しもきた」(架線下を急行として運行されたのは盛岡駅→弘前駅、大鰐駅→盛岡駅)
急行「しもきた」の前身にあたる列車は1959年7月に登場した準急「八甲田」です。
岩手県の盛岡駅と青森県の大鰐駅(現:大鰐温泉駅)の間を、東北本線(※現:いわて銀河鉄道線・青い森鉄道線)と奥羽本線経由で結んでいました。
途中で通る青森駅は行き止まりの形の駅なので「八甲田」にとっては終着駅ではないものの列車の進行方向が変わります。
※いわて銀河鉄道線(盛岡駅~目時駅)と青い森鉄道線(目時駅~青森駅)は、いずれも当時は東北本線(現在は東京駅~盛岡駅)の一部区間でした。
「八甲田」は1961年に改称されて準急「しもきた」となります。
下北半島を通る大湊線に乗り入れるわけでもないのに、なぜか「しもきた」なのです。
1965年10月に準急「しもきた」は一旦消滅しました。
しかし、翌年の1966年10月には、盛岡発・碇ケ関行きと大鰐発・盛岡行きの急行列車として「しもきた」が復活します。
青森県側の始発駅と終着駅が違うという変わり種の列車でした。
また、碇ケ関行きの列車は、弘前駅から終着の碇ケ関駅までは、急行ではなく普通列車という扱いでした。
なお、当初から、機関車が客車をけん引するタイプの列車ではなく、気動車での運行です。

Olegushka – 投稿者自身による著作物, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156459014による
「しもきた」の経路の内、東北本線は1968年8月に電化されて、奥羽本線は1971年8月に電化されたものの、電車への置き換えはされなかったため、以降は全区間で架線下を走る気動車急行となりました。
1972年3月の時刻表によると、下記のダイヤで運行されていました。
盛岡駅から弘前駅までの241.3kmに3時間50分かかっていて、碇ケ関駅までの261.2kmでは4時間20分でした。
大鰐駅から盛岡駅までの253.1kmの所要時間は4時間30分でした。
- しもきた:113D(弘前駅から普通列車332D) 17時55分盛岡駅発 21時00分青森駅着(20時50分着の青函連絡船に接続) 21時10分青森駅発 21時45分弘前駅着 22時15分碇ケ関駅着
- しもきた:112D 6時10分大鰐駅発 7時04分青森駅着 (7時30分発の青函連絡船に接続) 7時25分青森駅発 10時40分盛岡駅着
(青函連絡船とは、青森駅と北海道の函館駅の間を結んでいた、鉄道路線同士を連絡する船です)
以後も1日1往復の気動車急行というスタイルは全く変わりませんでした。
おそらく、交流電化区間を走行できる急行用電車を、工面できなかったのでしょう。
1982年に東北新幹線が開業したことに伴い行われた11月のダイヤ改正において、急行「しもきた」は特急「はつかり」に格上げされる形で廃止されました。
特急化と同時に、485系電車の投入による電車化も行われています。

格上げ後の「はつかり」は、基本的には盛岡駅~青森駅間の運転でしたけれども、金曜・土曜・休日に限り、1日1往復の列車が弘前駅までの延長運転を行っていた点に、急行「しもきた」の後身であることがうかがえます(ただし、急行「しもきた」の運行時刻とは全く異なっていました)。
しかし、1986年11月の時刻表には「はつかり」の青森駅~弘前駅間延長運転の記載がないので、このときの改正で終了したものと思われます。
後身の「はつかり」は、2002年12月に東北新幹線が盛岡駅から八戸駅まで延伸したことに伴い、廃止されました。
なお、現在のJR東日本は快速「しもきた」という列車を運行しています。
この列車は大湊線の起点の野辺地駅、または青い森鉄道線の八戸駅から、大湊線の終点である大湊駅までの間で運行されています。
名前が示す通りに下北半島を走る列車です。

急行「羽越」(新潟駅~秋田駅)
1962年3月に準急「羽越」が、新潟駅~秋田駅間の列車として運行を開始しました。
1965年に一旦「羽越」は消滅するものの、1967年10月に新潟駅~酒田駅間に不定期の急行「羽越」が再度登場します。
1968年の10月に「羽越」は毎日運転の定期列車になった上、新潟駅~秋田駅間の運行に延長されました。
元に戻ったともいいます。
1972年8月に白新線・羽越本線が電化された後も「羽越」は気動車のままだったので、全区間架線下気動車急行となりました。
1972年10月には「羽越」は1日2往復に増発。
増発された列車も、気動車での運行であることは変わりません。
1978年10月の時刻表によると、ダイヤは下記のとおりです。
新潟駅から秋田駅までの273.0kmの所要時間は4時間半前後でした。
なお、現在の特急「いなほ」は3時間35分ほどかかっています。
- 羽越1号:811D 7時19分新潟駅発 8時08分坂町駅着(あさひ2号仙台行きを切り離し) 8時12分坂町駅発 10時18分酒田駅着 12時04分秋田駅着
- 羽越3号:813D 15時31分新潟駅発 16時20分坂町駅着(あさひ4号仙台行きを切り離し) 16時27分坂町駅発 18時20分酒田駅着 20時03分秋田駅着
- 羽越2号:812D 7時33分秋田駅発 9時06分酒田駅着 9時18分余目駅着(山形始発の月山1号を連結) 9時24分余目駅発 10時15分鼠ケ関駅着(月山1号を切り離し) 10時20分鼠ケ関駅発 11時56分新潟駅着
- 羽越4号:814D 12時35分秋田駅発 14時16分酒田駅着 17時04分新潟駅着
「羽越」は、別の気動車急行列車と連結して運行されていました。
電車と気動車は、一部の例外を除いて、連結して運行することはできないので「羽越」は運行区間が全て電化されているものの、引き続き気動車での運行となったのです。
「羽越」の連結相手の説明は若干複雑になります。
1978年10月時点では、秋田行きの「羽越1号」は、始発の新潟駅から途中の坂町駅まで急行「あさひ2号」と連結していて「羽越3号」は「あさひ4号」と連結していました。
「あさひ」は、新潟駅から仙台駅までを、白新線・羽越本線・米坂(よねさか)線・奥羽本線・仙山(せんざん)線経由(坂町、米沢、山形駅を経由)で結んでいた列車です。
米坂線は電化されていないので「あさひ」は気動車で運行する必要がありました。
一方、新潟行きの列車の内「羽越2号」は、途中の余目駅から鼠ケ関駅まで、急行「月山(がっさん)1号」と連結していました。
「月山1号」は、山形駅から鼠ケ関駅までを、奥羽本線・陸羽西線・羽越本線経由(新庄駅、余目駅経由)で結ぶ列車で、陸羽西線が非電化なので、やはり気動車で運行する必要がありました。
なお「月山」は、山形発・鼠ケ関行き(1号・5号)以外に、山形発・酒田行き(3号)、仙台発・酒田行き(5号)、酒田発・山形行き(2号・4号)、鼠ケ関発・仙台行き(4号)、鼠ケ関発・山形行き(6号)もありました
(わけがわからないと思ったかもしれませんけれども、筆者も書いていてわけがわからないです)。
仙台駅発着の列車は、仙台駅~山形駅間(仙山線の区間)では先ほど登場した「あさひ」と連結しており、山形駅~余目駅間では別の行き先の(号数が同じ)「月山」と連結していました。
いくらなんでもややこしかったのではないかと思います。
1982年(おそらく6月)には、連結相手だった「あさひ」が「べにばな」に改称されました。
11月に開業する上越新幹線の列車の愛称の1つとして「あさひ」が使われることになったので、急行「あさひ」の方が名前を変えたのです。
11月の上越新幹線開業のときに、急行「羽越」は特急「いなほ」に格上げされる形で廃止され、車両は485系電車に変更。
先ほど登場した急行「しもきた」も特急列車に格上げされる形で廃止されていましたけれども、国鉄時代末期からJR発足初期には、全国の各地で急行列車の特急列車への格上げ(または快速列車への格下げ)が行われていたのです。

「羽越」の連結相手だった急行「べにばな」は存続しますが、1985年3月には、運行区間が山形駅~新潟駅間に短縮されました。
おそらく仙台駅と新潟駅の間を移動する旅客は、東北・上越新幹線を乗り継いで移動するようになり「べにばな」を仙台駅から運行するほどの需要はなくなっていたのでしょう。
その後、山形新幹線の開業に向けた工事に伴い、従来の車両が米沢駅~山形駅間を通行できなくなります。
そのため、1991年に急行「べにばな」の運行区間は、新潟駅~米沢駅間へとさらに短縮された上で、快速列車に格下げされました。
以後、しばらく大きな動きはありませんでしたが、2022年8月に発生した豪雨災害で米坂線が被災したために、被災区間ではバス代行輸送が行われています。
被災以後は快速「べにばな」は運休しており、既に時刻表から抹消されています。
「月山」の方も存続しましたが、まず1982年11月の時刻表によると、仙台駅を発着していた「月山」は消滅したようです。
さらに1986年11月の時刻表を見ると、鼠ケ関駅発着の列車がなくなり、山形駅~酒田駅間での運行のみに改められています(酒田行きの月山1号のみ、酒田駅から普通列車として4駅北の吹浦駅まで運転)。
そしてJR発足後の1992年に快速列車への格下げが行われ、後に「月山」の愛称も消滅しました。
新庄駅~酒田駅間を結ぶ陸羽西線の快速列車には、その後「最上川」という愛称がつけられました。
しかし、陸羽西線自体が2022年5月より、近接する国道のトンネル建設工事のため運休中で、バス代行輸送が行われています。
急行「しらゆき」(金沢駅~青森駅)
1963年4月に石川県の金沢駅と東北地方を結ぶ急行「しらゆき」が設定されました。
下り列車は金沢発・秋田行き、上り列車は青森発・金沢行きでした。
1965年には下り列車も青森行きに延長されます。
近接していない地方の、大都市とはいえない都市同士を結ぶという、JR発足(1987年4月)以前の国鉄時代にしても、珍しい性質の急行列車でした。
ほとんどの急行列車は、大都市同士を結ぶ列車、大都市と地方都市を結ぶ列車、「羽越」のように比較的近い距離の地方都市同士を結ぶ列車のいずれかです。
経路の電化は1972年8月に完了したものの「しらゆき」は以後も気動車のままでした。
「しらゆき」の運行区間は772.4kmで、おそらく「全区間架線下を走る気動車急行列車」としては、日本の鉄道史上最長の運行区間です
(※「全区間架線下を走る気動車特急列車」ならば「なは」というもっと長い列車があります。
運行区間は大阪駅と西鹿児島駅、現在の鹿児島中央駅の間で、900kmを超えていました)。
1978年10月の時刻表によると「しらゆき」のダイヤは下記のとおりです。
金沢駅から青森駅までの772.4kmを乗り通すと、およそ12時間半もの長旅を楽しめ(?)ました。
また、青森駅で青函連絡船と乗り継げる時刻設定にはなっておらず、あくまで北陸・新潟・東北を結ぶための列車であったと考えられます。
- しらゆき:501D 9時49分金沢駅発 11時56分糸魚川(いといがわ)駅着(松本行きの白馬を切り離し) 12時02分糸魚川駅発 14時26分新潟駅着 17時16分酒田駅着 18時56分秋田駅着(仙台始発のきたかみ3号を連結) 19時21分秋田駅発 22時18分青森駅着
- しらゆき:502D 6時50分青森駅発 9時46分秋田駅着(仙台行きのきたかみ4号を切り離し) 9時57分秋田駅発 11時34分酒田駅着 14時15分新潟駅着 17時04分糸魚川駅着(松本始発の白馬を連結) 17時18分糸魚川駅発 19時17分金沢駅着
電車に置き換えられなかったのは、やはりまずは急行用の電車が工面できなかったためと思われます。
金沢駅から青森駅までの電化方式は、西から順に交流60Hz、直流、交流50Hzとなっていて、急行「しらゆき」を電車にするためには、3種類全ての電化方式に対応している高価な電車が必要なのです。
また「羽越」と同様に「しらゆき」も途中で別の気動車急行との連結を行っていました。
1978年10月時点の「しらゆき」は、金沢駅から新潟県の糸魚川駅までの間で、急行「白馬」と連結。
また、秋田駅から青森駅までの区間では、青森行きの「しらゆき」は急行「きたかみ3号」と、金沢行きは「きたかみ4号」と連結していたのです。
「白馬」は金沢駅と長野県の松本駅の間を、北陸本線(現:IRいしかわ鉄道線、あいの風とやま鉄道線、日本海ひすいライン)・大糸線経由で結んでいました。
「きたかみ」は仙台駅と青森駅の間を、東北本線・北上線・奥羽本線経由(北上駅・横手駅・秋田駅経由)で結んでいました。
大糸線の一部区間と北上線が電化されていないので、これらの列車は気動車で運行する必要があり、連結を行う限りは「しらゆき」も電車にはできなかったのです。
1982年11月に上越新幹線が開業したことに伴い、急行「しらゆき」は福井駅~青森駅館の運行に延長、そして特急「白鳥」への格上げと、485系電車化が行われました(ただし発着時刻は大幅に変わっています)。
「しらゆき」は消滅するそのときまで、最後まで気動車による1日1往復のみの運行でした。

著作者:Gohachiyasu1214 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123866005による
「しらゆき」の連結相手だった「白馬」は同時に廃止されました。
また「きたかみ」は快速に格下げされた上に、運行区間が北上駅から秋田県の湯沢駅までの区間に短縮されたので、日本海縦貫線への乗り入れは終了しています。
「しらゆき」の後身である福井駅発着の「白鳥」は、設定からわずか2年あまり後の1985年3月のダイヤ改正で、福井駅~新潟駅間の運行に短縮された上に、愛称も「北越」に変更されてしまいました。
その「北越」も2015年3月に北陸新幹線が長野駅から金沢駅まで延伸開業した際に廃止されています。
「北越」の後身と呼べる列車は、新潟県内だけを走る新井駅・上越妙高駅~新潟駅間(妙高はねうまライン・信越本線経由)の特急「しらゆき」です。
特急「しらゆき」は、急行「しらゆき」の後身(白鳥)の後身(北越)の後身ということになります。
しかし運行区間長があまりに違うので、いくら愛称が同じでも、同じ系譜の列車と呼んでよいのかは微妙なところでしょう。

急行「しらゆき」に関する単独解説記事はこちらです。
急行「むつ」(秋田駅~青森駅)
1963年10月に仙台駅~青森駅間を東北本線経由で結ぶ急行「むつ」が運行を開始しました。
1965年10月には「むつ」は仙台駅から青森駅を経て秋田駅までに運行区間を延長し、北東北を周遊するような列車となりました。
仙台駅から秋田駅までは、北上線(岩手県の北上駅と秋田県の横手駅を結ぶ路線)を通って行った方が距離が短いので、全区間を乗り通す乗客はほぼいなかったと思われます。
1968年10月には「むつ」のルーツだったはずの仙台駅~青森駅間の部分を、急行「くりこま」に譲り渡したので「むつ」は秋田駅~青森駅間の運転に改められました。
「陸奥(むつ)」とは主に東北地方の太平洋側を指すので、本来の陸奥という言葉のイメージからは遠い列車になってしまいました。
ちなみに「くりこま」も、1972年3月に電車化されるまでは全区間架線下気動車急行でした。
東北本線編で紹介しています。
1970年10月に「むつ」は増発されて1日2往復の運行となりました。
1971年8月に奥羽本線の電化が行われたものの「むつ」は気動車での運行が続けられ、全区間架線下気動車急行列車に。
やはり連結相手が気動車だったからだと思われます。
1972年3月の時刻表によると、当時の「むつ」のダイヤは下記の通り。
秋田駅から青森駅までの185.8kmの乗車時間は3時間10分~3時間29分です。
ちなみに現在の「スーパーつがる」だと2時間半ほど。
下記の4本とも、青森駅で青函連絡船と乗り継げる時刻設定ではなく、あくまで秋田と青森を結ぶことが目的といえる列車でした。
- むつ1号:615D 7時36分秋田駅発 9時18分大館駅着(宮古行きのよねしろ1号を切り離し) 9時22分大館駅発 11時00分青森駅着
- むつ2号:617D 17時29分秋田駅発 19時19分大館駅着 19時21分大館駅発 20時39分青森駅着
- むつ1号:616D 8時10分青森駅発 9時27分大館駅着(盛岡始発のよねしろ1号を連結) 9時34分大館駅発 11時20分秋田駅着
- むつ2号:618D (陸中八木始発の深浦と連結)17時40分青森駅発 (深浦行きの深浦を切り離し)18時17分川部駅発 19時12分大館駅着(宮古始発のよねしろ2号を連結) 19時23分大館駅発 21時09分秋田駅着
(現在は下り列車の号数が奇数、上り列車の号数が偶数になっていますが、1978年10月のダイヤ改正以前は、そのような区別がされていませんでした)
青森行きの「むつ1号」は、秋田駅から大館駅までで急行「よねしろ1号」と連結していました。
「よねしろ1号」は、秋田駅から岩手県の宮古駅までを、奥羽本線・花輪線・東北本線(現:いわて銀河鉄道線)・山田線経由(大館駅、好摩駅、盛岡駅経由)で結んだ列車です。
花輪線と山田線が非電化なので、気動車で運行する必要がありました。
秋田行きの「むつ1号」も、大館駅から秋田駅までで「よねしろ1号」と連結していましたが、秋田行きの「よねしろ1号」は宮古発ではなく盛岡発(山田線を走行しない)でした。
秋田行きの「むつ2号」も「よねしろ2号」と連結しており「よねしろ2号」は宮古発でした。
さらに「むつ2号」は、青森駅から川部駅までの区間で急行「深浦」とも連結していました。
「深浦」は岩手県の陸中八木駅から八戸線・東北本線(現:青い森鉄道線)・奥羽本線・五能線を経由(八戸駅、青森駅、川部駅、五所川原駅を経由)して、深浦駅まで運行されていました。
岩手県の北東の端辺りから、青森駅を経由して、青森県の西の端あたりまでという、今では考えられないような列車です。
八戸線と五能線が非電化なのでやはり気動車での運行が必要です。
また「深浦」は八戸線内と五能線内の双方で普通列車として扱われていた時期があり、この場合急行列車として運行される区間は東北本線と奥羽本線内のみになります。
そういう意味では「深浦」も「急行列車として運行される全区間」が電化されている列車ではありました。
1982年11月には「むつ」がさらに1往復増発されて1日3往復になります。
一方で、他の列車との連結運転は縮小されて、青森行きの「むつ5号」のみが、大館駅~弘前駅間で「よねしろ3号」と連結していました。
「よねしろ」の運行区間は以前と変わっていて、盛岡駅から東北本線(現:いわて銀河鉄道線)を北上してから花輪線に入り、大館駅からは奥羽本線を秋田駅方面には行かず、大館駅止まりとなる列車が1日1往復、北の弘前駅まで行く列車が1日1往復になっていました。
1985年3月には急行「むつ」は
- 特急列車に格上げ
- 485系電車化
- 1日1往復に削減
以上が行われ、気動車急行としての「むつ」は消滅しました。
急行「むつ」と連結していた「よねしろ」は同時に快速「八幡平(はちまんたい)」に格下げ。
「八幡平」は2015年3月に廃止されました。
そして、特急「むつ」誕生からおよそ1年半後の1986年11月に、特急「むつ」も廃止されます。
「むつ」が果たしていた秋田駅と青森駅を結ぶ役目は、新潟駅と青森駅を結ぶ特急「いなほ」や、盛岡駅と青森駅を田沢湖線・奥羽本線経由(大曲駅・秋田駅経由)で結ぶ特急「たざわ」に受け継がれます。
その後、1997年3月に秋田新幹線が開業したことに伴い、秋田駅~青森駅間を結ぶ特急列車は「かもしか」と名づけられます。
さらに、2010年12月に東北新幹線が八戸駅から新青森駅まで延伸開業したことに伴い、秋田駅~青森駅間の特急は「つがる」に改められ、2024年3月には停車駅の少ない「スーパーつがる」も登場し、現在に至っているのです。

急行「こまくさ」(山形駅~秋田駅・青森駅)
山形駅~青森駅間を奥羽本線経由で結んでいた急行「こまくさ」も、日本海縦貫線の一部区間を経由する全区間架線下気動車急行列車でした。
奥羽本線・仙山線編で解説済みなので、ご覧ください。
終わりに
今回で全区間で架線下を走った気動車急行・特急シリーズは終わりの予定です。
筆者の手持ちにある時刻表からわかる範囲で、東北地方の該当する定期列車は全部紹介したと思います。
「昔はこんな列車があったのか」という驚きを経験していただけたならば幸いです。
余談になりますが、このシリーズでとりあげた「全区間架線下気動車列車」は、普通列車に限れば現在もたくさんあります
(特急列車も、西日本にいくつかあります。「らくラクびわこ4号」「まいづる5号・15号・6号・14号」「はしだて9号」など)。
特に今回の記事の対象となった羽越本線では、村上駅~間島駅間(電化方式が変わる区間)をまたぐ全ての普通列車と、臨時快速「海里」(新潟駅~酒田駅)が気動車によって運行されているのです。
鉄道で活躍する車両は電車ばかりではありません。
気動車も電化の有無や電化の方式にかかわらず自走できるという長所を活かして、広く活躍しているのです。