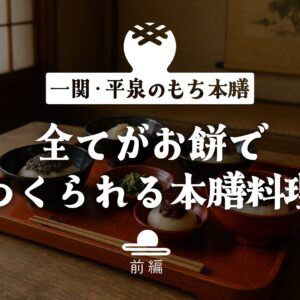【青森県五所川原】ド迫力!「五所川原立佞武多」の歴史と感動が年中体感できる「立佞武多の館」
目次
青森市の「ねぶた」、弘前市の「弘前ねぷた」とともに「青森三大佞武多」に数えられる「五所川原立佞武多(ごしょがわらたちねぷた)」は、青森県五所川原市で毎年8月4日から8日まで開催される夏祭りです。
色鮮やかなねぷたと「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の威勢のいい掛け声が青森の短い夏の夜空に響き渡り、人々に感動と興奮を与えてくれます。
今回はそんな青森の夏の風物詩、五所川原立佞武多をいつでも体感できる施設「立佞武多の館」について紹介します。
五所川原立佞武多とは
明治中期から大正にかけて、五所川原は津軽平野のもたらす豊かな農産資源で繁栄。多くの力をもった豪商や地主を生み出しました。程なくしてそんな資産家たちが自分達の力の象徴として、夏祭りに山車(ねぷた)を出すようになりました。
力と財力の象徴として出している以上、他人に負けるわけにはいかず、競い合いの末ねぷたはどんどん巨大化していったそうです。
そんな理由ですから祭りの最中に他者のねぷたとかち合えば、言い合いからの喧嘩も当たり前。立佞武多のヤッテマレの掛け声はその当時の「やってしまえ!」からきたものと言われているそうです。かなり物騒な成り立ちですね!
五所川原立佞武多の特徴
五所川原立佞武多の最も大きな特徴は、なんといってもねぷたの大きさにあります。
祭りに使われるねぷたの高さは20メートル以上、重さは約19トンにも及び、運行には数十人の力が必要です。

祭り当日はこの大型佞武多が3台運行されるほか、企業や高校生などが製作した中型佞武多、太鼓や笛、手平鉦で構成されるお囃子(はやし)方とハネト達がともに五所川原中心市街地を練り歩き、祭りを盛り上げます。
幻のねぷたを90年ぶりに現代に蘇らせた
今や青森県を代表する夏祭りのひとつとなった五所川原立佞武多。
五所川原市で巨大なねぷたづくりが最も盛んに行われていたのは明治後期で、ピーク時には高さ30メートル級のねぷたが作られていたといわれています。
しかし、電線の普及と同時にねぷたの高さは制限されていき、時代の移り変わりとともに小型のねぷたへと変化していきました。

ねぷたの小型化以降、五所川原市の巨大ねぷたの伝統は途切れていましたが、明治時代の写真と台座の図面が発見されたことをきっかけに市民の有志らが高さ22メートルの巨大ねぷたを再現することに成功。1,996年に「五所川原立佞武多」として90年ぶりに祭りを復活させました。
祭りの感動をそのままに伝える「立佞武多の館」
五所川原市の中心部に高さ38メートル、地上6階建てのひと際目立つ建物がそびえたっています。
これが「立佞武多の館」です。

こちらの施設では祭りで実際に使用した大型ねぷたが常時3台展示されているほか、大型多佞武多の製作・保管場所としての役割も兼ね備えています。
圧巻の立佞武多出陣
五所川原立佞武多当日、立佞武多の館の壁面が開き大型立佞武多が顔を出します。

例年、立佞武多の館から巨大な立佞武多が祭りに出陣する瞬間は多くの見物客が駆け付け、祭りの見どころのひとつとなっています。
「立佞武多の館」の見どころ
立佞武多の保管というのがメインの役割ですが、館内にはその他にも見どころが多数あります。各所を順に紹介します。
立佞武多展示室
立佞武多の館のメインともいえる「立佞武多展示室」。見学順路は、ねぷたを上から見下ろせる高さの4階からスタートです。

らせん状のゆるやかな通路を下りながら大型佞武多を至近距離でじっくり観察できるほか、立佞武多の歴史を学べる資料が多数展示されています。
巨大スクリーン上映
立佞武多展示室内にある巨大なスクリーンでは、立佞武多の歴史や五所川原の美しい自然や風景が堪能できます。

五所川原立佞武多当日の様子も上映され、まるで祭りに来ているかのような臨場感がいつでも味わえます。
立佞武多製作所
立佞武多が実際に製作されている様子や進行状況を見学できる「立佞武多製作所」も見どころです。
大型佞武多は50個ほどのパーツに分けて半年以上の期間をかけて作られ、約2日間の間に立佞武多展示室内でクレーンを使って組み立てられます。
4月から6月頃までの期間はねぷたへの無料紙貼り体験も実施されています。
中型佞武多を間近にみる多目的ホール
休憩スペースとなっている多目的ホールでは、祭りで実際に使われた中型佞武多を無料で見学できます。

新型コロナウイルス感染症により五所川原立佞武多が3年ぶりの開催となった2022年は、祭りの先頭を運行した人気ゲームシリーズ「桃太郎電鉄」、通称「桃鉄」の中型佞武多が展示され、そのユニークな姿で多くの見物客を楽しませていました。
立佞武多の館<Information>
- 施設名称:立佞武多の館
- 住 所:青森県五所川原市大町506-10
- 電話番号:0173-38-3232
- 公式URL:立佞武多の館
Google Maps
おわりに
五所川原市民の熱い想いによって90年の時を経て復活した巨大立佞武多。
その姿をいつでも間近で見学できる「立佞武多の館」は青森県観光にぴったりのスポットです。ぜひ訪れて夏の感動を体感してみてはいかがでしょうか。