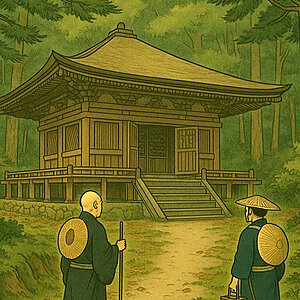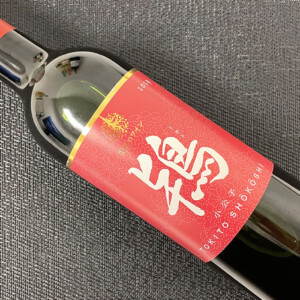【鳥海山・飛島ジオパーク:飛島編】江戸時代に北前船で栄えた飛島
目次
飛島は、酒田市沖の日本海に浮かぶ山形県唯一の離島です。面積は約2.75平方㎞で周囲は10kmほど。人口は169人(令和4年12月)で漁業が主な産業となっています。江戸時代は酒田へ出入りする北前船の“風待ち港”として賑わっていて、年間400隻もの舟が立ち寄ったといわれています。
島の周囲を暖かい津島暖流が流れているため年間を通して暖かく、年平均気温は12℃以上で、積雪も10cm未満となっています。島の成り立ちがあらわになった自然や、縄文時代の遺跡などもあり鳥海山・飛島ジオパークとして自然探索も楽しめる島です。
縄文時代から人が住んでいた飛島
飛島は1900万年程前にユーラシア大陸から分離し、海底火山の堆積物が地殻変動で盛り上がり、それが波や風による浸食などによって、何百万年もかけて今の形になったといわれています。本土からも近く、比較的温暖で海産物も多く獲れたこともあって縄文時代には人が住んでいました。島内の遺跡からは約6000年前、縄文時代の土器などが発見されています。
トドが多く生息していたので“とど島”と呼ばれていた
平安時代以降室町時代までの正確な記録は残っていないのですが、「テキ穴」といわれる遺跡からは平安時代と思われる人骨などが見つかっています。

「飛島」と呼ばれるようになったのは江戸時代初期で、それまでは都島、渡島、別れ島、とど島などいくつもの名称が使われていました。“とど島”はとどがいっぱい生息していたかららしく、江戸時代の古文書には“とど島”という表記が多く登場していて、“とびしま”はとどから変わったといわれています。
一説によると鳥海山が爆発した際に飛び出した山の一部が「飛島」になったという説もあるのですが、それはあくまで俗説です。
名産のイカを年貢として納めていた江戸時代
戦国時代以降「飛島」の領主は由利氏、武藤氏、最上氏、酒井氏と変わっていきます。江戸時代最初の領主最上氏は島民から年貢としてイカを売った金を“烏賊税(いかぜい)”という形で徴収するようになりました。
その後庄内藩主となった酒井氏も“烏賊税”を存続させたのですが、イカそのものを納めさせるという形に変更しています。
北前船の風待ち港として繁栄した勝浦港

江戸時代から明治にかけての「飛島」は、北前船の寄港年間400~500隻もあったといわれています。
北前船は、鉄道やトラックなどがない時代に、日本海側の各地に寄港しながら大阪方面と東北、北海道を行き来して巨額の富を得た廻船ですが、本来の積み下ろし港である酒田港は北西の季節風の影響を受けやすく、悪天候では港に入ることができません。そのため、酒田沖にあり、北西からの風を受けない立地だった飛島の勝浦港は、絶好の風待ちの港だったのです。
酒田は過去大火や大地震などに襲われ、寄港した北前船やその乗員を記した客船帳はほとんど残っていません。
どんな船がどのくらい入港していたかが分からなかったのですが、「飛島」は大火もなく災害も受けなかったため、江戸時代には13軒、明治以降は9軒あった船宿には客船帳が残っていました。その船がそのまま酒田港に入ったと考えられるため、貴重な資料となったのです。
「鳥海山・飛島ジオパーク」として注目される飛島
飛島は1,000万年以上前に誕生したといわれ、海底火山の堆積物や波に洗われてできた不思議な形をした岩や洞窟があり、さまざまな伝説も伝わっています。その成り立ちや地層、自然の造形など、地球を考えるのに最適な場所として「鳥海山・飛島ジオパーク」に認定されています。
柏木山と海岸遊歩道

「飛島」の南端にある勝浦港周辺に位置し、勝浦港の風よけとなった「舘岩」や「柏木山」などが連なっています。海岸沿いには遊歩道が設けられ、「賽の河原(さいのかわら)」と名付けられた火山性の石がゴロゴロした浜や、溶岩が流れた筋状の跡が見られる岩に触れることができます。
柏木山にはトビシマカンゾウが自生しており、酒田市の天然記念物にも指定されています。

トビシマカンゾウは飛島と佐渡島だけにしかない花で、ニッコウキスゲの仲間です。
佐渡島の大野亀(おおのがめ)にある大群落が有名ですが、かつては飛島中に咲いていたそうです。最近は数が減っていて保全活動が行われています。
ミルフィーユ状の崖が特徴的なゴトロ浜

島の南西部にある「ゴトロ浜」にはミルフィーユのような層になっている高さ20mの崖があります。海底火山から吹き出た火山弾と火山灰が交互に積み重なったもので、飛島がかつて海底にあったことが分かります。
火山だった痕跡が残る御積島

「御積島(おしゃくじま)」は、飛島の西、1kmほどのところにあるごつごつした岩でできた小さな島で、流紋岩というマグマが地表かその近くで固まった岩石でできています。
北側にある波が浸食してできた洞窟には、「龍の鱗」といわれる黄金色をした岩肌があり、龍神の住む聖地として島民や船乗りに信仰されてきました。
「日本の渚百選」に選ばれた荒崎海岸

海底火山から噴出した礫凝灰岩や軽石などでできた「荒崎海岸」は、「日本の渚百選」に選ばれるほど日本海に沈む夕日が美しい海岸です。周辺ではトビシマカンゾウなどの自生地もあり、飛島一の景勝地です。
「日本の渚百選」に選定された記念に「渚の鐘」が海岸を望む高台に設置されています。
鳥海山も望める最東端の「鼻戸崎展望台」

飛島の最東端にある「鼻戸崎」は北に鳥海山、南に勝浦港が望める景勝地です。屋根付きの展望台があり、景色を堪能できます。
平安時代の人骨が発見された「テキ穴」

「テキ穴」は、勝浦港と鼻戸崎の間にある洞窟で、1964年(昭和39年)に平安時代のものと推定される22体の人骨や遺物が発見されています。何故平安時代に人が住んでいたのかなど、謎が多いままです。
酒田港からの定期船で飛島へ

「鳥海山・飛島ジオパーク」に認定されたこともあり、最近注目されている飛島。
島までは酒田港から酒田港から定期船とびしまで約75分です。地球の不思議な造形探索を絶景とともに楽しんでください。
飛島<Information>
- 所在地:山形県酒田市船場町2-5-6【定期船発着所】
- 電話番号:0234-22-3911(定期航路事業所)
- 定期船運賃:おとな 片道2140円、こども (小学生、幼児)1070円
- 営業時間:定期船は1日1~3航海
- ※気象状況により欠航の場合があります。電話で確認してください
- アクセス
- 酒田港から定期船とびしまで75分、飛島勝浦港
- 駐車場
- 定期船乗り場前にあり(大型可)
- URL:「とびしま」運行状況