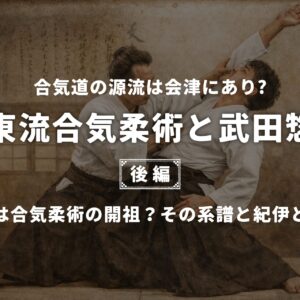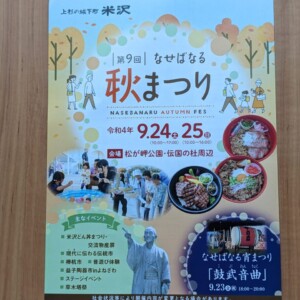【秋田県】東北の夏祭り秋田代表「竿燈まつり」を楽しむ前に!知っておきたい歴史や豆知識をご紹介
目次
東北の夏祭りを代表する秋田竿燈まつり、ぜひ足を運んでみたいけれどどのようなお祭りなのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では秋田竿燈まつりを見に行く前に知っておきたい竿燈まつりの歴史や豆知識を解説します。
秋田竿燈まつりとは?

秋田竿燈まつりは例年8月3日~8月6日に秋田県秋田市で行われる祭りで、1980年に国の重要無形文化財に指定されています。
また青森県のねぶた祭り、仙台の七夕祭りとともに「東北三大祭り」の1つとされているのを知っている人も多いでしょう。さらに山形の花笠まつり、岩手のさんさ踊り、福島のわらじ祭りとあわせて「東北六大祭り」の一角としても有名です。
竿燈まつりの歴史

秋田竿燈まつりの歴史は古く、七夕行事の1つで夏の睡魔を穢れとして形代などで流す「眠り流し」がその起源とされています。
眠り流しは全国各地で行われますが特に東北地方で盛んに行われ、東北3大祭りは全て眠り流しを起源としているだけではなく、秋田県内でも能代の眠流し(ねぶながし)、横手のねむり流しが有名です。
秋田市外に住む人は秋田竿燈まつりを「秋田県の祭り」と感じ、能代の眠流しや横手のねむり流しを「地元の祭り」と感じる人が多いのは秋田県内各地で眠り流しが行われているからなのでしょう。
竿燈まつりが初めて文献に登場したのは1789年で、国学者である津村淙庵によって書かれた「雪の降る道」の4巻に現在の竿燈と似た絵が描かれ、旧暦の7月6日に行われたねぶりながしが紹介されています。
その後ろうそくや提灯が少しずつ庶民にも浸透するにつれ、今の形になったのではないかと言われているのです。
参考:国立国会デジタルコレクション 津村淙庵「雪の降る道 4巻」
知っておきたい!秋田竿燈まつりの豆知識

秋田竿燈まつりを見る前に、知っておきたい豆知識を3つご紹介します。
【豆知識1】竿燈の見どころをYouTubeで学べる
秋田竿燈まつりの見どころは、オンラインワークショップとして
- 竿燈の歴史・見どころ
- 竿灯妙技<差し手>
- 竿燈妙技<囃子方>
の3つがYouTubeにて公開されています。

現在の竿燈まつりに至るまでの経緯や裏話から竿燈の差し方、太鼓や笛などを使ったお囃子についてまで詳しく解説されているので、事前に竿燈について知っておきたい人はぜひ動画に目を通してみてください。
【豆知識2】秋田以外でも竿灯がみられるイベントがある
竿燈は秋田以外の地域でも、その雄々しい姿を見ることができます。
例えば都内であれば「秋田竿燈浅草まつり」や、「うえの夏祭りパレード」で演技を見ることができるのです。
最新のイベント参加情報は秋田竿燈まつり公式サイトに掲載され、イベントが終わると「出竿総集編」のページでその時の画像を見ることができるので、興味のある人は目を通してみましょう。
まとめ
秋田竿燈まつりは国の重要無形文化財に指定されており、青森県のねぶた祭り、仙台の七夕祭りとともに「東北三大祭り」及び「東北六大祭り」の1つとされています。この記事も参考に竿燈まつりへの知識を深め、会場に足を運んでみてください。