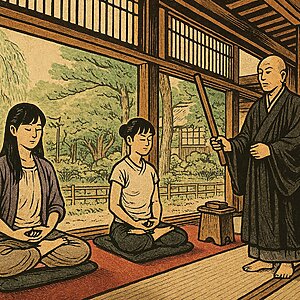久保田藩や庄内藩に挟まれて本荘・亀田・矢島各藩が割拠していた由利本荘市【秋田県】
目次
江戸時代まで山形県と秋田県のエリアは1つの国として扱われていた
由利本荘市は、山形県との県境にそびえる鳥海山(ちょうかいさん/標高2236m) の北側に位置し、にかほ市とともに秋田県由利郡を構成していた自治体です。
1871年(明治4年)に発足した秋田県由利郡には江戸時代より多くの町村が存在していましたが、2005年(平成17年)に町村合併により、由利本荘市とにかほ市が誕生しました。
飛鳥時代の710年頃、現在の秋田県と山形県をほぼ併せたエリアは出羽国(でわのくに)と定められました。
出羽国はそれから江戸時代まで1国として扱われており、明治時代に突入した1868年(明治元年)にはじめて羽前国、羽後国に2分割されました。
羽前国は現在のほぼ山形県のエリアで、羽後国は秋田県にあたります。1871 年(明治4年)には羽後国が正式に秋田県、1876年(明治9年)には羽前国が山形県になりました。
戦国時代は10以上の小さな豪族が割拠していた由利地方
由利本荘市のある由利郡は、平安時代までは陸奥国に勢力をもっていた安倍氏、清原氏、藤原氏と支配者が変わっていったのですが、藤原氏が源頼朝によって滅ぼされて鎌倉時代に突入してからは小規模な豪族が群雄割拠する時代に入ります。
一時的に信濃国(長野県)の大井氏が幕府の命を受け由利郡に入りますが、鎌倉時代の終わり頃からは再び戦乱の時代に突入しました。
室町時代の中頃、応仁の乱(おうにんのらん/1467年~1477年)が始まった頃には、“由利十二頭”と呼ばれる豪族(武家)たちが台頭してきます。
“由利十二頭”とは仁賀保(にかほ)氏・子吉(こよし)氏・潟保(かたほ)氏・滝沢氏・矢島氏・到米(とうまい)氏・下村氏・石沢氏・打越(うてち)氏・赤尾津(あこうづ)氏・羽根川氏・岩屋氏・鮎川氏・芹田氏などで実際は12氏族以上いました。
“由利十二頭”が勢力争いをしながら由利郡を治める時代は戦国時代末期まで続きます。
江戸時代にはそれほど面積が大きくない由利地方に3つの藩が成立

江戸時代になると現在山形県エリアを支配していた山形藩最上氏が由利郡の領主となります。
しかし、最上氏は江戸時代初期に当主を巡る内紛(最上騒動)により1622年に江戸幕府から大きな懲罰を受け没落します。
最上氏の支配から離れた由利郡には“本荘藩”、“亀田藩”、“矢島(やしま)藩”という3つの小さな藩が成立、3藩体制が幕末まで続きました。明治維新後1871年(明治4年)に3藩は本荘県、亀田県、矢島県となりましたが、その3県はすぐに秋田県に編入されています。
百合の里だったから名称がつけられたといわれる由利郡
由利本荘市の名称にある“由利”は、飛鳥時代に決められた郡の名前に由来します。
当時の古文書には“百合”や“油里”“油理”など表記はバラバラに登場しますが、“ゆり”と発音することは間違いなさそうです。現在の“由利”と統一されたのは、江戸時代の元禄年間だといわれています。

この地方が“ゆり”と呼ばれたのにはどんな訳があったのでしょう。由利本荘市の南にそびえる鳥海山にはユリ科の花、ニッコウキスゲの大群落があります。
鳥海山の沖に浮かぶ飛島(山形県酒田市)にも、飛島と佐渡島(新潟県)にしか自生していないトビシマカンゾウというユリの一種が初夏の島を彩ります。
このことから考えても鳥海山の裾野一帯にもユリが自生していたと考えるのが自然で、郡名としても“ゆり”とつけられたとの説が有力になっています。
最上氏没落後由利郡には仁賀保藩を含む4つの藩が誕生していた
江戸時代、最上氏の没落で由利郡に誕生したのは、本荘藩、亀田藩、矢島藩のほか、象潟(きさかた)で知られるにかほ市エリア仁賀保藩も立藩されています。
しかし、初代藩主が1年もたたないうちに亡くなり、仁賀保藩は廃藩になり、その領地はほとんどが幕府領になり、その後庄内藩の領地になりました。
由利本荘市を構成する3つの藩は、どのような経緯で誕生したのでしょう。
豊臣秀吉死後の覇権争いで、徳川家康率いる東軍と反徳川で結束する西軍が戦った関ヶ原の戦い(1600年)の際、由利郡の豪族たちは概ね徳川側についていましたが、あまり積極的ではありませんでした。
戦いは徳川方の勝利に終わり、由利勢はその不誠実さをとがめられ、多くが領地を没収されてしまいました。由利勢のいなくなった由利郡は、戦功の高かった最上氏の領地となり、郡主には楯岡満茂(たておかみつしげ/本城道茂)が就任します。
ところが1622年には最上騒動により領地を取り上げられ(最上氏改易)、最上家は近江大森(滋賀県東近江市)に57万石から1万石に減らされ移動させられてしまいました。当然ながら満茂も解任されてしまいます。
地元出身ではない地方大名が江戸幕府の命令で赴任した由利3藩
最上氏没落後旧最上藩の領地は、鳥居忠政(とりいただまさ/山形藩/山形県山形市)、酒井忠勝(さかいただかつ/庄内藩/山形県鶴岡市・酒田市)、戸沢政盛(とざわまさもり)/新庄藩/山形県新庄市)などの大名により多くの藩が作られます。
由利郡は、本荘地区(由利本荘市中央部)には常陸国から六郷政乗(ろくごうまさのり) が、亀田地区(由利本荘市北部)には信濃国から岩城吉隆(いわきよしたか)が入り、本荘藩、亀田藩を立ち上げます。
矢島地域(由利本荘市南部)には打越氏という由利十二頭に列せられていた豪族が領主として復帰しまたしが、後に讃岐国から生駒氏がやってきます。
六郷氏が幕末まで支配し、由利で最も栄えた本荘藩

本荘藩は、由利本荘市の中央部を占めるエリアにあった藩で、現在は市役所が置かれ、市の中心部として発展しました。
本荘城(鶴舞城)の跡地は本荘公園として整備され、JP羽越本線羽後本荘駅は由利高原鉄道鳥海山ろく線の起点ともなっています。
江戸時代に入り、最上氏からは派遣された楯岡満茂は、交通の要所だった子吉川(こよしがわ)南岸に城を築き、領主として本城性を名乗りました。しかし、1622年の最上騒動で満茂は解任され、本城城も取り崩されてしまいます。

翌1623年、常陸府中藩(ひたちふちゅうはん)1万石(茨城県石岡市/のちの石岡藩)の六郷政乗が2万石に増石され本荘に移ってきて本荘藩を興します。
政乗は本荘城を修復し、居城とします、その後六郷氏は明治維新まで11代にわたって本荘藩の藩主として過ごしました。

日本海に注ぐ子吉川沿いの古雪(ふるゆき/由利本荘市古雪町)には港(古雪湊)が設けられ、大阪と東北、北海道を行き来する廻船、北前船が立ち寄るようになり、大いに栄えました。
本荘城址・本荘公園<Information>
- 施設名称:本荘城址・本荘公園
- 所在地:秋田県由利本荘市尾崎
- 電話番号:0184-24-6376(由利本荘市観光文化スポーツ部観光振興課)
- 散策自由
- URL:本荘城址・本荘公園
- アクセス:
- 鉄道/羽越本線羽後本荘駅から徒歩約18分
- 車/日本海東北自動車道本荘ICから約7分
Google Map
2万石を与えられ幕末まで岩城氏が藩主をつとめた亀田藩

亀田には1623年、信濃国川中島(しなののくにかわなかじま)の松代藩1万石岩城吉隆(いわきよしたか)が転入し、2万石を与えられて亀田藩を立ち上げました。
岩城氏は亀田城を築き明治維新まで13代にわたって亀田の領主を努めます。亀田藩は子吉川の北側に位置していて、川沿いの石脇湊(いわきみなと)は、対岸の本荘藩古雪湊とともに、北前船で大いに賑わいました。

岩城吉隆は、1626年になって叔父に当たる久保田藩初代藩主佐竹義宣(さたけよしのぶ)の養子になり、佐竹義隆と改名します。義宣の死後は2代目藩主となり、久保田藩の基礎を固めました。

亀田城跡<Information>
- 施設名称:亀田城佐藤八十八美術館
- 所在地:秋田県由利本荘市岩城下蛇田字高城4
- 電話番号:0184-74-2500
- 開館時間:9:00~17:00(11月~2月は16:00まで)
- 休館日:月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日~1月3日
- 入館料:一般 210円、学生等 無料
- URL:亀田城佐藤八十八美術館
- アクセス:
- 鉄道/JR羽越本線羽後亀田駅から徒歩約20分
- 車/日本海東北自動車道松ヶ崎亀田ICから約4分
Google Map
問題を起こし減石され讃岐から移された生駒氏の矢島藩

矢島藩は、由利郡の南の部分、北は本荘藩、南は鳥海山の裾野で庄内藩と接する藩です。
矢島地域は、戦国時代には大井氏(矢島氏)が八森城(矢島城)を築城し支配していました。江戸時代に入り最上氏の支配下となり、最上氏改易後は1623年に由利十二頭のひとり、打越光隆(うていちみつたか/うてちみつたか)が領主となりました。
しかし、打越氏が領主の時代は2代のみで、その後1660年に生駒(いこま)氏が高松藩(香川県)から入城するまでの間のことは、よく分かっていません。
生駒氏は高松藩17万石の藩主でしたが、1640年3代目藩主高俊(たかとし)の時代に家臣たちによる対立抗争を収拾できなかったために、幕府より全領地を没取されてしまいます。そのかわりに移動させられたのが矢島で、堪忍料としてお情けで1万石が与えられました。
高俊の死後、矢島1万石はこども2人に分割相続されたため、8,000石で藩を継いだ高清は1万石以上が藩主となれるという原則にはずれ、藩主として資格を剥奪されます。
高清以降の生駒氏は、交代寄合(こうたいよりあい)という格式に降格されていて、明治維新時に再興するまでの間、領主ではあるけど藩主ではないという中途半端な状態が続きました。
交代寄合とは、領地に住むことは許され、参勤交代もしなければならないという譜代大名に準ずる格です。
明治維新時にようやく新政府の許しを得て生駒藩は復活しましたが、わずか3年で廃藩置県となり、矢島藩は消滅しました
八森城(矢島城)址<Information>
- 施設名称:八島神社
- 所在地:秋田県由利本荘市矢島町城内字八森3
- 電話番号:0184-56-2141(八島神社)
- URL:八森城(矢島城)址
- アクセス:
- 鉄道/由利高原鉄道鳥海山ろく線矢島駅から徒歩で約分
- 車/日本海東北自動車道本荘ICから約30分
Google Map
久保田藩とともに新政府側について反政府軍と戦った戊辰戦争
明治維新の時新政府と、それに反対する勢力が雌雄を決する戊辰戦争(ぼしんせんそう/1867年)が勃発しました。
当初陸奥国・出羽国に越後国(新潟県)を加えた諸藩は奥羽越列藩同盟を結成し、新政府に対して徹底抗戦の構えを見せます。しかし、久保田藩が同盟を離脱してしまい、同盟軍と相対することになりました。
由利3藩も同盟に加わっていましたが、3藩とも久保田藩に同調し、同盟を離脱します。
離脱後は久保田藩を含め、同盟側の庄内藩や南部藩の総攻撃を受け、3藩とも甚大な被害を受けます。
本荘藩は本荘城、矢島藩も陣屋に自ら火を放って撤退し、亀田藩は降伏して同盟軍に加わるなど、由利はほとんど同盟軍に占拠されてしまいます。
しかし、その窮状を知って新政府軍が同盟軍に対して大攻勢をかけ、戦況は改善します。最終的には新政府軍が勝利し、由利3藩も復活、羽後国(秋田県)の所属となったのです。