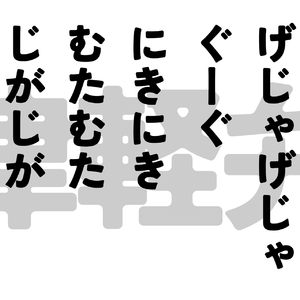仙北角館を最初に領有した戸沢氏は新庄藩の藩主まで上り詰めた勝ち組大名【仙北市の見所①】
目次
秋田県仙北市(せんぼくし)は、2005年(平成17年)に旧仙北郡田沢湖町(たざわこまち)、旧仙北郡角館町(かくのだてまち)、旧仙北郡西木村(にしきむら)の3町村が合併して誕生した新しい自治体です。
秋田県の東部中央に位置し、エリアの中央部に日本一深い田沢湖、南部に武家屋敷などで人気の角館があります。田沢湖の東には乳頭温泉郷や玉川温泉などの日本屈指の秘湯群が控え、西側(旧西木村)は、江戸時代には多くの鉱山が開発された地域です。
また、「ささら踊り」や幻想的な「紙風船上げ」など多くの民俗芸能や行事が残されている地域でもあります。
角館は観光客数が秋田県第2位。桜シーズンに秋田県で最も多くの観光客が訪れる

仙北郡は現在も美郷町(みさとちょう)が所属する郡として残っていますが、最南部の美郷町を除いて、中央部は大仙市(だいせんし)となり、北部が仙北市となっています。
大仙市や仙北市になった地域には江戸時代に180あまりの町村があったとされていますが、明治時代以降村同士の合併が繰り返され、最終的に田沢湖町・角館町・西木村が仙北市、それ以外は大仙市となったのです。
角館には秋田新幹線・JR田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道の駅があり、仙北市の玄関口になっています。
仙北市を訪れる観光客数は秋田市に次ぐ第2位(秋田市年間延べ746万人/仙北市約476万人)になっていて、イベントとしての集客数は「角館の桜まつり」(集客数約140万人)が秋田市の「秋田竿燈(かんとう)祭り」(約130万人) をしのいで第1位です(データは「令和元年秋田県観光統計」による。令和2年~令和6年は新型コロナの影響で観光客数が激減したため対象外)。
岩手県から奥羽山脈を越えてやってきた戸沢氏
仙北地方には、田沢湖を中心に古代から人が住んでいたことが、発掘された遺跡から分かっています。その後飛鳥時代(6世紀末~7世紀)には、奈良の大和朝廷が蝦夷(えみし)と呼んでいた東北地方に進出し、歴史書などに仙北地域の地名なども見えてきます。
平安時代には、前九年の役(ぜんくねんのえき/前九年合戦/1051年~1062年)、後三年の役(ごさんねんのえき/後三年合戦/1083~1087年)で知られる清原氏(きよはらうじ/きよはらし)、その後平泉(岩手県平泉町)を本拠とする奥州藤原氏が仙北地方を支配していたと考えられています。
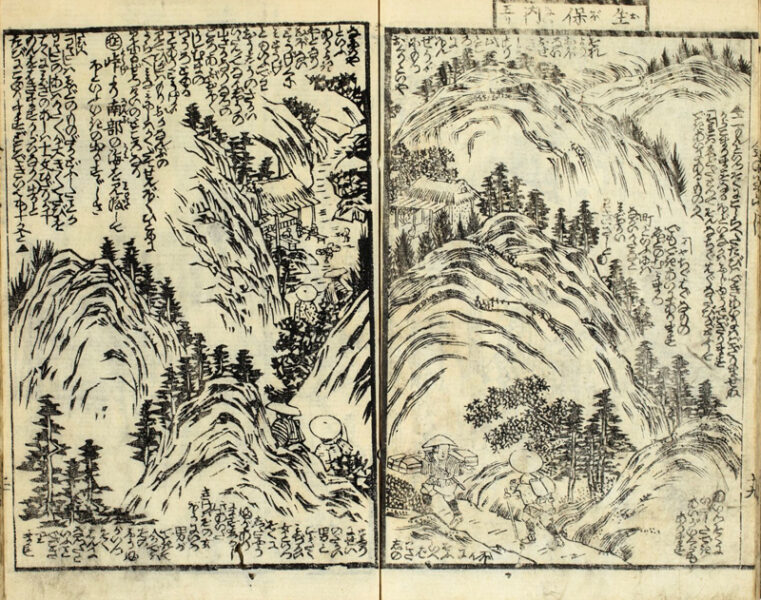
鎌倉時代の1228年に、陸奥国(岩手県など)滴石戸沢(しずくいしとざわ/雫石/岩手県雫石町字古館)の豪族戸沢氏(とざわし)が、奥羽山脈を越えて進入し、仙北の門屋(かどや/仙北市西木町門屋)に城を築きました。一説によると戸沢氏は陸奥国で大勢力だった豪族南部氏に追われて、命からがら門屋にやって来たといわれています。
戸沢氏は平家の出で、源氏に味方して地位を築いた
戸沢氏は、もともと平安時代後期に都で勢力を強めていた平氏(たいらし/へいし)の流れをくむ武家で、戸沢氏初代の衡盛(ひでもり/生没年不詳)の父は、平家の大将、平将門(まさかど903年?~940年)の従兄弟(いとこ)という血筋でした。
しかし父通正(みちまさ/生没不詳)が将門に殺されてしまい、衡盛は父の敵である平家撲滅のために源頼朝(みなもとのよりとも/1147~1199)に協力します。そのご褒美に滴石戸沢の領地を与えられ、戸沢氏を名乗ったのです。
戸沢氏は、しばらくの間門屋城を拠点として仙北の地を支配していました。1423年になって第13代当主の家盛(いえもり/生没不詳)が、それまで地元の小さな豪族が支配していた角館城(古城山城跡/古城山公園/仙北市角館町古城山)に移り、戦国時代を過ごします。
戸沢氏最初の居城「門屋城」や守りの拠点「古堀田城」は戦国時代に破壊

門屋城は、安貞2年(1228)に戸沢兼盛によって築かれたとされています。その後200年ほどの間、戸沢氏の本城として機能していました。
戸沢氏が角館城に拠点を移した後は戸沢氏の家臣が城を守っていましたが、戦国時代後期に破却されました。
また古堀田城(こぼたじょう)城は、戸沢氏の北方防備における重要拠点とされていた城郭で、戸沢氏に近い親族や家臣が城代を務めていましたが、こちらも門屋城とともに戦国時代後期に破却されました。
門屋城跡・古堀田城跡 Information
- 施設名称:門屋城跡
- 文化財指定:秋田県指定史跡
- 所在地:秋田県仙北市西木町小山田沢口212
- 施設名称:古堀田城跡
- 文化財指定:秋田県指定史跡
- 所在地:仙北市西木町上荒井字古堀田
- 問い合わせ先:仙北市観光文化スポーツ部文化財保護室
- 電話番号:0187-43-3384
- アクセス:
- 公共交通機関/秋田新幹線・JR田沢湖線角館駅乗り換え秋田内陸縦貫鉄道で約10分、西明寺駅下車徒歩約25分
- 車/秋田自動車道協和ICから国道46号経由で約45分、または大曲ICから約50分
Google Map(門屋城跡)
Google Map(古堀田城跡)
常に勝者側に味方し、負けを知らなかった戸沢氏

家盛が角館に入ってから戸沢氏は徐々に勢力を広げます。
角館に移った当初は足利氏(あしかがし)が君臨した室町幕府の時代(1336年~1573年)でしたが、程なく幕府内の跡目争いから大名間の権力争いへと発展した応仁の乱(1467年~1477年)が勃発、戦国時代といわれる群雄割拠の時代に突入しました。この時代を戸沢氏は足利氏、織田氏の家臣として働き、1590年に秀吉が北条氏の残党を討つため小田原派兵した小田原攻めに参戦し、そして戦況が変化すると、1600年には関ヶ原の戦いでは徳川側につくなど、常に勝者側に味方したのです。
関ヶ原の戦いで戦果を上げた21代当主政盛(まさもり/1585年~1648年)は、1602年にその功績により徳川家康から外様(とざま)の大名から、より幕府に近い譜代大名(ふだいだいみょう)に格上げされ、常陸国松岡藩(茨城県高萩市)の初代藩主に登用されたのです。そして、1622年により大きな新庄藩(山形県)を任されることになり、戸沢氏は明治維新まで新庄藩6万石の藩主として勤め上げました。
他のささら踊りとは一線を画す、戸沢氏が残した「戸沢ささら」

<ささら踊り>はその原型と考えられている<獅子踊り>とともに、秋田県に伝承される民俗芸能です。<ささら踊り><獅子踊り>とも大きな特徴は“三匹獅子”、つまり獅子のお面をかぶった3人の踊り手による踊りです。起源は、そのほとんどが久保田藩主となった佐竹氏が、それまでの支配地域常陸国から秋田へ移動したとき、寂しい思いをしているお殿様に和んでもらおうと、家臣が殿様の前で踊ったものが民衆に間に広がったものといわれています。
しかし、県中央から北のエリアに数多く残る<ささら踊り><獅子踊り>の中で、仙北市エリアに伝わる<ささら踊り>にだけ、他の地域のものと明らかに違う踊りがあるのです。
仙北の「ささら踊り」には、佐竹氏伝承の「ささら踊り」にない楽器が使われる

仙北市に伝承される<ささら踊り>は、「戸沢ささら」(西木町上桧木内)「小山田ささら」(西木町小山田)、「白岩ささら」(角館町白岩)、「広久内(ひろくない)ささら」(角館町広久内)、「堂ノ口ささら」(角館町白岩堂野口)、「梅沢ささら」(田沢湖町梅沢)などあるのですが、いずれも三匹獅子舞であることは変わりません。
他地域の<ささら踊り>と明らかに違うのは、ささらを披露する場所(神社など)に向かう獅子たちの行列や、踊りの中で[びんざさら]と呼ばれる平安時代から神楽などで使われていた楽器を使っていることです。
この[びんざさら]は、不思議なことに他地域の<ささら踊り>や<獅子踊り>では全く使われていないのです。さらに、元になる佐竹家臣が踊っていた常陸国に伝承されている<ささら踊り>にも[びんざさら]が使われていたという形跡がありません。
佐竹氏が秋田に来る前から仙北には独自の踊りがあった

戸沢氏の居城のあった上桧木内(西木町小山田)に伝わる「小山田(こやまだ)ささら」には、このような逸話が残されています
『家盛は角館に移ることを決意します。家臣領民は驚きますが、家盛の決心の固さに皆納得します。(中略)。家盛は、家臣団に伝わる獅子舞を、領民に伝授することにしました。 出発の日、家盛の前で領民はその舞を披露します』
引用元:仙北市公式ホームページ「桜が見える丘で ~戸沢氏800年の物語~」
というもので、この舞が現代に伝わる「小山田ささら」と同一かどうかは分かりませんが、佐竹氏が秋田県に「ささら踊り」を伝える前に、仙北には何らかの舞があったことを物語っています。
戸沢氏出身の岩手県には「びんざさら」を用いた踊りがある
一方で、戸沢氏が雫石で暮らしていた頃には、南部地域に“念仏剣舞(ねんぶつけんばい)”という独特の舞がありました。
その発祥は平安時代後期にあった前九年の役頃ともいわれていて、戦いで命を落とした兵士たちの亡霊を成仏させるために舞われたもののようです。この<念仏剣舞>の一部では[びんざさら]が使われているのです。

ただ、[ささら]を持った踊り手の舞い方が異なるとか、戸沢氏の出身地雫石には念仏剣舞が伝承されていない、などの違いも多く、仙北の<ささら踊り>に何故[ささら]が使われているかは研究者の間でも意見は分かれているようです。
戸沢氏ゆかりのささら踊り Information
- 「戸沢ささら」(西木町上桧木内/秋田県指定無形民俗文化財)
- 「小山田ささら」(西木町小山田/仙北市指定無形民俗文化財)
- 「白岩ささら」(角館町白岩/秋田県指定無形民俗文化財/)
- 「広久内(ひろくない)ささら」(角館町広久内/仙北市指定無形民俗文化財)
- 「堂ノ口ささら」(角館町白岩堂野口/仙北市指定無形民俗文化財)
- 「梅沢ささら」(田沢湖町梅沢/仙北市指定無形民俗文化財)
- 開催時期・開催場所・等は要問い合わせ
- 問い合わせ先:仙北市観光文化スポーツ部文化財保護室
- 電話番号:0187-43-3384
- 角館の歴史や伝統行事は【仙北市の見所②】でご紹介しています。
- 秋田県の「ささら踊り」に関しては秋田のささら踊りで詳しくご紹介しています