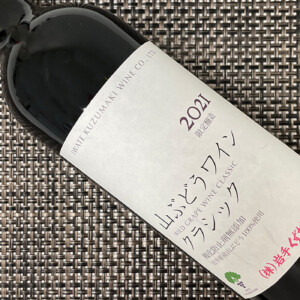にしんの切り込み?誕生の背景とおすすめの食べ方を紹介【青森県】
目次
北海道や東北では、発酵文化が今もなお色濃く残っています。その中でも北海道と青森で食べられる「にしんの切り込み」は、ご飯のお供やお酒のつまみとして長年愛されてきた伝統的な保存食です。この記事では、にしんの切り込みが生まれた背景や地域性、そしておすすめの食べ方についてご紹介します。
にしんの切り込みとは?

「にしんの切り込み」は、北海道や東北地方で古くから作られてきた発酵食品のひとつです。新鮮なニシンを細かく刻み、塩、米麹、生姜などと一緒に漬け込み、一定期間寝かせて発酵させることで完成します。魚の臭みが抑えられ、麹のほのかな甘みと塩味が混ざり合い、深い旨味が感じられるのが特徴です。
この「にしんの切り込み」は、かつて家庭で冬場に仕込まれるのが一般的でした。雪国の冷たい環境は発酵に適しており、無理なく時間をかけて味を引き出すことができたのです。現在では、各地のスーパーや物産展などでパック詰めの商品も販売されており、地元の人々だけでなく観光客からも注目を集めています。
にしんの切り込みが生まれた背景を解説!

北海道や青森ではニシン漁が盛ん
にしんの切り込みが広まった背景には、北海道や青森で盛んだったニシン漁があります。明治から昭和初期にかけて、特に北海道では「鰊場(にしんば)」と呼ばれる漁場がにぎわいを見せ、ニシンは大量に水揚げされていました。青森でも津軽海峡沿岸を中心に、ニシン漁は地域の暮らしを支える重要な産業のひとつでした。
食料としてだけでなく、肥料(鰊粕)や油(にしん油)としても利用されるなど、ニシンは多用途に活用される資源でしたが、漁期には消費しきれないほどの量が一気に揚がることも……そうなると、どのように処理するかが問題になってくるのです。
ニシンは保存が難しい

ニシンは脂がのっていて美味しい反面、非常に傷みやすい魚です。特に当時は冷蔵設備が整っておらず、水揚げされたその日のうちに加工しなければすぐに鮮度が落ちてしまいました。そのため、塩漬けや乾燥といった保存法が発達する中で、塩と麹による「切り込み」という製法が生まれたのです。
切り込みにすることで旨味が凝縮されるだけでなく、長期間保存が可能となり、冬場の貴重なタンパク源として家庭の食卓に定着していきました。魚の保存と美味しさの両立を実現したこの知恵は、今でも多くの家庭に受け継がれています。
北海道や東北では発酵食品が多い
にしんの切り込みが愛されるもうひとつの理由として、地域に根付いた発酵文化が挙げられます。北海道や東北地方は、味噌や漬物、塩辛など、発酵を活かした食品が非常に多く存在します。これは、雪国だからこそ発酵がゆっくりと進行し、時間をかけて旨味を引き出せる環境的な条件があったからです。また、厳しい冬を乗り越えるため、食材を保存する知恵や方法が豊富だったことも関係しています。
家庭での食材保存に発酵を取り入れることは自然な流れであり、切り込みもその一環として発展しました。冬の間の保存食として重宝され、季節の変わり目になると各家庭で仕込む習慣が根付いていたのです。
にしんの切り込みのおすすめの食べ方

王道アレンジ・お茶漬け
炊きたての白ご飯ににしんの切り込みをのせ、熱いお茶や出汁を注ぐだけ。簡単で手軽に食べられますが、その美味しさは格別です。発酵の旨味が出汁と合わさって、さらっと食べられるのに満足感もあり、飲んだあとの〆にもぴったり。お好みで刻みねぎやのり、わさびを加えても風味が引き立ちます。
大根おろしと和えて塩辛風
さっぱりと楽しみたいときには、大根おろしとの組み合わせがおすすめです。切り込みは塩辛と表記されることもあり、塩辛と大根おろしの相性は抜群!切り込みの塩気と大根の辛みがよく合い、魚の脂を程よく中和してくれます。
大根おろしを添えるだけでも美味しいですが、和えてしまっても美味しい!焼酎や日本酒と一緒に味わえば、より一層素材の味を楽しめます。
野菜と煮て三平汁風

三平汁は塩漬けにした魚と根菜類を一緒に煮込んだ北海道の郷土料理。にしんの切り込みを使えば気軽に三平汁を食べられます。じゃがいもや大根、にんじんなどの根菜と一緒に煮込むことで、切り込みの旨味が汁に溶け出し、出汁いらずで深い味わいの一椀に。寒い季節にぴったりのあたたかい汁物として、家族で楽しんでみてはいかがでしょうか。
まとめ
にしんの切り込みは、寒さの厳しい北海道や東北地方で生まれた、知恵と工夫の詰まった伝統料理です。ニシン漁の盛んな土地で、保存の工夫として発展したこの食文化は、時代を超えて今も多くの家庭で愛されています。
そのまま食べても良し、お茶漬けにしても、三平汁にしても良し。さまざまな形で楽しめる切り込みは、まさに発酵食品の魅力を凝縮した一品です。北海道や青森以外ではほとんどお目にかかれないので、見つけたらラッキー!
もし見かける機会があれば、ぜひ一度味わってみてください。