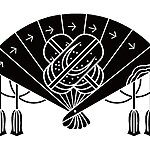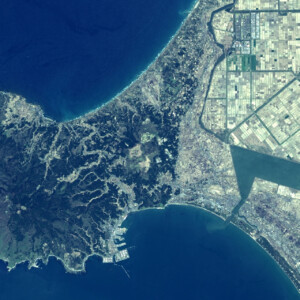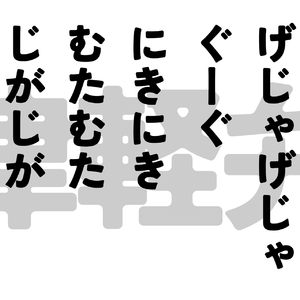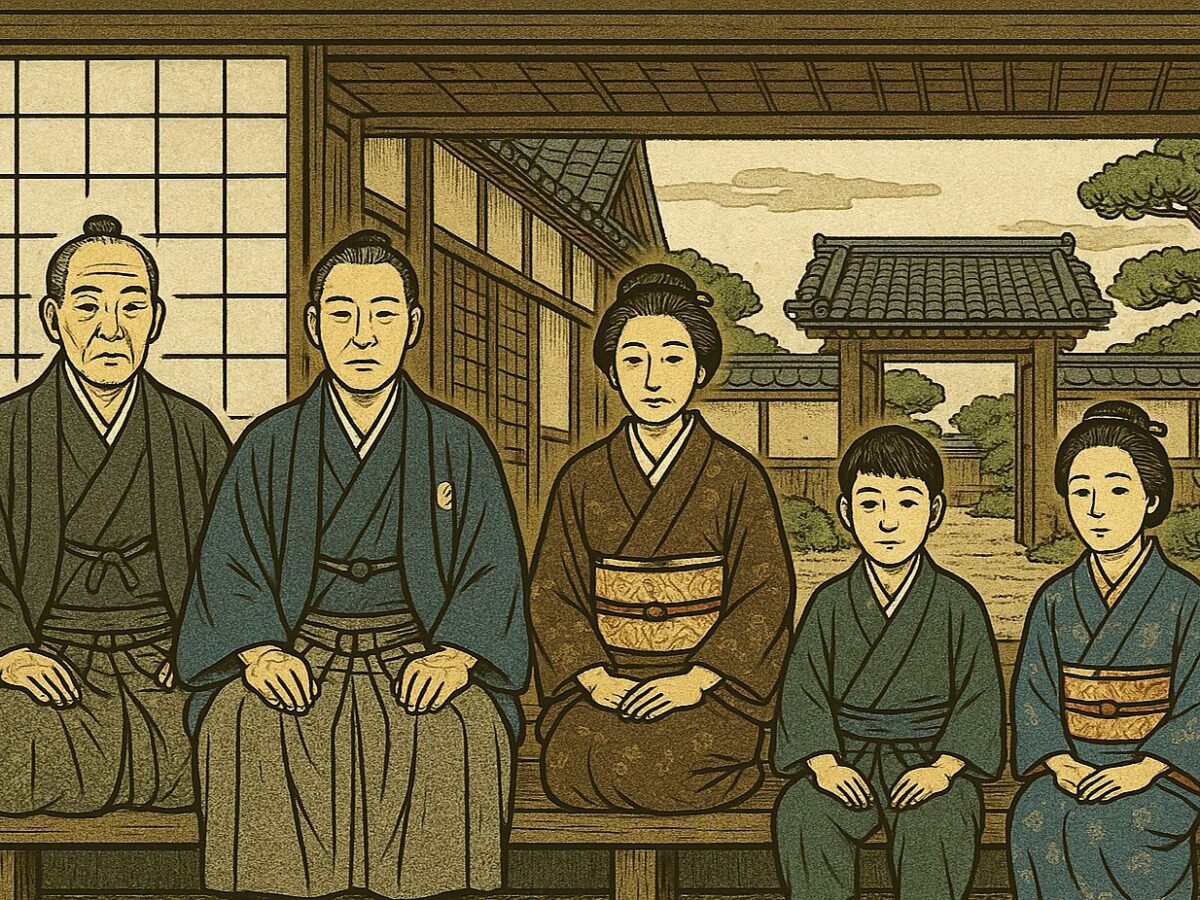
秋田県の名門・名家にルーツを持つ苗字30選
目次
- 1 秋田県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
- 1.1 青柳(あおやぎ)
- 1.2 赤尾津(あかおつ)
- 1.3 麻木(あさぎ)
- 1.4 浅利(あさり)
- 1.5 安東(あんどう)
- 1.6 生駒(いこま)
- 1.7 一部(いちぶ)
- 1.8 岩城(いわき)
- 1.9 岩屋(いわや)
- 1.10 打越(うちこし)
- 1.11 小田野(おだの)
- 1.12 小野寺(おのでら)
- 1.13 潟保(かたのほ)
- 1.14 河原田(かわらだ)
- 1.15 沓沢(くつざわ)
- 1.16 子吉(こよし)
- 1.17 佐竹(さたけ)
- 1.18 下村(しもむら)
- 1.19 芹田(せりた)
- 1.20 滝沢(たきざわ)
- 1.21 須田(すだ)
- 1.22 玉米(とうまい)
- 1.23 戸沢(とざわ)
- 1.24 中谷(なかや)
- 1.25 仁賀保(にかほ)
- 1.26 根井(ねのい)
- 1.27 本堂(ほんどう)
- 1.28 真崎(まさき)
- 1.29 矢島(やじま)
- 1.30 六郷(ろくごう)
- 2 東北各県の名門・名家にルーツを持つ苗字シリーズ
日本全国どこの土地でも、いわゆる「地元の名士」と囁かれるような名門・名家が存在します。「うちはごく普通の一般家庭です」という方でも、よくよく先祖を辿れば実は由緒ある武家の家柄だった…というのも珍しくありません。
今回の記事では、秋田県内各地の名門・名家と呼ばれる苗字について調べてみました。「同級生にそんな苗字の人がいたなぁ…」なんてことがあったら実はその友達は良家のお家柄かもしれませんね…。
秋田県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
秋田県は武家にルーツを持つ名家が多い印象。また久保田藩(秋田藩)に移封された佐竹氏の関係で常陸国(現在の茨城県周辺)から移り住んだ旧家も多いようです。
青柳(あおやぎ)
会津芦名氏家臣、芦名氏断絶後は佐竹氏の臣下として出羽移封に帯同した仙北郡角館(仙北市角館町)の旧家。佐竹北家に仕え、明治維新後は金融業で成功し、角館町長も輩出した家柄。屋敷は角館武家屋敷を成す一軒として保存・公開されている。
リンク:角館歴史村・青柳家 公式HP
赤尾津(あかおつ)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。出羽国由利郡赤尾津(由利本荘市)の国人衆。南北朝時代に由利郡に入部したといわれる。
麻木(あさぎ)
土崎湊(秋田市)の豪商。呉服・太物商を皮切りに、酒造業、質屋、金貸業と手を広げ短期間で財を成した。秋田藩の御用商人も務めていた。
浅利(あさり)
出羽国比内郡の戦国大名。甲斐浅利氏の一族で、鎌倉時代に比内郡の地頭となり下向、領主となって発展する。独鈷城(大館市)を居城としていた。
安東(あんどう)
陸奥・出羽の戦国大名で、阿部貞任の子孫と伝わるが真偽は不明。もとは津軽の豪族だったが海路を巧みに使い現在の秋田、青森、北海道函館周辺を支配し、海賊のような一面も。一時檜山安東氏、湊安東氏と別れるが、安藤愛季の時代に再度両家が統合され土崎湊城(秋田市)を居城に秋田氏へと改称する。
生駒(いこま)
矢島藩(現在の秋田県由利本荘市矢島町)の藩主。幕末には新政府軍に与し、維新後に男爵となる。もとは讃岐国高松藩(現在の香川県)の藩主の家柄。
一部(いちぶ)
出羽国秋田郡の国衆。太平城(秋田市)城主の一族。
岩城(いわき)
亀田藩(現在の秋田県由利本荘市岩城亀田)藩主の家柄。陸奥国磐城郡の戦国大名岩城氏の一族。明治維新後は子爵となる。
岩屋(いわや)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡岩谷(現・由利本荘市岩谷町)付近を拠点とし、関ヶ原合戦後は最上氏に仕える。
打越(うちこし)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡打越(現・由利本荘市内越)付近を中心に勢力を持っていた。
小田野(おだの)
秋田藩の重臣で常盤佐竹家の庶流。8代藩主佐竹義敦に仕えた小田野直武は、杉田玄白の『解体新書』のさし絵を描いたことや秋田蘭画の祖としても有名。
小野寺(おのでら)
出羽国仙北地方の戦国大名。下野小野寺氏が奥州合戦の功績で出羽国雄勝郡の地頭頭に任命され、鎌倉時代に稲庭うどんで有名な出羽国雄勝郡稲庭(湯沢市)に入部したのが始まり。戦国時代には横手城(横手市)を拠点に仙北地方一帯を支配した。
潟保(かたのほ)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡潟保(現・由利本荘市西目町潟保)付近を中心に勢力をもった一族で、関ヶ原合戦では最上氏に属し、後に酒井氏に仕え鶴岡藩士となる。
河原田(かわらだ)
仙北郡角館(仙北市)の旧家。芦名氏の会津時代からの譜代の家柄で、後に佐竹北家に仕える。漢学者、秋田県議、角館町長など多数の人材を輩出した家柄。屋敷は仙北市指定史跡として保存・公開されている。
沓沢(くつざわ)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡沓沢(現・由利本荘市矢島町立石)付近を中心に勢力を持った一族で、矢島氏、仁賀保氏と同様に先祖は大井氏と称した。
子吉(こよし)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡子吉(現・由利本荘市埋田)付近を中心に勢力を持った一族。矢島氏、仁賀保氏と同様に先祖は大井氏と称し、関ヶ原合戦後は最上氏に、江戸時代には佐竹氏に仕えた。
佐竹(さたけ)
秋田藩(久保田藩)藩主。もとは常盤国の大大名だったが関ヶ原合戦にて西軍に属したため戦後処理にて出羽久保田(秋田市)に減転封。しかし秋田では「秋田市は佐竹義宣が国替えになった1602年に始まる」といわれるほど重要な藩政の基礎を固めた名家・名族。
下村(しもむら)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡下村(現・由利本荘市東由利蔵)付近を中心に勢力を持った一族。矢島氏、仁賀保氏と同様に先祖は大井氏と称し、関ヶ原合戦後は最上氏に仕え、江戸時代には佐竹氏の陪臣(家臣の家臣)となった。
芹田(せりた)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡芹田(現・にかほ市芹田)付近を中心に勢力を持った一族。関ヶ原合戦後は最上氏に仕えた。
滝沢(たきざわ)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡滝沢(現・由利本荘市前郷字滝沢館)付近を中心に勢力を持った一族。関ヶ原合戦後は最上氏に仕え、最上氏改易後は六郷氏に仕えて本荘藩家老となり幕末を迎える。
須田(すだ)
秋田藩家老。戦国時代は須賀川(福島県須賀川市)二階堂氏の重臣であり、二階堂氏の滅亡後佐竹氏に臣従。佐竹氏の秋田移封に従い出羽横手に転じた。
玉米(とうまい)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡玉米(現・由利本荘市東由利館合)付近を中心に勢力を持った一族。矢島氏、仁賀保氏と同様に先祖は大井氏と称し、関ヶ原合戦後は最上氏に仕え、最上氏改易後は六郷氏に仕えて幕末を迎える。
戸沢(とざわ)
出羽新庄藩主。もとは秋田県の仙北地方の戦国大名で、1622年に新庄に移封される。智勇に優れ「鬼九郎」「夜叉九郎」の異名で恐れられた戸沢盛安(とざわ もりやす)が有名。現在でもそのルーツである秋田県仙北市によくみられる苗字。
中谷(なかや)
久保田城下(秋田市)の豪商。甲斐国の出であることから「甲斐屋」の屋号で質屋を営んでいた。
仁賀保(にかほ)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡矢島(現・由利本荘市矢島町)付近を中心に勢力を持っていた。先祖は大井氏と称し、矢島氏とは近い同族関係。家紋等からは大江広元との関係も指摘されている。
大坂の陣での功績により一万石の仁賀保藩を立てた。現在は秋田を中心に10人程しかいないと思われる希少な苗字。
根井(ねのい)
禰々井とも。戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡直根(現・由利本荘市鳥海町直根)付近を中心に勢力がもち、先祖は木曾義仲の家臣、根井行親と称した。矢島氏に属したが、滅亡後に仁賀保氏に、江戸期以降は遠藤と改名し生駒氏(矢島藩)に仕えた。
本堂(ほんどう)
出羽国仙北郡の国衆。元本堂城(仙北郡美郷町)を本拠とした。現在は青森県や岩手県に比較的多い苗字。
真崎(まさき)
秋田藩家老。佐竹氏の庶流。佐竹氏の秋田移封に帯同し、江戸期以降は秋田藩重臣となる。戊辰戦争では藩を代表し官軍に参加した。
矢島(やじま)
戦国時代に出羽国由利郡の各地に存在した豪族 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)の一つ。由利郡矢島(現・由利本荘市矢島町)付近を中心に勢力を持っていた。先祖は大井氏と称し、仁賀保氏とは近い同族関係。
六郷(ろくごう)
出羽国山本郡六郷(仙北郡美郷町六郷)の国衆。関ヶ原合戦後に常盤国(現在の茨城県石岡市)に国替えされ常陸府中藩(ひたちふちゅうはん)を立藩。その後六郷政乗が2万石に加増され本荘(現在の秋田県由利本荘市)に移ってきて本荘藩を興す。