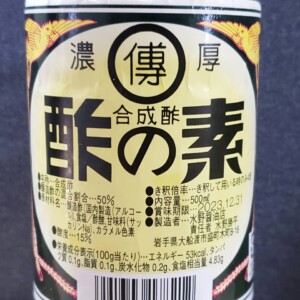青森県の名門・名家にルーツを持つ苗字30選
目次
- 1 青森県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
- 1.1 淡谷(あわや)
- 1.2 一町田(いっちょうだ)
- 1.3 大浦(おおうら)
- 1.4 奥瀬(おくせ)
- 1.5 櫛引(くしびき)
- 1.6 七戸(しちのへ)
- 1.7 四戸(しのへ)
- 1.8 杉山(すぎやま)
- 1.9 清藤(せいとう)
- 1.10 大光寺(だいこうじ)
- 1.11 大道寺(だいどうじ)
- 1.12 武田(たけだ)
- 1.13 津軽(つがる)
- 1.14 津島(つしま)
- 1.15 堤(つつみ)
- 1.16 坪田(つぼた)
- 1.17 剣地(つるぎじ)
- 1.18 戸沼(とぬま)
- 1.19 飛島(とびしま)
- 1.20 浪岡(なみおか)
- 1.21 鳴海(なるみ)
- 1.22 南部(なんぶ)
- 1.23 野村(のむら)
- 1.24 野呂(のろ)
- 1.25 平山(ひらやま)
- 1.26 戸来(へらい)
- 1.27 米田(まいた)
- 1.28 松橋(まつはし)
- 1.29 村井(むらい)
- 1.30 盛田(もりた)
- 2 東北各県の名門・名家にルーツを持つ苗字シリーズ
日本全国どこの土地でも、いわゆる「地元の名士」と囁かれるような名門・名家が存在します。「うちはごく普通の一般家庭です」という方でも、よくよく先祖を辿れば実は由緒ある武家の家柄だった…というのも珍しくありません。
今回の記事では、青森県内各地の名門・名家と呼ばれる苗字について調べてみました。「同級生にそんな苗字の人がいたなぁ…」なんてことがあったら実はその友達は良家のお家柄かもしれませんね…。
青森県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
青森県の名家は、広大な版図を築き、一族を各所に配した南部氏にルーツを持つ武家が多く、全く違う名字でも元を辿っていくと南部氏にいきつく…といった印象が強いです。
淡谷(あわや)
青森湊越前町(現:青森市)の豪商。北前船の水主だった初代が竜飛沖で遭難、救助後に青森で「阿波屋」と号した魚屋を始める。その後「大世」と号した呉服商に商売替えをして、明治維新後に青森を代表する豪商に成長した。
一町田(いっちょうだ)
陸奥大浦氏の庶流。南部久慈氏の一族の南部光信(後の大浦光信)の弟が祖といわれ、陸奥国津軽郡一町田村(現:弘前市一町田)にあった一町田館を拠点としていた士族とされている。代々津軽氏に仕え、江戸時代に津軽藩士となり西舘氏と改称した。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在でも弘前市には「一町田」を名乗る人が約60人程存在する。
大浦(おおうら)
南部久慈氏の一族の南部光信(後の大浦光信)が安東氏の抑えとして西津軽郡鰺ヶ沢町にあった種里城に入ったのが始まり。その後1502年に現在の青森県弘前市賀田・五代に大浦城を築城し拠点としたことから、以降大浦氏を名乗る。子孫である大浦為信の時代に南部氏から独立し、その後は津軽氏となる。
奥瀬(おくせ)
陸奥国北部の国衆。南部氏の始祖である南部光行に従って鎌倉時代頃に移り住んだ小笠原氏の一族といわれている。現在の青森県十和田市奥瀬にあった奥瀬城を拠点とし南部氏に従ったことから奥瀬氏を名乗る。戦国時代には油川城(現:青森市西田沢)を拠点として南部氏の代官を務めた。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に1,100人程の奥瀬さんが存在し、うち500人以上が青森県内に集中している。
櫛引(くしびき)
陸奥国三戸郡の国衆。南部氏の一族、四戸氏の庶流とされ、名前からもわかる通り櫛引城(現:青森県八戸市櫛引館神)を拠点とし、櫛引八幡宮の神事にも関わっていた。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に3,000人程の櫛引さんが存在し、うちおよそ1,200人が青森県、900人が北海道に集中している。
七戸(しちのへ)
津軽の国衆で八戸南部氏の庶流。南部氏初代・南部光行の三男の朝清または四男・朝清が最初に七戸を名乗ったとする説と根城南部氏八代の南部政光が晩年、家督を譲って七戸城に隠居し七戸氏の祖となったとする説など、諸説あり定かではない。
四戸(しのへ)
南部氏の祖・南部光行の五男の宗清が、二戸郡四戸の郷を賜わり四戸氏を称したのが始まりとされる。四戸氏の分流には武田氏、金田一氏、櫛引氏、中野氏、糠塚氏などの各氏がある。
杉山(すぎやま)
安土桃山時代に豊臣政権の中枢を担った五奉行の一人石田三成(いしだ みつなり)の末裔といわれる津軽藩の家臣。豊臣秀頼に小姓として仕えていた光成の次男である石田 重成(いしだ しげなり)が関ヶ原合戦の敗北を受けて津軽へと落ち延び「杉山」と姓を変えて、深味村(現:北津軽郡板柳町)に身を落ち着けて津軽藩の庇護を受けたといわれる。
重成の長男の吉成は弘前藩2代藩主・津軽信枚(つがる のぶひら)の娘を妻として家老職につき、以後代々杉山家は弘前藩重臣として存続した。
石田三成の縁からか、宗徳寺(青森県弘前市)にある重成以下杉山家の代々の墓には豊臣の姓が刻まれている。
清藤(せいとう)
津軽郡猿賀村(現:平川市猿賀石林)の旧家。24代目である清藤 盛義(せいとう もりよし)が造った庭園「盛美園」は明治時代三名園の一つに数えられ、国指定名勝として今も親しまれている。
リンク:国指定名勝「盛美園」
大光寺(だいこうじ)
陸奥国平賀郡(現在の平川市・大鰐町周辺)の国衆。系図は不明な部分が多いが、南部氏第20代当主南部信時の四男、田子弾正左衛門光康を祖とするといわれ、「糠部五郡小史」の記述によると、光康の孫の景行が大光寺(現:平川市)を拠点とし大光寺氏を称したとされている。
大道寺(だいどうじ)
津軽藩の家老。山城国綴喜郡大道寺(現:京都府綴喜郡宇治田原町)発祥であることから大道寺を名乗る。北条早雲以来の北条氏の重臣で、その血筋である大道寺直英が北条氏滅亡後、尾張を経て津軽藩士へと転じた。
戦国時代の北条氏の重臣で、上野松井田城代として豊臣秀吉の小田原征伐に対抗した大道寺 政繁(だいどうじ まさしげ)が有名。
武田(たけだ)
津軽郡金木(現:五所川原市金木町)の豪商。弘前城下で金木屋呉服店を開業し弘前藩の御用商人となり、明治にかけて津軽を代表する豪商へと成長した。
津軽(つがる)
南部久慈氏の一族の南部光信が安東氏の抑えとして西津軽郡鰺ヶ沢町にあった種里城に入ったのが始まり。その子孫である大浦為信が主家である南部氏にいわゆる「下克上」を起こし、南部家重臣である石川高信の居城だった石川城(現:弘前市石川大仏下)を攻め落とし南部氏より独立する。
後に豊臣秀吉から津軽の所領を認知され、この頃から姓を大浦から津軽に改めている。関ヶ原合戦後に弘前藩を立藩し、為信は初代藩主となる。
津島(つしま)
津軽郡金木(現:五所川原市金木町)の豪農。商売上手な血筋で、古着屋、豆腐屋、金融業などで成功して土地を集積し大地主となる。政治家、俳優などの名士を輩出し、その中でも有名なのは文豪の太宰治(本名:津島 修治)。
金木町にある津島家の豪邸は戦後に売却され、一時は旅館「斜陽館」となり、現在は太宰治記念館「斜陽館」として保存・公開されている。
堤(つつみ)
南部氏第20代当主南部信時の四男、田子弾正左衛門光康が田子館(現:三戸郡田子町)から堤ヶ浦城(現:青森市松原周辺)に入部し堤氏を称する。さらに南方に横内城を築城(現:青森市横内)し、堤ヶ浦城を平時の政庁、横内城を有事の要害として周辺に勢力を持っていたといわれる。
坪田(つぼた)
津軽郡の豪農。近江国から津軽郡王余魚沢(現:青森市浪岡王余魚沢)に移り峠の茶屋を営んだのが始まりといわれる。
剣地(つるぎじ)
北郡脇野沢(現:むつ市)の豪商。能登国鳳至郡剣地村(現:石川県輪島市門前剣地)の出であることから剣地を名乗る。廻船問屋を営み、主に青森ヒバの取引で財を成した。
戸沼(とぬま)
津軽郡鰺ヶ沢湊(現:鰺ヶ沢町)の豪商。「山〆二」と号し、「塩屋」の名で船主・船問屋に町名主も務めていた。
高沼家と七戸家の縁組を経て、両家から「沼」「戸」と一字づつ拝借し「戸沼」を名乗ったといわれている。
飛島(とびしま)
津軽郡五所川原(現:五所川原市)の豪商。出羽国飛島(山形県)の出であることから飛島を名乗る。新田開発で財を成し、四代目は郷氏に取り立てられ帯刀を許された。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に700人程の飛島さんが存在し、うち約300人以上が青森県と北海道に集中している。
浪岡(なみおか)
津軽の戦国大名。村上源氏の公家北畠家の庶流。陸奥国多賀城に下向した北畠顕家(きたばたけ あきいえ)またはその弟の顕信(あきのぶ)の流れを汲むといわれる。
浪岡における北畠氏の宗家は、「浪岡御所」「大御所」あるいは「北の御所」とあがめられ、天正年間まで力を持ち続けた。
鳴海(なるみ)
津軽郡浅瀬石(現:黒石市)の豪農。もともとは武家だったが、主家の滅亡後に帰農したといわれる。江戸時代には藩の開発取締方として杉の植林事業なども行っていた。
「久〇」「菊乃井」「稲村屋文四郎」等の銘酒で知られる黒石市の鳴海醸造店は分家筋にあたる。
リンク:鳴海醸造店
南部(なんぶ)
現在の青森県・岩手県に勢力をもった戦国大名。
南部氏は甲斐源氏の流れをくみ、鎌倉時代に今の山梨県南部町から陸奥国に入部したといわれる。糠部群を中心に四門九戸の制をしいて各地に一族を配置した。中でも嫡流の三戸南部氏と八戸南部氏が大きな勢力を持っていた。
その領土を最も広げたのは三戸南部氏24代当主の晴政(はるまさ)で、青森県の大部分と岩手県の北半分を合わせ「三日月の丸くなるまで南部領」と謳われたほどだった。
野村(のむら)
北郡野辺地(現:野辺地町)の豪商。代々「治三郎」と称して廻船問屋や酒造業を営む。南部藩の御用商人も務めて、維新後は青森を代表する大地主となる。貴族院議員、衆議院議員などの人材も輩出している。
野呂(のろ)
津軽郡木造(現:木造町)の豪農。新田開発に力を注ぎ、木造周辺66ヵ村もの開発を行ったといわれている。
平山(ひらやま)
津軽郡湊村(現:五所川原市)の豪農・豪商。湊村開村以来肝入役を務め、代々藩の広田組代官所の手代、堰奉行、堤奉行、郷士なども務める。10代目為之助は衆議院議員となり、その後陸奥銀行頭取、津軽鉄道の初代社長など、要職を務めた。
同家の住宅は国の重要文化財に指定され、保存・公開されている。
戸来(へらい)
陸奥国三戸郡の国衆。長亨年間に木村秀勝という人物の長男政秀が戸来郷(現:三戸郡新郷村戸来)を領して戸来氏を称したといわれている。
この戸来(へらい)に関しては現在、新郷村の「キリストの墓」とあわせて、戸来=ヘブライとするなど都市伝説的な話題も飛び交っている。
米田(まいた)
陸奥国三戸郡の国衆。三戸郡米田(現:十和田市米田)に由来する。江戸時代に南部藩士となる。
松橋(まつはし)
三戸郡新井田村(現:八戸市新井田)の豪商。代々「孫助」を称し、八戸藩の御用商人を務めた。酒造業や廻船業を営んでいた。
村井(むらい)
八戸城下(現:八戸市)の豪商。近江国の大塚屋村井伊兵衛が八戸城下三日町に出店を構えたのが始まり。藩に多額の献金を行い「特権商人」の地位を獲得。同城下の「近江屋」「美濃屋」とともに「八戸三店」といわれていた。
盛田(もりた)
北郡七戸(現:七戸町)の豪商。石田三成の末裔といわれる。元禄年間に近江の初代石田喜平治が「大塚屋」を号して七戸で創業したのが始まりといわれる。酒造業や呉服店など、手広く商売を行い七戸一の豪商となる。1756年に名字帯刀を許された折に石田家の「田」と盛岡藩の「盛」の字を合わせて盛田家を名乗る。
1800年代に「盛田牧場」を開設し、同牧場産の競走馬は日本ダービーや天皇賞を制したこともあった。しかし時代とともに競走馬生産の中心地が北海道へ移っていくなかで衰退していき2006年に閉場した。
旧南部領の特徴である「曲屋」を含む各施設が良好な状態で残されており、旧場内8つの物件が登録有形文化財となっている。
リンク:文化遺産オンライン – 盛田牧場一号廏舎(南部曲屋育成廏舎)