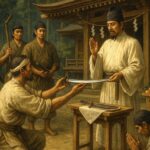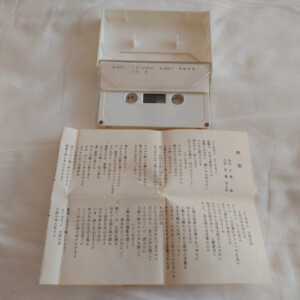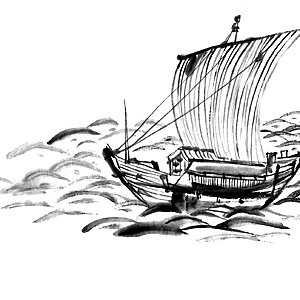岩手県の名門・名家にルーツを持つ苗字30選
目次
- 1 岩手県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
- 1.1 阿蘇沼(あそぬま)
- 1.2 姉帯(あねたい)
- 1.3 一戸(いちのへ)
- 1.4 岩淵(いわぶち)
- 1.5 江刺(えさし)
- 1.6 及川(おいかわ)
- 1.7 太田(おおた)
- 1.8 大槻(おおつき)
- 1.9 葛西(かさい)
- 1.10 柏山(かしやま)
- 1.11 金子(かねこ)
- 1.12 亀卦川(きけがわ)
- 1.13 久慈(くじ)
- 1.14 葛巻(くずまき)
- 1.15 九戸(くのへ)
- 1.16 小梨(こなし)
- 1.17 斯波(しば)
- 1.18 鳥畑(とりはた)
- 1.19 中村(なかむら)
- 1.20 奈良坂(ならさか)
- 1.21 楢山(ならやま)
- 1.22 南部(なんぶ)
- 1.23 浜田(はまだ)
- 1.24 稗貫(ひえぬき)
- 1.25 前川(まえかわ)
- 1.26 村井(むらい)
- 1.27 村上(むらかみ)
- 1.28 八重畑(やえはた)
- 1.29 留守(るす)
- 1.30 和賀(わが)
- 2 東北各県の名門・名家にルーツを持つ苗字シリーズ
日本全国どこの土地でも、いわゆる「地元の名士」と囁かれるような名門・名家が存在します。「うちはごく普通の一般家庭です」という方でも、よくよく先祖を辿れば実は由緒ある武家の家柄だった…というのも珍しくありません。
今回の記事では、岩手県内各地の名門・名家と呼ばれる苗字について調べてみました。「同級生にそんな苗字の人がいたなぁ…」なんてことがあったら実はその友達は良家のお家柄かもしれませんね…。
岩手県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
岩手県の名家は、県北は南部氏に連なる家柄、県南は伊達氏と葛西氏のいずれかに属する国衆の家柄が多い印象です。
阿蘇沼(あそぬま)
藤原秀郷の後裔である藤姓足利氏の一族。足利有綱の四男阿曽沼四郎広綱を祖とし、下野国安蘇郡阿曽沼(現:栃木県佐野市浅沼町)を領して阿蘇沼または阿曽沼と称したのが始まりとされる。
阿曽沼四郎広綱は1189年の奥州合戦にて功をあげ、陸奥国閉伊郡遠野保(遠野十二郷)地頭となるが実際には現地に赴かず代官統治を行う。その後広綱の次男親綱が護摩堂山(現:遠野市松崎町)に横田城を築き、以降その子孫は遠野に土着した。
姉帯(あねたい)
陸奥国糠部郡(現:青森県東部~岩手県北部)の国衆。現在の岩手県二戸郡一戸町姉帯字館にあった姉帯城に拠って九戸氏に属した。
1591年の「九戸政実の乱」においても九戸氏側として豊臣軍と交戦。姉帯城の落城とともに自刃した。
一戸(いちのへ)
南部家初代光行の長男、行朝が庶子(正室以外の子供)だったため南部家の家督を継げず、一戸郷(現:二戸郡一戸町)に拠ったのが始まり。二代目義実の時代に一戸城を築いて本拠として糠部郡の南門を総攬した南部支族の家柄。
上記の姉帯氏と同様に「九戸政実の乱」において九戸氏側に与したことで南部信直に攻められ一戸城は落城。
この流れで一戸氏の嫡流は断絶したとされるが一戸氏には荒木田、平舘、寄木、堀切、千徳氏、八木沢、津軽石、江繋、根井沢、江繋、野田、閉伊口、種市、長牛、谷内、中村、浅瀬石、十二屋などの多くの分流が存在し、その一部は明治以後に本姓の一戸氏に復したといわれている。
岩淵(いわぶち)
下総国猿島郡岩淵(現:茨城県猿島郡)をルーツとする陸奥国磐井郡の国衆。前九年の役において「黄海の戦い」で知られる要衝、黄海(現:一関市藤沢町黄海)を鎌倉時代以後に領した豪族。
以降磐井郡一帯に広がり繁栄するが、1590年に行われた豊臣秀吉の奥州仕置によって一族は離散してしまったといわれる。
江刺(えさし)
陸奥国江刺郡の国衆。葛西氏の庶流とされ、代々岩谷堂城(現:奥州市江刺岩谷堂舘下)に拠り、江刺郡を支配した。1590年に行われた豊臣秀吉の奥州仕置によって所領を没収され没落し、江戸時代以降に南部藩士となる。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に1,400人程の江刺さんが存在し、約30%にあたる600人程が宮城県に分布している。
及川(おいかわ)
陸奥国磐井郡(現:一関市・西磐井郡平泉町・奥州市の一部)の国衆。葛西氏に属して磐井郡一帯を治める及川氏は磐井郡・興田保を拠点としていたことから柏木城主の及川頼家を頭領として「沖田及川党」と呼ばれていた。
1559年に千葉三郎信近と争い所領没収の処分を受けるが、これを不服として「柏木城事件」が発生。大原氏により柏木城は鎮圧され及川党は討伐された。
太田(おおた)
磐井郡上奥玉村(現:一関市千厩町)の奥玉鋳物師。天明鋳物師の系譜とされ、北関東から信越地方にまで販路を持っていた。明治以降に上金屋と号し鍋・鉄瓶類を製造していた。
大槻(おおつき)
もともとは葛西氏の一族、寺崎氏の末裔で葛西氏の家臣だったが、江戸時代に磐井郡山目村(現:一関市)で帰農。
本家は代々大肝煎を世襲し、分家は医家となって一関藩の藩医を輩出し、その後も漢学者や国語学者など多くの人材を世に送り出した。
葛西(かさい)
陸奥国中部(現在の宮城県三陸沿岸から岩手県南部にかけての地域)を統治した大身(数郡規模の国人領主)。
鎌倉時代に武蔵国・下総国の御家人・豊島氏当主豊島清元(清光)の三男で、下総国葛西御厨(現:東京都葛飾区・江戸川区・墨田区周辺)を所領として葛西氏を名乗った葛西清重が祖。奥州合戦で武功を立て奥州藤原氏が滅亡後に奥州総奉行に任じられ陸奥国に所領を得て土着した。
戦国時代には寺池城(現:宮城県登米市)を本拠として牡鹿・登米・本吉・磐井・胆沢・江刺・気仙の葛西7郡を支配したが、豊臣秀吉の奥州仕置(1590年)により所領を没収され、1597年に第17代当主だった葛西晴信の死去で大名としての葛西氏は滅亡した。
柏山(かしやま)
陸奥国胆沢郡の国衆。出自は諸説ありはっきりしない。代々葛西氏に従い、大林城(現:岩手県胆沢郡金ケ崎町)を拠点とした。葛西家臣団の中で江刺氏と並ぶ重臣で、伊達氏の天文の乱の際は伊達晴宗に味方したことで一時は主家をしのぐ勢力を誇った。
しかし後継者争いが起こり次第に弱体化し、豊臣秀吉の奥州仕置により主家の葛西家とともに改易され、江戸時代には南部藩士となった。
金子(かねこ)
紫波郡日詰(現:紫波町)で美濃屋と号した豪商。呉服商として成功し後に金融業にも着手。四代目は南部藩の勘定奉行に抜擢され、武士として金子、商人として関を名乗っていた。
1849年に藩主であった南部利剛が美濃守となったことをきっかけに美濃屋から幾久屋と屋号を改めた。
亀卦川(きけがわ)
陸奥国磐井郡の国衆。下総国千田庄亀卦川村(現:千葉県)が発祥で、葛西家初代である葛西清時の奥州下向に随従したものとされている。
豊臣秀吉の奥州仕置(1590年)に抵抗し、葛西・大崎の家臣らで構成された一揆軍中に亀卦川一族の面々とともに当主亀卦川信秀も子供らと出陣し、深谷庄和淵村で木村吉清軍と闘いことごとく討死し、亀卦川氏は滅亡した。
久慈(くじ)
陸奥国久慈郡の国衆。南部氏の一族で南部光行の三男を祖とする系譜といわれるが、「陸奧安倍氏族」の系譜を引くものもあるといわれる。
戦国末期の当主、久慈直治は九戸信仲の三男政則を娘婿としたため、天正19年(1591年)の「九戸政実の乱」で九戸氏に荷担し敗北。直治、政則がともに処刑され、久慈氏の宗家は断絶した。
久慈直治の弟である閉伊郡宮古摂待村(現:岩手県宮古市田老)領主・治光は、九戸家に加担しなかったことで摂待久慈家として存続し、久慈出羽守と称した。
葛巻(くずまき)
岩手県岩手郡葛巻町田子にあった葛巻城を拠点としていた陸奥国糠信郡の国衆。
藤原南家の流れを汲む工藤氏の一族と伝えられ、1189年に岩手郡地頭職を賜わった工藤行光の分流が、応仁年間に葛巻村に移住したのが始まりとされる。
「九戸政実の乱」では九戸氏の誘いを断り南部氏方に与し、江戸期には南部藩士となった。
九戸(くのへ)
陸奥国糠信郡を本拠とした戦国大名。九戸政実(くのへ まさざね)が有名。中野氏・高田氏・坂本氏・上野氏・小軽米氏・江刺氏・江刺家氏・姉帯氏などがこの一族といわれている。
出自には諸説あり、長年、南部氏の祖・源光行(南部光行)の六男、九戸行連(くのへ ゆきつら)とされてきたが、南部光行が陸奥国に下向していない可能性が指摘され、九戸行連の九戸郡領有も疑問が持たれている。
九戸村の九戸神社伝「小笠原系図」(現存せず)には白河結城氏初代である結城親朝の配下の総大将、小笠原氏を九戸氏の始祖とする記述があったとされている。
1591年に四戸氏、七戸氏、久慈氏らとともに俗にいう「九戸政実の乱」を起こし、これが奥州仕置に対する反発ととられ、蒲生氏郷をはじめとした仕置軍に鎮圧され九戸氏は滅亡した。
小梨(こなし)
陸奥国磐井郡の国衆。陸奥日和山(現:宮城県石巻市)城主葛西春重の四男清胤が小梨城(現:一関市千厩町小梨)に拠って小梨氏を称した。葛西氏滅亡後は伊達氏に従い、江戸期に仙台藩士となった。
斯波(しば)
陸奥国紫波郡の高水寺城(現:紫波郡紫波町)に拠って高水寺斯波氏と呼ばれた名門の家柄。室町幕府管領家斯波氏の一族で「斯波御所」「奥の斯波殿」とも呼ばれていた。
稗貫氏や和賀氏と結んで三戸南部氏に対抗していたが、1588年に南部信直に敗れ滅亡した。
鳥畑(とりはた)
陸奥国磐井郡の国衆。桓武平氏の末裔である奥州千葉氏の庶流とされる。
千葉氏一族の胤持が葛西氏近臣に取り立てられ鳥畑城(現:一関市東山町松川)に拠ったのをきっかけに鳥畑氏を称する。その血筋は後に帰農したとされる。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に700人程の鳥畑さんが存在し、うち約150人程が岩手県に分布している。
中村(なかむら)
盛岡城下新穀町(現:盛岡市)の豪商。糸屋と号し呉服・古着などを扱い、南部藩の特産品である「紫根染」を一手に引き受けたことで発展した。
1861年頃に建築された同家の住宅は盛岡市中央公民館敷地内に移築され、国指定重要文化財として現存している。
奈良坂(ならさか)
陸奥国磐井郡の国衆。葛西氏の一族で磐井郡奈良坂郷(現:一関市花泉町)に住んでいたことから奈良坂氏を称した。代々葛西氏に仕えていたが葛西氏の滅亡後は伊達氏に臣従。江戸期に仙台藩士となる。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に400人程の奈良坂さんが存在し、うち約170人程が宮城県に分布している。
楢山(ならやま)
南部家の一門で代々家老を務めた家系。南部家高知衆(譜代上級武士)として、代々盛岡城内丸に屋敷を構えていた。
幕末時の南部藩首席家老だった楢山佐渡は藩論を佐幕にまとめて奥羽越列藩同盟に参加し、敗戦後に斬首された。その後楢山家は宮古市川井にて謹慎していたが、明治22年(1889年)に政府から家名再興の恩典を賜り盛岡へ戻った。
南部(なんぶ)
戦国大名であり、明治期には華族となった氏族。甲斐源氏の流れを汲む加賀美遠光の三男である南部光行が家祖とされる。甲斐国巨摩郡南部郷(現:山梨県南巨摩郡南部町)に住んでいたことから南部氏と称した。
糠信郡に九戸四門制を敷き、光行の長男の行朝が一戸氏、次男の実光は後の宗家三戸南部氏、三男の実長は波木井南部氏や根城南部氏、四男の朝清は七戸氏、五男の宗清は四戸氏、六男の行連は九戸氏と、一族を各地に分出し陸奥北部に大きな勢力を持ったとされる。(異説もあり)
江戸時代には盛岡藩主となり、維新後には華族の伯爵家となる。
浜田(はまだ)
陸奥国気仙郡の国衆。気仙郡千葉矢作氏の分流とされる。三人の兄弟が浜田・高田・長部と分立し高田湾(現:陸前高田市)を中心に勢力を広げた。戦国時代、浜田氏は葛西氏の親族となり、その威光を背景に勢力をさらに広げるが、後に葛西氏に背命して熊谷氏、本吉氏らと抗争を続ける。
豊臣秀吉の奥州仕置によって没落し、後に南部家の家臣となったといわれている。
稗貫(ひえぬき)
陸奥国稗貫郡の国衆。その起こりには諸説あり定かではないが、近年では武蔵国埼玉郡小野保を本貫地とした御家人の中条氏が奥州合戦によって北上川流域の稗貫郡を給されたことに始まるといわれる。
豊臣秀吉の奥州仕置により改易され、和賀氏とともに「和賀・稗貫一揆」を起こすが仕置軍により鎮圧され稗貫は滅亡する。
しかしその末裔は仙台藩士の稗貫家、万城目家、南部藩士の瀬川家として血脈を保ったとされている。
前川(まえかわ)
閉伊郡吉里吉里(現:大槌町)の豪商。常盤国那珂湊の白子屋と貿易を行っていた。盛岡藩の御用商人となり江戸への産品の積み出しを行う一方尾去沢鉱山の発掘請負人にもなり、多角経営で発展した。
村井(むらい)
盛岡城下(現:盛岡市)の豪商。油商人から始まり2代目の時に盛岡藩の勘定奉行に抜擢される。4代目茂兵衛の時に南部藩の70万両もの借金を肩代わりさせられて没落した。
村上(むらかみ)
近江屋と号した遠野の豪商。葛西家家臣で後に帰農した村上愛光が家祖とされる。茶商として成功し、質屋や酒造業も営んでいた。
八重畑(やえはた)
陸奥国稗貫郡の国衆。稗貫氏の一族といわれている。八重畑館(現:岩手県花巻市石鳥谷町)に拠って稗貫氏に属した。豊臣秀吉の奥州仕置により主家の稗貫氏とともに没落した。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に300人程の八重畑さんが存在し、その半数以上にあたる約190人程が岩手県に分布している。
留守(るす)
留守氏は、藤原北家 藤原道兼の玄孫と称した伊沢家景(いさわ いえかげ)を祖とする士族で、奥州征伐後の1190年に家景が源頼朝から陸奥国留守職に任じられ、子孫がその地位を世襲したことから役職をそのまま姓として留守氏を称するようになった。
13代の留守持家以降、伊達氏から養子が次々に送り込まれその影響下に入る。江戸期には伊達家の一門として伊達に改称して水沢を領し「水沢伊達家」と呼ばれた。維新後は留守に復姓して士族となる。
和賀(わが)
陸奥国和賀郡の国衆。その出自は文献により諸説あり、「奥南落穂集」では遠祖を源頼朝とし、「源姓和賀系図」では多田式部大輔忠明、和賀一族・鬼柳氏の「鬼柳文書」では、鎌倉御家人中条義勝(法橋成尋)の次男・成季であるとされている。
戦国期には葛西氏や稗貫氏とともに三戸南部氏と争ったが、豊臣秀吉の奥州仕置により改易。稗貫氏とともに「和賀・稗貫一揆」を起こすが仕置軍により鎮圧され滅亡。後に末裔が仙台藩士となっている。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に2900人程の和賀さんが存在し、その内420人と最も多く分布しているのが秋田県横手市で、これは「和賀・稗貫一揆」の後、和賀氏は西和賀方面に敗走したとされているので、その一団がそのまま奥羽山脈を越えて横手市に定着したのではないかと考えられる。