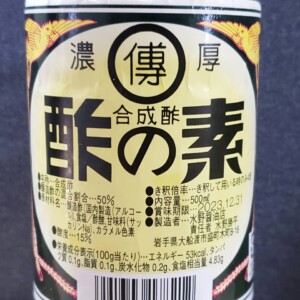宮城県の名門・名家にルーツを持つ苗字30選
目次
- 1 宮城県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
- 1.1 秋保(あきう)
- 1.2 姉歯(あねは)
- 1.3 猪狩(いがり)
- 1.4 石川(いしかわ)
- 1.5 石母田(いしもだ)
- 1.6 一栗(いちくり)
- 1.7 一力(いちりき)
- 1.8 氏家(うじいえ)
- 1.9 遠藤(えんどう)
- 1.10 大倉(おおくら)
- 1.11 大崎(おおさき)
- 1.12 笠原(かさはら)
- 1.13 片倉(かたくら)
- 1.14 金成(かんなり)
- 1.15 熊谷(くまがい)
- 1.16 黒川(くろかわ)
- 1.17 国分(こくぶん)
- 1.18 小谷(こたに)
- 1.19 三分一所(さんぶいっしょ)
- 1.20 白石(しろいし)
- 1.21 但木(ただき)
- 1.22 伊達(だて)
- 1.23 四十九院(つるしいん)
- 1.24 百々(どど)
- 1.25 富沢(とみざわ)
- 1.26 藤崎(ふじさき)
- 1.27 明珍(みょうちん)
- 1.28 茂庭(もにわ)
- 1.29 留守(るす)
- 1.30 亘理(わたり)
- 2 東北各県の名門・名家にルーツを持つ苗字シリーズ
日本全国どこの土地でも、いわゆる「地元の名士」と囁かれるような名門・名家が存在します。「うちはごく普通の一般家庭です」という方でも、よくよく先祖を辿れば実は由緒ある武家の家柄だった…というのも珍しくありません。
今回の記事では、宮城県内各地の名門・名家と呼ばれる苗字について調べてみました。「同級生にそんな苗字の人がいたなぁ…」なんてことがあったら実はその友達は良家のお家柄かもしれませんね…。
宮城県内の名門・名家につながる苗字30選(五十音順)
宮城県の名家は、代々地元に根付いていた国衆をルーツとする家柄が多いですが、戦国時代、県南から勢力を伸ばした伊達氏と県北の大崎氏、沿岸部の葛西氏のいずれかに属する印象です。
秋保(あきう)
陸奥国名取郡の国衆。元は平家の落人だったという伝承が残る。現在の秋保温泉周辺地域であり、現在も地名として残る秋保郷の五つの村(馬場、新川、長袋、境野、湯元)を治めていたことから秋保氏を名乗る。江戸時代に嫡流が仙台藩の重臣となる。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在でも全国に約2,000人の秋保さんが存在し、山形、北海道、宮城の順に多くなっている。
姉歯(あねは)
陸奥国栗原郡二迫の姉歯城城主。祖先は奥州藤原氏4代当主藤原泰衡(ふじわらのやすひら)の家臣だったと伝わる。大崎氏に従っていたが、後に伊達政宗に仕える。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に200人程しかいない希少な姓で、その内100人以上が宮城県に集中している。
猪狩(いがり)
本吉郡気仙沼(現:気仙沼市)で横田屋と号した豪商。代々当主が新兵衛を称して廻船問屋を営み、商船の遭難から海苔製造に転じて成功、維新後は製塩業を営んだ。
石川(いしかわ)
仙台藩一門の元戦国大名。陸奥守源頼義に従って前九年の役に従軍した軍功から石川郡(現:福島県石川郡)を拝領し石川氏を称したのが始まり。
長年にわたって独立大名だったが、豊臣秀吉の奥州仕置で改易。これにより伊達氏家臣となり、陸奥国伊具郡角田(現:宮城県角田市)で21,000石を領した。江戸時代には仙台藩の中で一門首席の座にあった。
石母田(いしもだ)
仙台藩の重臣。鎌倉時代に伊達家初代である伊達朝宗に従い奥州合戦に従軍、陸奥国伊達郡石母田(現:福島県伊達郡国見町)に住み、石母田を称するようになった。
一栗(いちくり)
陸奥国玉造郡の国衆。「ひとつくり」とも。大崎氏の重臣で、一栗放牛やその孫の高春が著名。1591年の葛西・大崎一揆に一揆側勢力として92歳の高齢で出陣した放牛は佐沼城にて討死。孫の高春は大崎氏滅亡後山形の最上義光に仕えた。
現在の宮城県大崎市岩出山下一栗に一栗氏の拠った一栗城跡が存在する。
一力(いちりき)
仙台の大町五丁目に店を構え、大竹左右助とともに仙台の二大茶商と呼ばれた仙台の地方財閥。明治維新後に河北新報社を創立、戦後には東北放送を創立した。
氏家(うじいえ)
陸奥国玉造郡の国衆。岩出山城城主。南北朝時代に奥州探題に任命され下向した斯波家兼(しばいえかね)に付き従い奥州へ。代々斯波氏の一族である大崎氏の家臣として岩出山城を治めていた。
大崎氏滅亡の後は伊達氏の家臣となる。
遠藤(えんどう)
仙台藩宿老で一迫川口(現:栗原市一迫)領主。戦国時代に伊達輝宗に仕えた遠藤基信が祖。以後代々宿老の家系で江戸時代以降に一迫川口を領する。子孫は戊辰戦争後に塩釜神社の宮司を務める。
大倉(おおくら)
陸奥国宮城郡大倉(現:仙台市青葉区大倉)の国衆。清和源氏、源義賢(みなもとのよしかた)の子で木曽義仲(きそよしなか)の兄弟にあたる重義という人物がこの地に隠れ住み大倉氏を名乗ったとされるが真偽は不明。
国分氏、後に伊達氏に仕えるが葛西・大崎一揆にて当主討死により断絶。血脈は熊ヶ根関(現:仙台市青葉区熊ケ根)に移り住み関氏と改称したとされる。
大崎(おおさき)
陸奥大崎5郡(志田郡・玉造郡・加美郡・遠田郡・栗原郡)を支配した戦国大名。南北朝時代に奥州管領として奥州に下向した斯波家兼(しばいえかね)を始祖とする斯波氏の一族。
家兼の嫡男である直持(ただもち)が、自身の先祖である足利家氏(あしかがいえうじ)が領していた下総国香取郡大崎荘(千葉県香取市)に因んで「大崎」を称するようになり大崎氏初代当主となる。支流には最上氏、天童氏などがある。
戦国時代になると次第に衰退、台頭してきた伊達氏の傘下となるも、豊臣秀吉の小田原攻めに参陣しなかったことから後の奥州仕置により所領を没収され滅亡した。
笠原(かさはら)
陸奥国志田郡の国衆。信濃国伊那郡笠原(現:長野県伊那市)の出で、木曽義仲(きそよしなか)の末裔といわれる。宮崎城(現:宮城県加美郡加美町宮崎)を居城として代々大崎氏に仕える。大崎氏滅亡後は伊達氏に仕え、江戸時代には仙台藩の重臣となった。
片倉(かたくら)
信濃国伊那郡片倉村(現:長野県飯田市周辺)に住していたが大崎氏に従い奥州に下ったと伝えられている。仙台藩片倉氏初代である片倉景綱は伊達政宗に側近として仕え、伊達成実とともに軍略に関与したとされる。
子孫は代々一国一城の例外的措置で残されていた白石城に住していたが、江戸時代末期の戊辰戦争の敗戦により知行と白石城を没収され、新天地を求めて北海道開拓へ赴き、現在の登別市や札幌市白石区の開拓に貢献した。
金成(かんなり)
陸奥国栗原郡金成(現:宮城県栗原市金成)の国衆。平安時代後期の陸奥国の豪族である金為時(こんためとき)の子孫が金成に移り住み金成氏を称したといわれる。大崎氏、葛西氏、最上氏と仕え、最上氏改易後は仙台藩士となった。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在は全国に4,000人程の金成さんが存在し、その内およそ1,700人が福島県、特にいわき市に集中している。
熊谷(くまがい)
陸奥国気仙郡の国衆。1189年に鎌倉幕府の御家人である熊谷直国(くまがいなおくに)の弟直宗が下向して赤岩城(現:宮城県気仙沼市松川)に拠ったのが祖とされる。葛西氏に仕え、多くの一族が分立して気仙郡を中心に勢力を広げた。
一族同士の争いが度々起こったが、血脈は後に伊達氏に仕え仙台藩士となっている。
黒川(くろかわ)
陸奥国黒川郡の国衆。斯波一門・大崎氏分家の最上氏一族で、斯波氏の庶流筋であることから大崎氏麾下の国人領主として重きをなした。16世紀初期に伊達氏に服属したものの、9代当主黒川晴氏は伊達家側である留守政景に娘を嫁がせる一方で、大崎義直の子・義康を養子に迎えるなど、大崎氏・伊達氏の双方に配慮を欠かさなかった。
しかし豊臣秀吉による小田原征伐へ参陣しなかったことで奥州仕置において改易され、伊達氏に仕える。11代季氏の死去後、無嗣断絶となった。
国分(こくぶん)
陸奥国の陸奥国分寺付近から宮城郡南部、現在でいう仙台市青葉区~宮城野区付近を中心に勢力をもち、伊達政宗が拠点とする以前の千代城(後の仙台城)を拠点としていた国衆。
戦国時代末期に伊達氏から国分(伊達)盛重を迎えて伊達氏に臣従することとなったが、1596年に伊達政宗の不興を買い、大名としての国分氏は滅亡。その後盛重は常陸国の佐竹氏に身を寄せ、子孫は秋田の久保田藩で幕末まで存続した。
小谷(こたに)
仙台城下の豪商。近江日野商人の小谷庄三郎の支店として国分町で開業。
薬種、瀬戸物を取り扱い豪商に発展し、江戸時代後期の「天保の大飢饉」の際には、藩命で上方に米の買い付けや資金調達の交渉に赴いた豪商6人の中の一人でもある。
三分一所(さんぶいっしょ)
奥州合戦の功績から桃生郡深谷保(現:東松島市・石巻市)を与えられた長江氏をルーツとし、さらに辿ると桓武平氏鎌倉景正を祖とする鎌倉氏の嫡流の血脈。
戦国末期、長江氏最後の当主である長江勝景が領土を三分割し、次男の景重が矢本景重として矢本城(現:東松島市矢本)に、そして三男の家景が三分一所家景として三分一所城(現:東松島市浅井)に入った。
長江の本家筋は滅亡したが、三分一所氏は江戸時代以降も仙台藩士として存続した。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に10~20人程しかいない超希少苗字で、奈良県と静岡県にわずかにみられる。
白石(しろいし)
家祖・刈田経元は藤原経清の子で、奥州藤原氏初代・藤原清衡の同母兄弟であるとされている。経元は後三年の役を清衡と共に戦い、戦後、八幡太郎の通称で有名な源義家から刈田・伊具の両郡を与えられ、刈田郡白石に土着して刈田氏を称した。白石氏を名乗り始めるのは第6代当主・秀長の頃からで、その後伊達氏より養子を迎えたことでその関係が密接になっていく。
伊達政宗の曽祖父にあたる伊達稙宗が当主となった頃から伊達氏の傘下となり、政宗の治世の頃から登米郡寺池城(現:宮城県登米市)を領する。1615年の大坂の陣にて白石宗直がその軍功により一門に列せられ、伊達姓の名乗りを許されて、以降は「登米伊達家」を名乗った。
但木(ただき)
仙台藩の重臣で、橘姓を称し代々伊達家に仕えた。
幕末の仙台藩家老だった但木土佐成行が藩論を佐幕に統一し「奥羽越列藩同盟」の結成に尽力したが、戦後に敗戦の全責任を負って麻布の仙台藩邸で処刑された。
伊達(だて)
陸奥の戦国大名。鎌倉時代に御家人だった伊達朝宗が、奥州合戦で信夫郡(現:福島県福島市)の佐藤基治を攻略した功績から陸奥国伊達郡(現:福島県伊達市)を与えられて伊達と称したのが始まりで、それ以前は中村を名乗っていたといわれる。
15代当主伊達晴宗の時代に拠点を米沢城(現:山形県米沢市)へと移し、17代当主伊達政宗の時代に二本松市、蘆名氏を討ち、大崎、田村、石川、白河等の東北諸大名を従え、伊達氏最大の版図を築く。
その後、豊臣秀吉の奥州仕置によって拠点を岩出山(現:宮城県大崎市)へと移し、関ヶ原合戦後の1601年に仙台に移る。江戸時代には仙台藩主となる。
四十九院(つるしいん)
陸奥国伊達郡四十九院(現:福島県伊達市)をルーツとする。伊達氏に従っていた中島氏の家臣で、戦国時代に中島宗求(なかじま むねもと)が主君・伊達輝宗より金山城(現:伊具郡丸森町金山谷地木戸)の城主に任命されると共に同地に移った。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在全国に50人程しか確認されていない希少な苗字で、その内およそ20人が宮城県、特に伊具郡丸森町に集中分布している。
百々(どど)
陸奥国遠田郡の国衆。大崎氏の庶流で、代々百々城(現:宮城県大崎市田尻)を拠点として大崎氏に仕えた。
政府発表統計および全国電話帳データを元に全国の名字人数を掲載している 名字由来net によると、現在でも宮城県に比較的多い苗字で、特に黒川郡大衡村に多く分布している。
富沢(とみざわ)
陸奥国栗原郡の国衆。葛西氏の庶流といわれる。葛西氏と大崎氏の領境にあたる栗原郡富沢(現:宮城県栗原市栗駒岩ケ崎)の岩ケ崎城(鶴丸城)を拠点としていた。
後に岩手の花巻に移り、江戸時代は南部藩士となった。
藤崎(ふじさき)
仙台城下で日野屋と号した豪商。
1819年に初代三郎助が独立して太物商「得可主屋(えびすや)」を創業。幕末には仙台城下を代表する豪商に発展し、維新後に株式会社藤崎呉服店に改組、1930年には「藤崎」と改称して百貨店となった。
明珍(みょうちん)
甲冑師。平安時代末期に近衛天皇から明珍の姓を与えられたといわれる。室町時代に17代明珍信家が武田信玄に仕え「名人」といわれる。16世紀に小田原、江戸時代に江戸に移り定住する。
全国各地に広がる一門の中でも仙台明珍家は特に有名で、仙台藩家老である片倉家に仕えていた。
茂庭(もにわ)
元々は鬼庭と名乗った藤原北家利仁流斎藤氏の流れをくむ一族で、伊達家8代当主伊達宗遠の戦に鬼庭氏が先鋒を務めたという記録が残るほど古くからの伊達家の家臣。
鬼庭氏11代当主の良直(左月斎)の時代に伊達家重臣の地位を確立。その後、嫡男の綱元が政宗から奉行職を拝命。綱元は後に伊達成実、片倉小十郎景綱と並んで伊達三傑と称された。
そしてこの綱元が豊臣秀吉に気に入られ「庭に鬼がいるのは縁起が悪い」と、秀吉の命により鬼庭から茂庭へと改姓したといわれている。
留守(るす)
留守氏は、藤原北家 藤原道兼の玄孫と称した伊沢家景(いさわ いえかげ)を祖とする士族で、奥州征伐後の1190年に家景が源頼朝から陸奥国留守職に任じられ、子孫がその地位を世襲したことから役職をそのまま姓として留守氏を称するようになった。
13代の留守持家以降、伊達氏から養子が次々に送り込まれその影響下に入る。江戸期には伊達家の一門として伊達に改称して水沢を領し「水沢伊達家」と呼ばれた。維新後は留守に復姓して士族となる。
亘理(わたり)
鎌倉幕府の御家人、千葉常胤の三男・武石胤盛が、奥州合戦で父が得た所領から宇田・伊具・亘理の3郡を分与され、その曾孫・宗胤が亘理に入ったのが始まり。7代当主 広胤の頃から亘理氏を称する。
戦国時代に急速に勢力を拡大していた伊達稙宗の傘下に入り、16代当主 亘理宗隆に男子がいなかったため、伊達稙宗に嫁がせた娘との間に生まれた元宗を養嗣子とし、元宗が亘理氏17代当主となる。
17代当主 定宗の時代に伊達姓が与えられ伊達一門に列し、江戸時代には遠田郡涌谷要害を中心に2万2600石を知行し「涌谷伊達家」を称した。