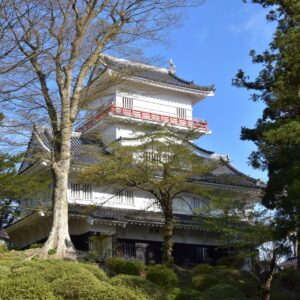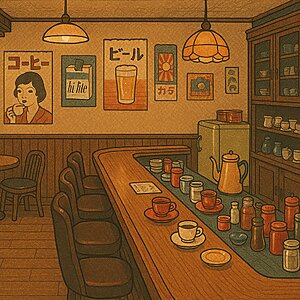【後編】最古級の刀工集団、奥州「舞草鍛冶」とは? 日本刀の発展に与えた影響を解説!
舞草刀はなぜよく切れた? 古刀は再現不可能なロストテクノロジー?
舞草刀の優れた切れ味に関する伝説を見てきましたが、ではなぜそんなにも高い切断力を獲得するに至ったのでしょうか。
その説明をするためにはまず「古刀」と「上古刀」と呼ばれる刀の時代分類について触れておかねばなりません。
「古刀」とは鎌倉時代初期~16世紀終わり頃までに打たれた刀剣のことで、それ以前のものを「上古刀」といいます。
古刀の造りの特徴としては軟らかい鉄と硬い鉄を練り合わせるようにして刀身を形成することが多い点にあり、軟鉄素材を硬鉄素材でくるむようにして仕上げる「新刀 」(古刀以降~江戸時代中期頃の刀)とは異なります。

刀 大隅掾正弘 江戸時代・慶長11年(1606) 出典:ColBase(国立文化財機構所蔵品統合検索システム)
驚くべきことに古刀の組成のほとんどは現代でも解明が進んでおらず、鉄素材の配合や焼成温度、成形法など多岐にわたる技術が復元不可能といっても過言ではないのです。
いわゆるロストテクノロジーと定義しても差し支えなく、現代刀工には古刀の再現を究極的な目標に掲げる人もいるといいます。
したがって、なぜ舞草刀がかくも鋭い切れ味を誇ったのかということは、厳密な意味においては判然としないというのが現実です。
古刀に用いられた鉄には現代的な意味でいうさまざまな不純物が混入していたとも考えられますが、そうした物質の作用によって想像を超えた強度を得たり、あるいはいくつかの伝説にあるように刀身に青や緑などの色が映えたりといった現象を引き起こした可能性が指摘されています。
また、意図的にそうした特殊な刃金を生み出す技と知識こそが秘伝であり、かつての刀工はみだりにその研究成果を公表しなかったといいます。
いわゆる一子相伝の技というものがあり、一度失われてしまうと二度と再現することができないことは想像に難くありません。
今後の科学的調査法の進歩によって古刀の組成や製作法が明らかになっていく可能性は充分にあるといえるでしょうが、古刀の高みは少なくとも現代の刀工も研究を続けている課題の一つです。
舞草刀が多くの武士たちから支持を受けたのは、実際によく切れるうえにおそらく激しい戦いに耐える強靭性も兼ね備えていたためではないでしょうか。
刀はその鋭い刃角から、互いに斬り結ぶと簡単に欠けてしまいます。
現代的な意味での美術的価値においては繊細な研磨が必要ですが、日々実戦に用いた本来的な道具としての刀では刃毀れのしにくさや折れにくさといった継戦性能が重要だったと考えられるでしょう。
そのため、戦の前に敢えて砂利で刀身を磨くようにして刃の状態を粗くするといった処置も行われたといいます。
先にも述べたとおり古刀の製作法には不明な部分が多いため詳細は謎ですが、当時の太刀・刀には鋭さだけではなく長く白兵戦に堪える剛性も求められたと想定するのは不自然ではありません。
さればこそ鎧武者を切り伏せたという「きりすえ」なる舞草刀の伝承も生まれたのではないでしょうか。
かつての舞草派の拠点? 儛草神社とは

最後に、かつての舞草派刀工たちが拠点にしていたと考えられている地に鎮座する、岩手県一関市の「儛草(もうくさ)神社」についてご紹介しましょう。

当社は標高324mの観音山中腹にあり、平安時代の創建で延喜式内社に列せられています。
周辺からは鞴(ふいご)や鉄滓、鉄片や焼土といった鍛冶に関わるものが出土していますが、正確には舞草派が拠点としたことを直接証明する遺跡はまだ発見されていないといいます。

しかしながら「儛草」と「舞草」といった字の相似や、周辺に点在する「鍛冶妻」「湯坪」「清水」といった鍛冶との関連を思わせる地名などから、ここを「舞草古鍛冶発祥の地」としています。
また、舞草刀の鍛冶集団は大陸から渡来してきた人々であるという伝承もあり、それを証明するかのような「唐ノ子」という地名が残っていることも興味深い事実です。

さらに儛草神社が所在する観音山に連なる白山岳では、かつて多くの鉄を含む良質な鉄鉱石が採掘されていました。
安全のため現在ではその跡は埋められていますが、こうした鉄原料を採集できることも鍛冶集団の発展に関わったと考えられています。

儛草神社東側の参道沿いには「舞草鍛冶遺跡」と記された標柱が設置されており、その一帯が鍛冶場であったと想定されていますが、やはり具体的にそれを証明する遺跡は発見されていません。

ただしその道すがらには「吉祥一番地」と呼ばれる開けた空間の場所があり、ここも鍛冶場跡である可能性が指摘されています。
儛草神社の祭神
儛草神社の祭神を確認してみると、「伊邪那岐尊(イザナギノミコト)」「白山姫神(シラヤマヒメノカミ)」「倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)」「熊野大神(クマノオオカミ)」の四柱が奉斎されていることが分かります。
伊邪那岐尊は日本創生の父神、白山姫神は石川県・岐阜県・福井県にまたがる白山への信仰に関わる神、倉稲魂命はいわゆる稲荷神、熊野大神は和歌山県の熊野に鎮座する神で東北でも広く崇敬されています。
これらの神を見るとポピュラーでありつつも、鍛冶との直接的な関係は認めにくいといえるでしょう。
しかし神域には養老2年(718) 創建と伝わる「白山妙理権現社」、そして「金鋳神像跡」の標柱が存在します。
白山妙理権現社は巨石を御神体にしていると思われ、いわゆる「磐座信仰」の古さを感じさせる場所でこちらが本来の儛草神社という説もあるようです。
「金鋳神像跡」には一見何の遺構や痕跡も見られませんが、この「金鋳神(かないがみ)」とは別名を「金屋子神」「金屋神」ともいう製鉄を司る神なのです。
火神の性質も持っていることから鍛冶師・蹈鞴師・鉄穴師・鋳物師など製鉄や鉱業に関わる職能者を中心に崇敬されてきた一柱で、儛草神社を舞草鍛冶の神であるとすればこちらの神格がより刀工にふさわしいといえるのではないでしょうか。
もちろん一柱の神だけを信仰していたわけではなく、製鉄・鍛冶を中心とした生業にも土・水・風といったさまざまな自然の要素が不可欠であることから、複数の神格を集合体として祀っていたとしても不自然ではありません。
儛草神社<Information>
- 名 称:儛草神社
- 住 所:〒021-0221 岩手県一関市舞川大平5
- 電話番号:0191-46-5319
- 公式URL:-
Google Map
最後に
舞草刀は鎌倉時代を遡る在銘品が見つかっていないことや、刀工集団の拠点と考えられる舞草地区・儛草神社との関連が立証されていないなど、まだまだ謎の多いテーマです。
しかしながら、舞草の地が日本刀という歴史上の画期を作ってきたといっても過言ではない器物の誕生に影響を与えてきたことを思うと、実に感慨深いといえるでしょう。
今後の研究の発展に伴い、さらに驚くべき舞草刀や奥州刀の事実が明らかになっていくのを楽しみに待つことといたしましょう。
〈主要参考文献・サイト〉
- 赤沼英男『東北地方北部における古代・中世の鉄・鉄器生産と流通 ー考古学と自然科学の学際的研究ー(概要書)』 早稲田大学審査学位論文(博士)の要旨 1992 <リンク:PDFファイル>
- 高橋信雄「蕨手刀」『まてりあ 34巻10号』 公益社団法人 日本金属学会 1995 <リンク:PDFファイル>
- 渡瀬 淳子「剣巻の成立背景 -熱田系神話の再検討と刀剣伝書の世界-」『国文学研究(138 12-22)』 早稲田大学国文学会 2002<リンク:PDFファイル>
- 特別展 「草創期の日本刀 反りのルーツを探る」 財団法人佐野美術館・大阪歴史博物館・一関市博物館 2003
- 赤沼英男・熊谷 賢「陸前高田市立博物館所蔵被災蕨手刀の金属考古学的解析」『岩手県立博物館研究報告 第 30 号』 岩手県立博物館 2013 <リンク:PDFファイル>
- いちのせき市民活動センター 伝説調査ファイルNo.4 「舞草鍛冶」<リンク:Webサイト>





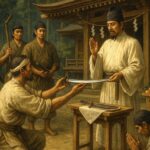







![どうして世界各地には[白神山地]より広いブナの原生林がなくなった?【青森県藤里町】 白神山地遠方岩木山](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/09/0d3ff92f34c42ae905cbae977b5345c3-150x150.jpg)