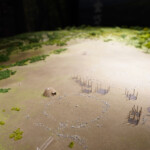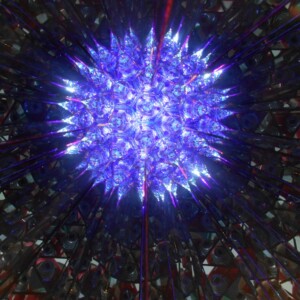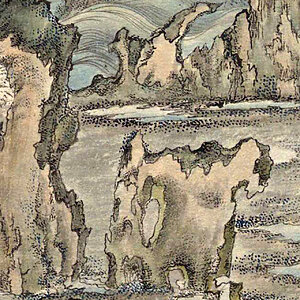岩手県釜石市の世界遺産「橋野鉄鉱山」は明治日本の産業革命を象徴する構成資産の一つ!
目次
橋野鉄鉱山・橋野高炉跡(はしのこうろあと)は、岩手県釜石市橋野町に所在する高炉跡で1957年に国の史跡に指定され、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つになります。
登録名は「橋野鉄鉱山」。
世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」構成資産
世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産は8県11市にまたがる23件になります。簡略化してますが以下エリア分けされた全国の構成資産になります。
- エリア1ー山口県萩市エリア
- 萩反射炉、恵美須ヶ鼻造船所跡、大板山たたら製鉄遺跡、萩城下町、松下村塾
- エリア2ー鹿児島県エリア
- 旧集成館、寺山炭窯跡、関吉の疎水溝
- エリア3ー静岡県エリア
- 韮山反射炉
- エリア4ー岩手県釜石エリア
- 橋野鉄鉱山
- エリア5ー佐賀県エリア
- 三重津海軍所跡
- エリア6ー長崎県エリア
- 小菅修船場跡、三菱長崎造船所第三船渠、三菱長崎造船所ジャイアント・カンチレバークレーン、三菱長崎造船所旧木型場、三菱長崎造船所占勝閣、高島炭坑、端島炭坑、旧グラバー住宅
- エリア7ー福岡県福岡県大牟田市・熊本県荒尾市・熊本県宇城市エリア
- 三池炭鉱・三池港、三角西港
- エリア8ー福岡県北九州市・中間市エリア
- 官営八幡製鐵所、遠賀川水源地ポンプ室
上のリストの中でも時期は初期発展期と産業形成期の2つに分かれます。
初期発展期の構成資産
製鉄・製鋼
萩(萩反射炉、大板山たたら製鉄遺跡等)、鹿児島(集成館)、韮山(韮山反射炉)、釜石(橋野鉄鉱山・高炉跡)
造船
萩(恵美須ヶ鼻造船所跡等)、佐賀(三重津海軍所跡)、鹿児島(集成館)、長崎(小菅修船場等)
石炭産業
長崎(高島炭鉱、端島炭鉱等)、三池(三角西(旧)港)
産業形成期の構成資産
製鉄・製鋼
八幡(八幡製鐡所)
造船
長崎(長崎造船所)
石炭産業
三池(三池炭鉱、三池港)
世界的にも稀ですが、なぜ日本の産業革命が世界遺産となったか、これには訳があります。以下世界遺産センター公式サイトからの引用とはなりますが、世界からは以下のように見えていました。
封建制度下の日本が欧米から技術移転を模索し導入した技術を、国内の需要や伝統に適合するよう改良し、日本が短期間で世界有数の産業国家になった過程を物語る。製鉄・製鋼、造船、石炭という基幹産業からなる技術の集合体は、非西洋国家で初めて産業国家化に成功した世界史上特筆すべき業績を証明している。
© UNESCO World Heritage Centre 1992-2024
上で世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の簡単な説明をさせていただきましたがその中でも岩手県釜石市橋野町に所在する「橋野鉄鉱山」は日本の産業革命の中でも取り分け重要な役目を果たしていました。
それは東北、岩手県、釜石市の土地柄、自然があったからこその事です。
岩手県釜石市、橋野鉄鉱山より以前に発見されていた鉱山「釜石鉱山」

そもそも何故に岩手県釜石市なのか?それは海が目の前に広がっていたからでもなく、たまたま岩手の地だからでもありません。この地が花崗岩となるマグマと周辺の石灰岩の反応(接触交代)でできた鉄鉱床で、 日本最大の鉄鉱山「釜石鉱山」 であったからこそです。
この「釜石鉱山」は北上山地の沿岸部に位置しており、明治時代の開坑から現在まで150年余の歴史を持つとされています。1727年に江戸幕府付採薬使(”さいやくしき”ー諸国を旅して薬草などを採取・研究した者)の阿部将翁(あべ しょうおう)が仙人峠で磁鉄鉱(鉄の酸化鉱物の一種)を発見、主要の鉄以外に金・銀・銅・鉛・亜鉛なども産出し閉山後の現在も研究などの用途で年間100トン程度の採掘がおこなわれています。
阿部将翁が仙人峠で磁鉄鉱を発見後、1849年には三河の高須清兵衛と陸中の中野大助とが合資で大橋に旧式高炉を建設します。
そして1857年、南部藩士大島高任(おおしま たかとう)が橋野鉄鉱山にて日本初の高炉を使った出銑(”しゅっせん”ー高炉の中で精錬された銑鉄が溶融状況で湯だまりにたまっているものを取出すこと)に成功し、1862年には高炉を2基増設、銑鉄を増産することになります。
近代製鉄の父、南部藩士・大島高任

日本最大の鉄鉱山から日本一の鉄の街へと移り変わった際に忘れてはいけない、この人をなくしては製鉄を語れない存在が「近代製鉄の父、大島高任(おおしま たかとう)」です。
盛岡の医師の家に生まれ蘭学を学ぶ
大島高任は1826年5月11日、盛岡藩の侍医・大島周意の長男として盛岡仁王小路で生まれ、1842年17歳の時に蘭学(医学)を習得するために上京、江戸で箕作阮甫(みつくり げんぽ)、坪井信道(つぼい しんどう)から蘭学を学びます。
長崎で近代兵器に興味を持ち、鉄反射炉の蘭書を翻訳
その後は長崎に留学し、西洋兵学・砲術、採鉱、精練に興味を持ち、長州藩士・手塚律蔵(てづか りつぞう)とともに、反射炉築造のバイブルであったヒューゲニン少将著『ロイク王立鉄製大砲鋳造所における鋳造法』を翻訳します。
水戸藩に招かれ鉄反射炉の建設に成功
その後、水戸藩に招かれ、那珂湊に反射炉の建設に成功、大砲の鋳造に成功しますが、原材料が砂鉄の為にその性能は高くはありませんでした。それからは高品質な鉄を作るべく、1857年に良質の鉄鉱石が産出する地、甲子村大橋(現岩手県釜石市甲子町大橋)に西洋式高炉を建設し、上でも記載した通り1857年に日本で初めて鉄鉱石精練による出銑操業に成功しました。
なぜ大島高任が「近代製鉄の父」と呼ばれるか。それは後の明治政府においても技術者として高く評価され、鉱業界の第一人者として活躍したからです。
世界遺産 橋野鉄鉱山(橋野高炉跡)

世界遺産「橋野鉄鉱山(橋野高炉跡)」は岩手県釜石市橋野町に所在します。
1957年に国の史跡に指定され、1984年にアメリカ金属協会から歴史遺産賞(HL賞)を受賞、そして2015年に世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産となりました。世界遺産での登録名は「橋野鉄鉱山」となり、鉄鉱石の採掘場跡と運搬路跡、高炉跡の総称を言います。
また、橋野高炉跡の一番奥には鉄鉱山へのゲートがあり、二股林道として道は続きますが先は国有林となっているため立入禁止になります。
橋野高炉跡

橋野高炉跡は現存する高炉跡としては国内最古になります。安政4年12月1日に大橋(現在の旧鉱山事務所付近)に大島高任が蘭書を参考に洋式高炉を建設し鉄の連続生産に成功後、翌年の安政5年に仮高炉(現在の三番高炉)で操業を開始したのが橋野鉄鉱山の始まりになります。

高炉が釜石市橋野町の山奥にできた理由は何も良質な磁鉄鉱が取れたから、だけではありません。

鉄の他にこの山で製鉄に欠かせない良質な炭を量産することができ、かつ小川が流れている事により水路を引き、水力で稼働するフイゴ(炭などの燃料を高温で燃焼させるために空気を送り込む装置)から高炉に十分な風を送り製鉄することができたのも大きな要因です。

敷地内では散策しているとそこら中で上の写真のような鉱滓(こうさい・スラグ)と呼ばれるものを見かけます。小石程度から直径60cmは超えるであろう大きなものまで大小様々なものがありますが、

これは鉄やニッケル、クロムなどの鉱物を精錬する際に発生する目的成分以外の溶解物質で、産業廃棄物の一種とされています。つまりこの鋼滓が当時、橋野高炉が稼働していた証になります。余談とはなりますが個人的には高炉跡よりもこの鉱滓にロマンを感じました。

橋野高炉が稼働していた頃は1000人程の作業員が従事しており、三基の巨大な高炉の他に従業員が寝泊まりする長屋や鍛治屋敷、水車場、給料を支払う「御日払所」、それに神社も置かれていました。

現在の橋野高炉跡地では三基の高炉跡の石垣が見られます。高炉の石組みには城などの石垣積みの技術が用いられ、高炉を覆っていたのは日本の木造建築が利用されていました。高さは10mほどあった事が資料から分かっています。これは大島高任が世界に負けない鉄を作るために日本の技術を利用し、建造しました。
ちなみに橋野高炉には一番から三番まで高炉がありますが、最初に建造されたのが三番高炉となり、この番号の順番は川上から数えての順番になります。
橋野鉄鉱山インフォメーションセンター

橋野鉄鉱山には2014年に建てられた「橋野鉄鉱山インフォメーションセンター」があります。橋野高炉跡に入る前にはこのインフォメーションセンターにて前知識を入れてから入場をすることをお勧めいたします。
案内人の方たちも地元の親切な方たちで優しく丁寧に迎え入れてくれます。
橋野鉄鉱山<Information>
- 名 称:橋野鉄鉱山インフォメーションセンター
- 住 所 : 〒026-0411 岩手県釜石市橋野町2−6
- 開館時間 : 9時30分~16時30分
- 休館日 : 12月9日から3月31日まで
- 利用料金 : 無料
- アクセス
- JR釜石駅から車で約50分(※釜石駅付近にタクシー、レンタカー店有)
- JR遠野駅から車で約35分(※遠野駅付近にタクシー有)
- 大型バスは、県道釜石遠野線を通り抜けできません。
- 路線バスの最寄り停留所は「中村」になりますが、そこからのタクシー利用は困難です。その場合、徒歩で県道及び市道を片道約10km移動することになりますのでご注意ください。