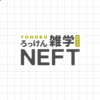南陽市発祥の伝統野菜「オカヒジキ」は栄養豊富な陸のヒジキ!【山形県】
オカヒジキ?ヒジキ?海藻がオカってどういうこと、と不思議に思いますよね。
山形県南陽市では、畑で作るヒジキ「オカヒジキ」が食卓を彩ってくれます。県外ではあまり見聞きしないと思われる「オカヒジキ」の魅力をご紹介させていただきます。
オカヒジキって何者?
オカヒジキは、ヒユ科オカヒジキ属の一年草で、別名ミルナ(水松菜)とも呼ばれます。
塩性の砂地に自生する野草で、日本では野菜として栽培もおこなわれており、古くから若い葉や茎を食用にしています。

葉の部分が海藻のヒジキに似ていたことからオカヒジキと呼ばれるようになったそうです。
オカヒジキとして栽培されるようになった発祥は山形県南陽市砂塚村(現:南陽市)で、海からは遠い内陸部でした。
なぜ内陸部で栽培が広がったのか?というと、江戸時代に山形県北部の庄内浜で自生していたオカヒジキの種が船便の荷物に紛れて、最上川流域の船着き場のあった南陽市にたどり着いたから…と言われています。
ちなみにオカヒジキを野菜として栽培しているのは日本だけのようです。
ハウス栽培やトンネル栽培が主で、湿気がこもってしまうと病気になりやすく一晩で全滅…などということも。ほぼ無農薬栽培で殺虫剤も使えないので虫との闘いと苦労が絶えないようです。
ですがその農家さんの苦労のおかげで我々消費者は安心してオカヒジキを食べることができありがたいですよね。
オカヒジキって細いし栄養あるのか疑問!

オカヒジキはカロテンが豊富な緑黄色野菜です。
カリウムの含有量も他の野菜と比べてもトップクラスで、カルシウム、鉄、ビタミンK、マグネシウム、マンガンも豊富に含まれています。
葉も細く茎ばっかりに見えてしまいますが、意外にも栄養豊富な野菜なのです。
どうやって食べると美味しいの?

代表的な調理法は「お浸し」です。
醤油やめんつゆをかけただけの簡単調理ですが、オカヒジキのシャキシャキ感が癖になることまちがいなしです。
マヨネーズもチョイ足しすると子ども受けも抜群で、地元南陽市の小中学校では給食のメニューにも登場するそうです。

オカヒジキそのものが癖のない味なので、シーチキンなどと和えていただくと、栄養価も一段とアップし好まれています。
辛子あえにするとお酒のおつまみとして人気があります。特に日本酒との相性は最高では?と思っています。
その他に天ぷらや炒め物、刺身のツマなどレパートリーも多く、市場に出回る時期も長いことから山形県内では大変人気のある伝統野菜です。
買うときの選び方や調理するときの注意点
オカヒジキは県外への出荷は少ないようですが、近県の市場では見かけることも多くなってきていて、栽培自体も各地に広がりを見せているようです。

購入の際は、株が大きくなってしまうと茎が固くなってしまうので小さめのものがおススメです。根元近くの赤みを帯びたところは硬くて食べられないので切り落としてから調理しましょう。
まとめ
「オカヒジキ」?と聞いただけではどのようなものなのか想像がつきませんよね。ヒジキは海藻が一般的なのでまさか野菜だとは思いませんでした。
オカヒジキのルーツを探っていくと江戸時代初期から食用として利用しようと栽培していたらしく、案外歴史の古い野菜でした。
発祥の地、南陽市では学校給食にも登場するほど県民に愛されている野菜です。美味しく栄養も豊富なオカヒジキ。チャンスがあったらぜひ食べてみてください。