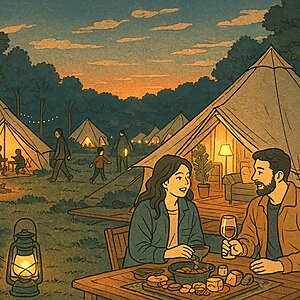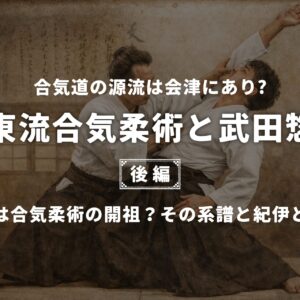日本で最初に宇宙とつながった「国立天文台水沢キャンパス」【岩手県】
目次
『国立天文台水沢キャンパス』は、名前は大学みたいですが、国立天文台の観測所です。
前身は1899年(明治32年)に開所した国立天文台としては現存最古の「緯度観測所(水沢緯度観測所)」で、現在は最前線の月惑星探査や宇宙を解き明かす世界的プロジェクトに関わっています。
敷地内には宇宙を楽しく学べる「奥州宇宙遊学館」や初代所長木村榮の業績を称えて開設された「木村榮記念館」があり一般公開されています。
日本の天体観測技術を世界に知らしめた「水沢緯度観測所」
緯度観測所とは地球の極軸がほんのわずか動いている運動(極運動)を解明するために作られた観測所です。
1898年(明治31年)に開催された万国測地学協会で設立が決まった北緯39度8分上の緯度観測所6か所のうちのひとつで、1899年(明治32年)に創設されました。
緯度観測所は、水沢のほかアメリカ大陸3か所(ゲイザーズバーグ、シンシナティ、ユカイア)、地中海の島カルロフォルテ(イタリア)、中央アジアのチャルジュイ(現トルクメニスタン)に置かれました。
観測方法は同一の観測機材を用いて、同一の星を毎日観測しその観測データを比較するといったものです。

「水沢緯度観測所」は第2次世界大戦中も国際情勢に影響されることなく観測を続け、1987年までその役割を果たしてきました。
その間1922年(大正11年)から1936年(昭和11年)、1962年(昭和37年)から1988年(昭和63年)までの間、世界各地にある緯度観測所の中央局としての機能を担っています。

「水沢緯度観測所」は、1989年以降「水沢VLBI観測所」となって、VERA(天文広域精測望遠鏡・VLBI Exploration of Radio Astrometry)(※1)や RISE(Research of Interior Structure and Evolution of solar system bodies) 月惑星探査プロジェクト(※2) の拠点として、銀河系の3次元地図の作成や月惑星探査など地球と宇宙の謎を解き明かすための世界的プロジェクトに関わっています。

「国立天文台水沢キャンパス」の見学(公開部分)は自由ですが、最初に「奥州宇宙遊学館」に立ち寄り、パンフレットを受け取るとより理解が深められます。
INFORMATION
- 施設名称:国立天文台水沢キャンパス
- 住所:岩手県奥州市水沢星ガ丘町2-12
- 電話番号:0197-22-7111
- 開場時間:9:00~17:00
- 見学自由
- URL:http://www.miz.nao.ac.jp/
GOOGLE MAP
宮沢賢治の原点となった「水沢緯度観測所」

『風の又三郎』『銀河鉄道の夜』などで知られる宮沢賢治(みやざわけんじ/1896年~1933年)は、生涯の多くを生地岩手県で過ごしていますが、その作品の原点が「水沢緯度観測所」だったのです。
賢治はたびたび「水沢緯度観測所」を訪れ、その体験をもとに『風の又三郎』の原作になった『風野又三郎』や『銀河鉄道の夜』を発表しています。
楽しく宇宙の謎に迫る「奥州宇宙遊学館」

『奥州宇宙遊学館』は、岩手県奥州市水沢にある国立天文台水沢キャンパスの旧本館を利用した宇宙と科学を楽しく学べる科学館です。
『奥州宇宙遊学館』では、「緯度観測所」や「国立天文台」で使用されてきた歴史的な天文観測機器が常設展示され、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の月探査機に搭載された観測装置(開発モデル)の見学もできます。
ほかに宮沢賢治と「緯度観測所」の関係資料を集めた常設展示「風」や隕石に触ったり、7億分の1スケールの太陽系模型で惑星のことを学んだりすることができます。また、シアター室では4次元デジタルシアター4D2Uが楽しめます。3Dメガネをかけて見る迫力ある宇宙の映像は必見です。

INFORMATION
- 施設名称:奥州宇宙遊学館
- 住所:岩手県奥州市水沢星ガ丘町2-12
- 電話番号:0197-24-2020
- 開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
- 入館料:おとな学生 300円、生徒児童 150円
- シアター/おとな学生200円、生徒児童 100円
- 休館日:火曜日(祝休日の場合は翌日)、12月29日~1月3日
- URL:http://uchuyugakukan.com/
GOOGLE MAP
水沢緯度観測所初代所長木村榮の業績を称える「木村榮記念館」

水沢に「緯度観測所」が開設された当初は、日本の観測技術を欧米の学者が過小評価していて、その技術を疑っていました。
しかし、もともと日本には江戸時代に暦を作るために星を観測していた天文方(てんもんかた)と呼ばれる人たちの高い測量技術があり、さらに初代所長に任命された木村榮(きむらひさし/1870年~1943年)の世界的な発見“Z項”(※3)がその地位を確かなものしたのです。
※3参照リンク

『木村榮記念館』には、木村の輝かしい業績の資料や「緯度観測所」当初から使われていた眼視天頂儀(天頂を観測する望遠鏡)や貴重な測定器、また当時の観測室の様子を示す写真などが展示公開されています。
建物は1900年(明治33年)に建てられた水沢緯度観測所の初代本館で、1921年(大正10年)に現在「奥州宇宙遊学館」として利用されている観測所2代目本館が建てられた後も昭和41年(1966年)まで研究室として使用されていました。国の登録有形文化財に指定されています。
INFORMATION
- 施設名称:木村榮記念館
- 住所:岩手県奥州市水沢星ガ丘町2-12
- 電話番号:0197-24-2020(奥州宇宙遊学館)
- 開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
- 観覧料:無料
- 休館日:火曜日(祝休日の場合は翌日)、12月29日~1月3日
- URL:https://www.miz.nao.ac.jp/kimura/