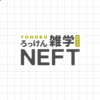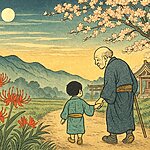どんと祭の裸参りで有名な仙台総鎮守にして国宝の「大崎八幡宮」【宮城県】
目次
大崎八幡宮は、宮城県仙台市青葉区の西寄りに鎮座する神社で、政令指定都市である仙台市青葉区八幡の県道31号線(仙台村田線)に沿った場所にあります。
旧社格は村社であり、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后を御祭神としていて、大崎八幡宮の松焚祭(どんと祭)で有名な神社でもあります。
国宝に指定される桃山建築の社殿
大崎八幡宮の確かな創建年代は不明ながら、平安時代に東北地方の蝦夷征討を朝廷より託された坂上田村麻呂が現在の大分県にある宇佐神宮から武神である八幡神を勧請し、蝦夷政党の前線基地となっていた鎮守府のある胆沢城(現:岩手県奥州市)のなかに祀ったことがはじまりであるとされています。
この為もとの名称は鎮守府八幡宮と呼ばれていたということです。
八幡太郎こと源義家が勧請したものを大崎氏が大崎八幡として再興
その後、前九年の役の際に八幡太郎こと源義家が実父源頼義とともに安倍氏の乱を平定。その折に旧新田の柵の守護神だった子松神社の跡地(現:宮城県大崎市)に石清水八幡を勧請し武具を納置。
室町時代には将軍家である足利氏の一門であり、奥州管領として東北地方で支配的な地位を獲得していた大崎氏が「この神社が自身の遠祖である源義家が勧請したもの」だと知り、1361年に社殿を再興し祭式を復し、大崎5郡(志田郡、玉造郡、加美郡、遠田郡、栗原郡)の総鎮守として大崎八幡と改称しました。
大崎八幡宮の由来にある鎮守府八幡宮の遷祀はこの時行われたものと思われます。
この大崎氏については戦国時代に地元の国衆と覇権を争って次第に勢力を失い、豊臣秀吉が天下を支配するようになると小田原の北条攻めに参陣しなかったとして、1590年の奥州仕置にて改易を申し渡されてしまいます。
伊達政宗の手で大崎より仙台へ
続いてこの地域を支配するようになった伊達政宗は、現在の宮城県大崎市にあった岩出山城から仙台市の仙台城(通称:青葉城)に拠点を移すにあたって、仙台城の乾方向にあたる現在地に大崎八幡宮の社殿を新たに造営し、大崎八幡神社と自身の長年の本拠であった米沢の成島八幡宮を共にこの地に奉遷しました。
この時伊達政宗が寄進した社殿は権現造りで全体に黒漆塗りとしたもので、金色にかがやく装飾金具をちりばめており、桃山建築の粋をなすものとして現在では国宝に指定されているところです。

戌年と亥年生まれの守り本尊
大崎八幡宮ではさまざまな祭事が行われていますが、特に9月の例大祭は宮城県の無形民俗文化財に指定されている能神楽や仙台藩のころから続いている流鏑馬などが行われるにぎやかなものです。
また仙台城の乾方向にあるということから、戌年、亥年の生まれの人たちから広く信仰を集めており、これは現在にも続いています。
大崎八幡宮<Information>
- 名 称:仙台総鎮守大崎八幡宮
- 住 所:〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡4丁目6−1
- 電話番号:022-234-3606
- 公式URL:仙台総鎮守【国宝】大崎八幡宮