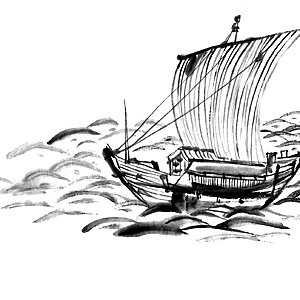3つのユネスコ文化遺産『大日堂舞楽』『花輪ばやし』『毛馬内の盆踊り』-鹿角市の見所伝統行事①
目次
秋田県鹿角市(かづのし)は、秋田県の東北部に位置し、当時の花輪町(はなわまち)・尾去沢町(おさりざわまち)・十和田町(とわだまち)・八幡平村(はちまんたいむら)の4町村が1972年(昭和47年)に合併して誕生した自治体です。市が誕生するまでは、秋田県小坂町とともに鹿角郡を形成していて、江戸時代までは鹿角郡全体が南部藩(現岩手県・青森県)に属していました。
明治維新の混乱で翻弄された鹿角エリア
明治維新の時、大名が支配していた藩をすべて廃止し、中央政府が管理する県として再編成しました。明治維新から廃藩置県が行われる間の数年間には、もともとあった出羽国(でわのくに/秋田県と山形県)が羽後国(うごのくに/ほぼ秋田県)と羽前国(うぜんのくに/山形県)に分割されたり、地域内にいくつもあった藩が県と名称変更されたりと大混乱していたのですが、1871年(明治4年8月)に行われた廃藩置県では、羽後国は秋田県、羽前国は山形県へ統合されました。
その際に、一部の地域は地域性などが考慮され、属性が変更されています。たとえば秋田県南部、鳥海山南麓地域の最上川より北の部分は、飽海郡(あくみぐん)と呼ばれ、羽後国(秋田)のエリアでしたが、廃藩置県では山形県(山形県遊佐町=ゆざまち・酒田市の一部)となりました。
最終的に秋田県への編入で落ち着いた鹿角市
鹿角市を含む鹿角地域は、江戸時代には盛岡(岩手県)や八戸(青森県)を領地とする南部藩(なんぶはん/盛岡藩)に属していました。明治維新後の藩解体という流れの中で、南部藩の盛岡地域が盛岡県となったため、盛岡県所属となり、その後1869年(明治2年)には、九戸(くのへ)県、八戸(はちのへ)県、三戸(さんのへ)県、江刺(えさし)県と、1年で5か所も所属県が変わったのです。その中でも一番短かったのが八戸県の6日間でした。
その後廃藩置県時に鹿角地域が鹿角郡として秋田県に編入されたのです。編入された理由は、正式な書類は残っていないのではっきりしませんが、鹿角地方が東北の西と東を分ける分水嶺の役割を果たす奥羽山脈の西側、つまり秋田県側に存在していて、日本海に注ぐ米代川が生活・経済の大動脈だったからだといわれています。
太古から人が住み、大湯環状列石や尾去沢鉱山跡が有名な鹿角市
鹿角地方は太古の時代から人が暮らしていました。鹿角盆地を流れる米代川の河岸にある丘の上には、縄文時代から平安時代にかけての遺跡が多く見つかっています。特に縄文時代後期(約4000年前)の大型ストーンサークル遺跡「大湯環状列石」は、、日本の代表的な縄文遺跡として世界文化遺産に登録されています。


鹿角が歴史書にはじめて登場するのが9世紀後半の平安時代で、「上津野(かづの)」という地名で書かれています。
鎌倉時代が始まる頃には、鹿角地方は南部藩の臣下たちが支配していて、以来江戸時代まで南部藩の領地でした。南部藩が奥羽山脈を越えた僻地にある鹿角地域を藩領として手放さなかったのは、地域内に東北最大級の鉱山「尾去沢鉱山」があったからと考えられています。
大湯環状列石 Information
- 施設名称:大湯環状列石
- 文化財指定:世界遺産(「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産)・国指定特別史跡
- 所在地:秋田県鹿角市十和田大湯字万座
- 電話番号:0186‑37‑3822
- 見学時間:
- [遺跡]
- 4月~10月/9:00~17:30(公開範囲を制限しています)
- 11月/9:00~16:00(月曜日は閉鎖。公開範囲を制限しています)
- 冬季閉鎖(11月中旬~4月中旬)
- ※見学のみは無料
- [ストーンサークル館]
- 通常期/4月1日~10月31日 9:00~18:00
- 降雪期/11月1日~3月31日 9:00~16:00
- 休館日:降雪期のみ 月曜日(祝休日の場合は翌日)、年末年始
- 入館料:おとな 320円、こども 110円
- URL:大湯環状列石
- アクセス:
- 公共交通機関/JR花輪線鹿角花輪駅下車大湯温泉行き路線バスで約35分、大湯環状列石前バス停下車
Google Map
尾去沢鉱山跡 Information
- 施設名称:史跡 尾去沢鉱山
- 文化財指定:近代化産業遺産
- 所在地:秋田県鹿角市尾去沢字獅子沢13‑5
- 問い合わせ先:0186‑22‑0123
- 見学時間:
- 4月~10月/9:00~17:00
- 11月~3月/9:00~15:30
- 休業日:
- 冬期のみ水曜日(年末年始・祝休日は営業)
- 入場料:
- 鉱山歴史館/無料
- 観光坑道コース/おとな 1000円、中高生 800円、小学生 600円
- ※砂金取りなどの体験メニューは別途
- URL:尾去沢鉱山
- アクセス:
- 公共交通機関/JR花輪線鹿角花輪駅からタクシーまたは路線バスで約10分
- 車/東北自動車道鹿角八幡平ICから約10分
南部藩の影響もあって独自に発展し、伝承された3つの伝統芸能
江戸時代までは南部藩、明治以降は秋田県に属している鹿角地方には、隣接する大館市や米代川沿岸の地域とは少し違った南部色の強い民俗芸能や風習、言語などが残っています。鹿角市には国や県、市指定の無形民俗文化財が数多く存在しているのですが、特筆すべきは国の無形民俗文化財に指定されている民俗芸能が3件もあることです。
もともと秋田県には、国の無形民俗文化財に指定されている貴重な民俗芸能が17件あり、都道府県の中で最も多い県(2位は新潟県の13)なのですが、鹿角市はそのうちの3件が指定されている県内で秋田市と並んで最も多い自治体となっています。しかもその3件すべてがユネスコ無形文化遺産にも登録されている日本を代表する文化遺産なのです。
ここでは数多くある民俗芸能の中から、国指定重要無形民俗文化財の3件、『大日堂舞楽(だいにちどうぶがく)』『花輪ばやし(花輪祭の屋台行事)』『毛馬内の盆踊(けまないのぼんおどり)』をご紹介します。
八幡平の守り神「大日霊貴神社」の大祭で演じられる秋田県最古の舞楽『大日堂舞楽』

『大日堂舞楽(だいにちどうぶがく)』は、八幡平の北西部に広がる鹿角市八幡平にある、継体天皇(けいたいてんのう/450年?~531年?/第26代天皇)が建立したと伝わる「大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ/通称大日堂)で、毎年1月2日に奉納される舞楽です。その起源は一時途絶えていた大日堂を、元正天皇(げんしょうてんのう/680年~748年第44代天皇)の命令で高僧行基(ぎょうき・ぎょうぎ/668年~749年)が再建した際に、都から連れてきた楽人たちが奉納した舞を、地元に人たちが伝承したといわれていて、秋田県最古の歴史を持っています。

大里(おおさと)、谷内(たにない)、小豆沢(あずきさわ)、長嶺(ながみね)の4集落がそれぞれ異なる舞を伝承しており、能衆(のうしゅう)と呼ばれる人々が世襲で舞を継承しています。舞は4集落の能衆による「神子(みこ)舞」と「神名手(かなて)舞」、小豆沢の「権現舞」と「田楽舞」、大里の「駒舞」「鳥舞」「工匠(こうしょう)舞」、長嶺の「烏遍(うへん)舞」、谷内の「五大尊(ごだいそん)舞」の9演目が伝承されており、仮面をつけたり採物(とりもの)を持ったりして笛や太鼓の囃子で舞われます。大日堂の舞楽は、演じ手の所作などに中世の芸能の古風さをうかがわせ、当地で独自に変化をした諸相をみせているのが特色です。(参照:文化庁 文化財オンライン)

大日堂舞楽 Information
- 名称:大日堂舞楽
- 文化財指定:国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に登録
- 開催場所:大日霊貴神社(大日堂)
- 所在地:秋田県鹿角市花輪字荒田4-1
- 電話番号:0186-32-2706
- 開催日:毎年1月2日
- 保存団体:大日堂舞楽保存会
- URL:大日堂舞楽
- アクセス:
- 公共交通機関/JR花輪線八幡平駅から徒歩で約1分
- 車/東北自動車道鹿角八幡平ICから約5分
Google Map
10台の豪華絢爛な屋台が競演。威勢のいいお囃子が一晩中鳴り響く『花輪ばやし』

『花輪ばやし』は、鹿角市の中心部、花輪地区にある幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)の祭礼の際に演じられる祭り囃子として、代々受け継がれてきたものです。祭礼は毎年8月16日~20日に開催されます。『花輪ばやし』は、祭礼最後の2日間、19日から20日にかけて行われる行事で、花輪の各町内から繰り出す10基の本漆と金粉で彩られた豪華絢爛な屋台によって繰り広げられます。屋台は、一旦ご神体が安置されている御旅所に集合し、午後5時30分頃太鼓や笛、鉦(かね/しょう)、三味線などによる威勢のいいお囃子とともに花輪駅を目指して町内を練り歩きます。

『花輪ばやし』の屋台は、4隅にタイヤはついていて、手で押して移動します。しかし、基本的には床がありません。お囃子隊の笛や鉦(かね/しょう)、三味線の演者には床があるのですが、大勢いる太鼓担当は屋台の動きに合わせて歩いて移動します。
午後8時近くには10基の屋台が花輪駅前に集合し、日本一の祭り囃子とも称賛される盛大なお囃子合戦が繰り広げられた後、屋台は花輪の町を巡行し、夜を徹してお囃子が鳴り響きます。20日の未明には10基すべてが1か所に集まり、祭りの神事である<枡形(ますがた)行事>が厳かに執り行われます。午前6時頃からの休憩タイムを挟んで、午前11時頃からはまた、屋台の町内巡行が始まります。午後8時頃には全基が花輪駅前に集合。再び屋台合戦が繰り広げられた後、午後11時30分頃には屋台が幸稲荷神社の赤鳥居に向けて出発、到着後シメの行事が行われ、祭りは終わります。

「花輪ばやし」の屋台は<腰抜け屋台>と呼ばれ、かつては全国にあったようなのですが、「花輪ばやし」以外では飯能市(埼玉県)の「底抜け屋台行事」(飯能市無形民俗文化財)位になってしまいました。
花輪ばやし Information
- 名称:花輪ばやし
- 所在地:秋田県鹿角市花輪地区
- 文化財指定:国指定重要無形民俗文化財(「花輪祭の屋台行事」として)・ユネスコ無形文化遺産(『山・鉾・屋台行事』の1つ)に登録
- 電話番号:0186‑22‑6088(花輪ばやし祭典委員会事務局)
- 開催日:
- 花輪ばやし/8月19日~8月20日
- 花輪祭/8月16日~20日(幸稲荷神社/神明社)
- 保存団体 花輪ばやし祭典委員会
- URL:花輪ばやし
- アクセス:
- 公共交通機関/JR花輪線鹿角花輪駅下車
- 車/東北自動車道角八幡平ICから約8分
Google Map
大太鼓による始まりの合図、厳かな「大の坂踊り」、唄だけが伴奏の「甚句」。450年続く『毛馬内の盆踊り』

『毛馬内の盆踊り』は、鹿角市の北部、十和田湖や大湯環状列石に近い鹿角市十和田毛馬内の本町通で、毎年8月21日から23日にかけて踊られている盆踊りです。盆踊りは主に3つに分かれていて、始めに大きな太鼓打ちが鳴らせる「寄せ太鼓」が盆踊りの始まりを知らせます。

最初に踊られるのが「大の坂踊り(だいのさかおどり)」。路上に焚かれたかがり火を見るように、道路の内側に向き、一列に並んだ踊り手たちが、大太鼓と笛のお囃子でゆっくり優雅に踊ります。この踊りは、先祖の霊を慰めるために踊るもので、最後に合掌で締めるのが特徴的です。踊り手たちは、女性は留め袖か振り袖など、男性は紋付きという正装で、頭には口まで隠す独特の頬被り(ほおかぶり)をしています。頬被りは、南部藩だった頃、他藩との戦いが繰り返されていたこのあたりでは特に南部美人といわれるほど女性が美しく、他藩の兵士から顔を隠すために着用したそうです。

次に踊られるのが「甚句(じんく)」で、こちらはお囃子が入らず唄だけで踊られます。衣裳は「大の坂踊り」と同じですが、戦国時代に行われていた戦勝の宴での踊りを起源とするためお祝いの要素が強く、また、豊作祈願などの願いも込められています。
かつては仮装をした踊り手たちがいたり、「大の坂踊り」にも唄があったりという記録があるのですが、今では仮装も歌い手も途絶えてしまって、今に受け継ぐことができませんでした。
「大の坂踊り」は、1657年頃にはあったと伝承されています。また、「甚句」についても1567年頃、南部藩が能代の檜山安東氏との戦いに勝利した際に始められたといわれています。また郷土史家の菅江真澄(すがえますみ/1754年~1829年)は、『鄙廼一曲(ひなのひとふし)』の中で、<盆踊大の坂ふし>の話を書いていることから、『毛馬内の盆踊り』は少なくとも江戸中期から行われていたのは確実です。
毛馬内の盆踊り Information
- 名称:毛馬内の盆踊り
- 文化財指定:国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産(全国41か所の風流踊)に登録
- 所在地:秋田県鹿角市十和田毛馬内こもせ通り
- 電話番号:0186-30-3939
- 開催日:8月21日~23日
- 保存団体:毛馬内北の盆実行委員会
- URL:毛馬内の盆踊り
- アクセス:
- 公共交通機関/JR花輪線十和田南駅から、徒歩で約20分・タクシーで約5分
- 車/東北自動車道十和田ICから約5分