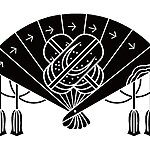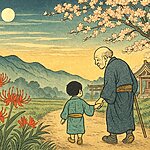温泉のある城下町・宿場町として発展した上山の歴史【山形県上山市】
目次
上山市は、山形県の南東部、山形市の南に位置し、江戸時代には上山藩の城下町で出羽国(でわのくに/山形県・秋田県)から奥州街道へ接続する羽州(うしゅう)街道の宿場町としても栄え、温泉のある宿場町としても人気になっていました。
戦国時代、米沢と山形の境にある上山では領地争いが激化
上山の地は、古くは“神山”あるいは“上の山形”と呼ばれていたのですが、1300年末頃に領主となった最上氏の流れをくむ武将、里見満長(さとみみつなが/最上満長)が“上山殿”と称していたことから上山(かみのやま)になったと伝わっています(参照:上山市プロフィール・上山市役所 )。
満長は1400年頃に上山の虚空蔵山(こくぞうさん)にはじめて城を築いたことで知られています。虚空蔵山の城は、高楯(たかだて)城または亀ヶ岡(かめがおか)城とも呼ばれていて、1535年武衛義忠(ぶえいよしただ)が現在の地に月岡城(上山城)を築くまで使われていました。
上山は、最上氏が支配する最南端の地で、南から攻めてくる伊達氏や上杉氏との戦いの舞台となっていました。時には伊達領となったりしましたが、武衛義忠が奪還。再び最上氏の領地となりました。
しかし義忠の孫里見(さとみ)吉兼(上山義兼)が総領主の最上義光(よしあき)と対立、攻防に敗れ、1579年に暗殺されてしまいます。その後1622年に上山藩を立藩するまでは最上氏の領地でした。
虚空蔵山・高楯城<Information>
- 施設名称:虚空蔵山・高楯城
- 所在地:山形県上山市松山字高楯(虚空蔵山)
- アクセス:
- 車/東北中央自動車道山形上山ICから約15分
- 鉄道/山形新幹線・JR奥羽本線かみのやま温泉駅から徒歩で約15分
Google Map
温泉開発や整備にも貢献した初代上山藩主松平重忠
上山藩は、能見(のみ)松平家(愛知県岡崎市能見町)松平重忠(まつだいらただしげ)が1622年に4万石で初代藩主となりました。
しかし、4年後には三田(さんだ)藩(兵庫県三田市)に移封(いほう/国替え・移動)となってしまい、その後は短い年月で蒲生氏・土岐氏・金森氏と頻繁に藩主が変わります。
ようやく、1697年から庭瀬藩(にわせはん/岡山県岡山市)の藤井松平家信通(のぶみち)が上山藩に移り、それ以降は藤井松平家が明治維新まで藩主となりました。
初代藩主松平重忠は、在任期間は僅か4年あまりでしたが、上山の城下町を整備し、温泉の開発にも努力しました。上山で温泉が発見されたのは里見氏時代の1458年で、肥前国(ひぜんのくに/佐賀県)の僧侶月秀が見つけたといわれています。
その後付近に多くの源泉が発見され、重忠の時代には温泉のある宿場町として知られるようになったのです。
今も残る温泉発見の地「鶴の休石」

かみのやま温泉は、“月秀が1羽の鶴が傷を癒やしていたのを見て、そこに温泉が湧いていたことを発見した” (かみのやま温泉源泉説明板より)と伝わり、その場所には割れ目から温泉の湧き出る「鶴の休石(つるのやすみいし)」があります。
この温泉はその故事から「鶴脛の湯」(つるはぎのゆ)とも呼ばれ、隣接して足湯が設置されています。
鶴の休石<Information>
- 施設名称:鶴の休石
- 所在地:山形県上山市湯町4-12
- 電話番号:023-672-0839(上山市観光物産協会)
- 営業時間:6:00~22:00
- 使用料:無料
- アクセス:
- 車/東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約10分
- 鉄道/山形新幹線・JR奥羽本線かみのやま温泉駅から徒歩で約20分
Google Map
松平重忠が領民のために解放した初の共同浴場「下大湯共同浴場」
さらに、かみのやま温泉の「下大湯共同浴場」は、1624年に松平重忠が領民のために解放した初の共同浴場で、建物、温泉設備などは変わっていますが、その温泉は400年にわたって親しまれています。

下大湯共同浴場<Information>
- 施設名称:下大湯共同浴場
- 所在地:山形県上山市十日町9-30
- 電話番号:023-672-0839(上山市観光物産協会)
- 営業時間:6:00~22:00(12月~2月は6:30から)
- 入浴料:おとな(中学生以上) 150円、小学生 100円、洗髪料 100円
- 休業日:無休
- アクセス:
- 車/東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約10分
- 鉄道/山形新幹線・JR奥羽本線かみのやま温泉駅から徒歩で約15分
Google Map
上山藩の発展に大きく寄与した土岐頼行・頼殷親子
上山が最も発展したのが、松平の三田藩への移封から2年後に藩主となった土岐頼行(ときよりゆき)とその子頼殷(よりたか)の時代です。

土岐頼行は下総国相馬郡(しもうさのくにそうまぐん/千葉県・茨城県)の守谷(もりや)藩主(茨城県)でしたが、1628年に2万5千石で上山に移りました。頼行は上山城の整備に力を注ぎ、本丸(三重の天守)、二の丸、三の丸、外堀などを造り、頼殷は豪奢な庭園まで造成しました。それだけでなく、城下町と交通路の整備、鉱業や新田の開発、神社仏閣の建立、用水路の建設、温泉の保護など、上山の発展に大きな功績を残しています。

頼行はまた、高僧の沢庵(たくあん)和尚が訳あって上山へ流刑人としてやってきた際に、立派な建物を建てて丁重に接しました。
沢庵和尚は3年後には江戸幕府の誤解が解けて江戸に戻ったのですが、上山の3年間で頼行は沢庵和尚からさまざまな教えを受け、領主として大きく成長したといわれています。
頼行が沢庵和尚のために建てた家「春雨庵(はるさめあん)」は当時のままの姿に復元され、山形県の重要文化財として保存されていて、見学可能です。
春雨庵跡<Information>
- 施設名称:春雨庵跡
- 所在地:山形県上山市松山2-10-12
- 電話番号:023-672-0824(春雨庵跡)
- 休館日:12月28日~1月3日
- 入館料:無料
- アクセス:
- 車/東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約15分
- 鉄道/山形新幹線・JR奥羽本線かみのやま温泉駅から徒歩で約15分
Google Map
江戸幕府によりすべての城郭が取り壊された上山城
土岐氏時代に城が整備され、大きく発展した上山藩ですが、それは2代64年で終わりを告げます。江戸幕府は1691年に頼殷を越前国野岡藩(福井県)に移動させ、何が気に入らなかったのか、城郭をすべて取り崩してしまったのです。
上山藩は土岐氏以降も明治時代になるまで存続しますが、三重の天守や豪華な二の丸などは再建されず、二の丸跡地に藩主の居館が建てられた程度の質素な城構えでした。
現在の上山城址には、ほんの僅かな遺構(堀跡)のほかは何も残っていません。現在の天守閣は、1982年(昭和57年)に、当時の天守がどんなものであったか全く分からないために、代表的な3層天守の形を模して建てられた模擬天守といわれる建物です。天守は「上山城郷土資料館」として上山の歴史や民俗資料などが展示されています。

上山城(上山城郷土資料館)<Information>
- 施設名称:上山城(上山城郷土資料館)
- 所在地:山形県上山市元城内3-7
- 電話番号:023-673-3660(上山城郷土資料館)
- 営業時間:9:00~17:15(最終入館16:45)
- 入館料:おとな 420円、高校生・大学生 370円、小中学生 50円(団体40円)
- 休館日:木曜日(祝日の場合は直前の平日)、12月29日~31日
- アクセス:
- 車/東北中央自動車道かみのやま温泉ICから約10分
- 鉄道/山形新幹線・JR奥羽本線かみのやま温泉駅から徒歩で約12分
Google Map
4軒の旧武家屋敷が残る「武家屋敷通り」
上山藩の城下町は、城から北西方面に広がっていて現在でも4軒の旧武家屋敷の建物が残っています。かみのやま温泉の中心部と温泉発見の地「鶴の休石」の間に、2軒が向かい合うように4軒あり、「武家屋敷通り」と呼ばれています。
4軒とも200年ほど前(江戸末期)に建てられたと推定されていて、東北地方に多く見られる茅葺き屋根の曲家(まがりや)となっています。曲家は、L字型の建物で、手前に飛び出した部分は農家では主に馬小屋として使われていたのですが、武家屋敷では座敷になっていて、攻めてくる敵を迎え撃つ場所として考えられていたようです。
森本家

森本家は、上山へ来る前から藤井松平家に仕えてきた家臣で、非常に重要な役職にあり、藩校「名神館」(跡地のみ)で教えていました。今も森本家の子孫が住んでいて、庭園以外見学できません。
森本家<Information>
- 施設名称:森本家
- 住所:山形県上山市鶴脛町1-7-48
- 電話番号:023-672-1111(上山市教育委員会)
三輪家

三輪家は上山藩11代目松平信古(のぶふる)の家臣で、殿様のお世話をする側用人(そばようにん)だったようです。明治時代には金融業として財をなしました。三輪家は一般公開されていて、当時の武家屋敷の様子がよく分かります。
三輪家<Information>
- 施設名称:三輪家
- 所在地:山形県上山市鶴脛町1-7-46
- 電話番号:023-673-1078
- 開館時間:9:00~16:45
- 休館日:月曜日、12月28日~1月3日
- 入館料:おとな 220円、高校大学生 160円、小中学生 50円
山田家

山田家は、殿様が乗る馬の世話をする馬廻役(うままわりやく)だった家系で、現在も子孫が住んでいます。非公開。
山田家<Information>
- 施設名称:山田家
- 住所:山形県上山市鶴脛町1-7-41
- 電話番号:023-672-1111(上山市教育委員会)
旧曽我部家

旧曽我部家は、上山藩7代藩主松平信通からの家臣で、馬廻役や奉行、役人を監督する大目付(おおめつけ)などの役職についていた上級武士の家系です。外観、庭のみ見学可能。
旧曽我部家<Information>
- 施設名称:旧曽我部家
- 住所:山形県上山市鶴脛町1-7-38
- 電話番号:023-672-1111(上山市教育委員会)
戊辰戦争で軍を鼓舞するために吹奏された上山藩鼓笛楽

上山藩は、明治維新後に勃発した新政府軍と幕府軍との戦い(戊辰戦争/ぼしんせんそう/1868年~1869年)の際、新政府と幕府側で揺れ動き大きな痛手を受けた歴史があります。
上山藩が戊辰戦争で出陣したのは計5回。最初は1868年4月新政府軍の一員として庄内藩と戦います。その後は奥羽越列藩同盟(おううえつれっぱんどうめい)という旧幕府側の組織に入り、3回にわたって新政府軍と戦火を交えました。それも隣接する米沢藩が新政府軍に降伏したことから、上山藩もそれに従い、再度新政府軍に編入されます。最後となる5回目の出陣は、しぶとく抵抗する旧幕府軍庄内藩の制圧に当たりました。
明治維新という大きな波に翻弄された上山藩ですが、戊辰戦争の際、フランス式の軍隊訓練を取り入れ、その際軍の士気を高めるために始められたのが「上山藩鼓笛楽」です。
上山藩鼓笛楽は、明治以降しばらく途絶えていましたが、昭和初期に復活し、現在でも祭やイベントで披露されています。上山市無形文化財。
上山藩鼓笛楽<Information>
- 名称:上山藩鼓笛楽
- 電話番号:023-630-3344(山形県教育局生涯教育・学習振興課)