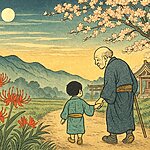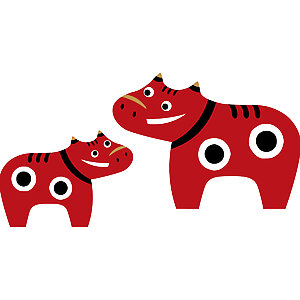【山形県上山市】江戸時代13もの藩主が利用した羽州街道の宿場町「楢下宿(ならげしゅく)」
目次
楢下宿(ならげしゅく)は、羽州街道(うしゅうかいどう)の宿場町です。羽州街道は、江戸と太平洋側の陸奥国(むつのくに)を結ぶ江戸五街道のひとつ奥州街道の桑折宿(こおりしゅく)から分かれて、日本海側の出羽国(でわのくに)に向かう重要な街道で、楢下宿は陸奥国との国ざかいにある宿場町でした。
奥州街道と羽州街道との分岐点で、現在の福島県伊達郡桑折町にあたる「追分(おいわけ)」は、2006年(平成18年)に整備・再現されています。敷地内には江戸時代の道標を中心に東屋、案内看板などが設置されています。
峠越え手前最後の本格的宿場町で、大いに賑わう
羽州街道は、桑折宿からしばらく陸奥国(福島県、宮城県)内を通り、金山峠(かねやまとうげ)を越えて出羽国に入ります。金山峠には金山宿がありましたが簡易的な宿場で、大名たちが泊まれるような本陣は楢下宿にありました。
参勤交代で江戸に向かう大名たちは必ずといっていいほど楢下宿に立ち寄っています。その数は日本海側にあった13藩で、中には陸奥国の津軽藩も利用していたようです。
楢下宿には23軒の旅籠に本陣、脇本陣、高札場(幕府や領主のおふれを張り出す場所)などがあり、大変な賑わいだったといわれています。
茅葺きの古民家や石橋など、昔の面影を残す町並み

現在の楢下は、かつて本陣だった塩屋斎藤家など多くの建物が失われてしまいましたが、脇本陣だった滝沢屋(丹野家住宅)など10棟ほどが当時の姿をとどめていて、宿場町だったことを思い起こさせる町並みです。ます。そのうちの大黒屋、山田屋、庄内屋、旧武田家それに滝沢屋が修復、復元され観光客に公開されています。

2つの石造アーチ橋、新橋と覗橋(のぞきばし)は明治初期に架けられたもので、いまでも現役の道路橋です。これらはすべて上山市の有形文化財に指定されていて、大切に保存されています。
さらに、金山峠を通る古道は、石仏などが残り昔の面影をよくとどめているため、楢下宿跡とともに「羽州街道 楢下宿・金山越」として国の史跡に指定されました。
脇本陣だった滝沢屋(旧丹野家住宅)は「歴史資料館」を併設

丹野家は、江戸時代に庄屋を務めていた家柄で、屋号を「滝沢屋」と称しています。もともと造り酒屋でもあり、客間は脇本本陣として大名や上級武士の宿泊・休息に利用されていました。建物の建築年代ははっきりしませんが、建てられてから250年以上は経っていると推測されています。現在は旧宿場町から少し離れたところに移築され、脇本陣としてのたたずまいを復元し、楢下宿の歴史資料を展示する「歴史資料館」となっています。

滝沢屋<Information>
- 施設名称:滝沢屋
- 開館時間:9:00~16:45
- 入館料: 一般 210円、学生160円、こども 50円
- 休館日:月曜日、12月28日~1月3日
食事処も開設。茅葺き屋根の古民家「大黒屋」

大黒屋は、宿場町の中心部にあって、元脇本陣滝沢屋の南隣に位置する由緒ある家柄です。建物は1808年に建てられたということが分かる古文書が残っています。茅葺き屋根が残る間口10.1m、奥行き17.5mの当時としては大きな造りで、間仕切りの形状などがよく保存された古民家です。建物は道を挟んだ反対側に移築されました。見学は無料。
楢下の伝統料理、おばあちゃん手作り「おもてなし御膳」
大黒屋では、囲炉裏を囲んで“楢下宿ばあちゃんずくらぶ”が手作りした郷土料理を味わうことができます。

山菜やきのこ、栗、芋、銀杏などを季節の食材を使った「おもてなし御膳」の、素朴な中に伝統に培われた深い味わいに感動です。冬には竹串に刺して囲炉裏であぶった名物料理「納豆あぶり餅」も食べることができます。おばあちゃんの料理は、5名以上で5日前までに上山市観光物産協会(023-672-0839)に予約が必要です。
大黒屋<Information>
- 施設名称:大黒屋
- 営業期間:通年
- 休業日:水曜日、6月上旬から7月上旬、年末年始
- 料金:「おもてなし御膳」2,000円
- 申し込み:5人以上、5日前までに予約
- 予約受付:上山市観光物産協会
- 電話番号:023-672-0839
- URL:ばあちゃんずくらぶのおもてなし御膳
明治時代に建て替えられた「山田屋」

山田屋の建物は、1868年(明治元年)の火災で建て替えられたもので、瓦葺きになっています。覗橋のたもとにあり、古いアーチ橋と一体となった景観は、楢下宿を代表するノスタルジックな雰囲気を醸し出す場所のひとつです。見学は無料。
殿様からの拝領の品も残る庄内藩の御用宿「庄内屋」

庄内屋は脇本陣で、庄内藩の御用宿でした。格式は準本陣級といわれており、他藩も利用したときの宿札も残されています。建物は茅葺き屋根の平屋造りで、客間が4室あります。庄内藩主の煙草盆や拝領品が残されていて、楢下に残っている民家の中では最も古いもののひとつです。建物は1700年代中頃のものと推定されています。見学は無料。
建築年代が正確に分かる貴重な建物「旧武田家」

旧武田家は茅葺き屋根の平屋造りで、1758年の屋敷割絵図に旅籠屋であることが明記されています。また、台所の柱には1758年に改装したとの墨書きが残っていて、建築年代が正確に分かる貴重な建物です。見学は無料。
2つのアーチ橋で眼鏡橋。新橋と覗橋

新橋は、1880年(明治13年)に竣工したもので、全長14.7m、幅は4.4mほどあります。この橋を架けるにあたり、県の補助300円だけでは足りず、残り700円を地元が負担したため、通行する人や人力車、荷車などから橋銭を徴収していました。いまでは有料の橋はどこにでもありますが、当時は大変珍しいものだったようです。今でも現役の橋で自動車(4トン以下)も通行できます。
覗橋は上流の新橋が完成した2年後の1882年(明治15年)に架けられたもので、全長は10.8m、幅3.5mです。現在も現役で重量制限は4トンとなっています。
新橋と覗橋は“眼鏡橋”と呼ばれています。眼鏡橋というと長崎などにある2つのアーチがある橋がほとんどです。川面に映る姿が眼鏡に見えるから眼鏡橋と呼ばれているのですが、楢下の新橋と覗橋はおのおの1つのアーチしかありません。楢下の眼鏡橋は2つの橋をあわせて眼鏡に見立てているのです。
保全活動によって安全に歩けるようになった金山越

山形県と福島県の県境にある金山峠は623mと標高もそれほど高くなく、歩きやすい峠道でした。江戸時代に大名行列が歩いた旧道には、いまでも馬頭塔や湯殿山碑、縁石などの遺跡が残っていて、往時の面影を今に伝えています。地元の人たちによる保全活動により、昔のままの状態に保たれ、安全に歩くことができるようになりました。
楢下宿<Information>
- 名 称:楢下宿(ならげしゅく)
- 所在地 :山形県上山市楢下
- 電話番号:023-672-1111(上山市教育委員会 生涯学習課)
- アクセス:
- 鉄道/JR奥羽本線かみのやま温泉駅より約20分
- 車/東北中央自動車道山形上山ICから約20分
- 公式URL:山形県公式観光サイト「楢下宿」