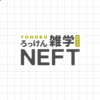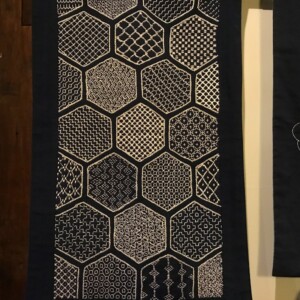かつては日本で二番目に広い湖があった「八郎潟」【秋田県】
目次
秋田県の八郎潟(はちろうがた)は、かつては220平方キロメートルの面積を誇り、琵琶湖に次ぐ日本で二番目に広い湖として知られてました。
八郎潟の成り立ち
遠い昔に、北側の米代川と南側の雄物川からそれぞれ土砂堆積により砂州(さす)が延び、離島だった現在の男鹿市にある寒風山に達して複式陸繋島(ふくしきりくけいとう)の男鹿半島が形成されたといわれています。その2つの砂州の間に残った海跡湖が八郎潟です。
かつては海洋資源の宝庫だったが大規模な干拓事業により消滅
琴の湖とも呼ばれ船越鉄道で日本海とつながっていた汽水湖であり、水深4~5mと浅いながらも、ワカサギ、シラウオ、ハゼなどの豊富な魚が水揚げされたり、大量に採れた藻類は、肥料として欠かせない資源でした。
しかし昭和32年、国営干拓事業という国家プロジェクトが始まったことで、八郎潟は埋め立てられ広大な農業用地となり、かつて湖の底だった土地は緑豊かな田園風景へと生まれ変わり、大潟村(おおがたむら)と命名されました。その後大潟村は、稲作による米の生産だけでなくメロンやリンゴの産地としても有名になり、現在へと至ります。
八郎潟の面影を感じる八郎潟調整池
日本第二位の広い湖だった頃の名残りが見られる場所が、大潟村の南部に残っている八郎潟調整池です。

ブラックバスやワカサギの釣りスポットとしても有名で、優雅なうたせ船などの姿も見られるなど、残存湖とはいえかなり広大で、過去の面影を色濃く残しています。

また、JR奥羽本線八郎潟駅から車で20分の所にある大潟村 桜・菜の花ロードでは、毎年ゴールデンウイーク前後になると、艶やかな桜と菜の花の壮大なコラボレーションがどこまでも続く景色を眺めることができることから人気です。
路肩にはさくらスポットという花見の駐車スペースがあるので、車を停めて桜をゆっくりと楽しむことができます。
緯度経度が切りのいい数字の経緯度交会点標示塔と海抜0メートルの山?
さらに、大潟村ならではの特徴的なスポットの経緯度交会点標示塔は、経緯度交会点に建てられている記念塔ですが、経緯と緯度が交差する地点は数多くあるものの北緯40度・東経140度の美しい数字で交差している場所は日本でもこの場所だけです。

また、日本一低い富士山である大潟富士があり、この富士山は、海抜0メートルの高さの富士山として知られています。
八郎潟に伝わる八郎太郎伝説
そんな八郎潟には、青森県にまたがる十和田湖、仙北市の田沢湖の3つの湖をまたにかける壮大な伝説「八郎太郎伝説」が伝えられています。
マタギだった八郎太郎がある出来事から人外となり、十和田湖の主となっていたが、ある高僧との戦いに敗れ田沢湖に落ち延び、田沢湖の辰子姫と結ばれ、その後も迫りくる追手から逃れ八郎潟にたどり着き、その地で龍神となった…と簡単にまとめるとこのようなお話です。
これだけ広域に渡って伝わる伝説というのもかなり珍しいのではないでしょうか?
まとめ
今となってはもう見ることができない八郎潟。東北地方にそんな湖があったとは今となっては信じられない気持ちもあります。なぜ干拓をしてしまったんだ?と惜しむ気持ちもあります。しかしその当時、その土地に生きる人たちには必要なことだったんでしょうね。
秋田市中心部からもそれほど遠くないので、秋田を訪れた際は少し足を延ばして、かつてあった巨大湖の面影に触れてみるのもいいのではないでしょうか。
大潟村<Information>
- 名称:大潟村(八郎潟埋立地)
- 住所:秋田県南秋田郡大潟村