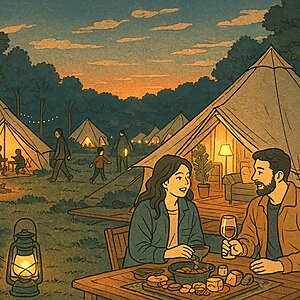ディーゼル特急から新幹線まで……「つばさ」の軌跡【秋田県・山形県】
目次
山形新幹線の「つばさ」は、2025年現在、主に東京駅と山形県の山形駅または新庄駅を結んでいます。
特に鉄道が好きな方でなくても、山形に住んでいる、あるいは山形に行ったことがあるという方であれば、知っている、乗ったことがあるという方は少なくないでしょう。
山形新幹線が開業したのは1992年のことですが、それ以前から「つばさ」という名前の列車は走っていました。
今回は、山形新幹線の前身ともいえる特急「つばさ」について紹介します。
ディーゼル特急として運行を開始した「つばさ」
特急「つばさ」は1961年10月のダイヤ改正に伴い、運行を開始しました。
運行区間は、東京都の上野駅から秋田県の秋田駅までで、途中栃木県の宇都宮駅・黒磯駅、福島県の郡山駅・福島駅、山形県の米沢駅・山形駅・新庄駅、秋田県の横手駅に停車していました。
路線名で言えば、上野駅~福島駅間は東北本線、福島駅~秋田駅間は奥羽本線です。
運行開始時のダイヤでは、下り列車は上野駅発が12時30分、福島駅着が16時11分、秋田駅着が21時ちょうどとなっています。
上り列車は秋田駅発が8時10分、福島駅着が12時57分、上野駅着が16時40分でした。
上野駅~秋田駅間の所要時間は上下列車共に8時間30分です。
現在の秋田新幹線「こまち」は、上野駅~秋田駅間を3時間50分ほどで走破してしまうので、当時の「つばさ」は倍以上の時間がかかっていたことになります。
しかし、当時は「つばさ」よりも短い時間で上野と秋田を結ぶ列車はなかったので、その需要は旺盛だったと思われます。
なお、1958年に上野駅と青森駅を結ぶ特急「はつかり」が、東北地方初の特急列車として運行を開始していました。
ただし「はつかり」は宮城県以南では常磐線を経由していたため、東北本線にある宇都宮駅や福島駅などは経由していませんでした。
これらの駅を経由する特急列車は「つばさ」が初めてだったのです。
※特急「はつかり」の詳細はこちらの記事でご覧ください。
また、上野駅~秋田駅間には「おが(男鹿)」という急行列車も運行されていました。
「おが」の詳細についても記事になっているので、ぜひご覧ください。
運行開始当初の「つばさ」は、キハ82系気動車の6両編成によって運行されました。
国鉄(JRの前身)初の特急用気動車であるキハ81系をベースとして量産された車両です。

気動車とは、車両に搭載された燃料でエンジンを回して走行する車両です。
日本では軽油を燃料とするのが一般的で、ディーゼルカーとも呼ばれます。
「つばさ」の歩みは、ディーゼル特急として始まったのです。
なお、福島駅~米沢駅間では、日本の鉄道の中でも有数の難所である「板谷峠(いたやとうげ)」を越えます。
この区間をキハ82系のエンジンの出力だけで越えるのは、エンジンへの負荷が大きかったため、補助機関車が連結されました。
しかし、機関車の助けを得てもなお、福島駅から米沢駅までのわずか43kmを走破するのに、1時間ほどもかかったのです
(現在の「つばさ」は35分程度)。

※板谷峠の鉄道の歴史についてはこちらの記事でご覧ください。
盛岡駅発着の「つばさ」や特急「やまばと」の登場
「つばさ」は、1963年に1両増結されて7両編成になります。
さらに、上野駅と岩手県の盛岡駅を結ぶ「つばさ」も、キハ82系の6両編成で運行されるようになります。
上野駅~福島駅間では、秋田駅発着の7両編成と、盛岡駅発着の6両編成が連結して、13両編成で運行されていました
(現在の新幹線で「やまびこ」と「つばさ」が、東京駅~福島駅間を連結して走行しているのと同じようなことです)。
1964年10月には、盛岡駅発着の編成が1両増結されて、秋田駅発着の編成と合わせて14両編成となりました。
同時に、上野駅と山形駅を結ぶ特急「やまばと」が、キハ82系の7両編成で運行を開始しています。
現在の山形新幹線「つばさ」は、東京駅と山形駅・新庄駅を結んでいるので、この「やまばと」の方が、現在の山形新幹線により近い性質の列車といえます。
盛岡駅発着の「つばさ」は、1965年に秋田駅発着の「つばさ」から分離されて「やまびこ」に改称されます。
この「やまびこ」の愛称も、後に東北新幹線の列車に受け継がれています。
また、秋田駅発着の「つばさ」は、1往復増発されて1日2往復となりました。
1968年10月のダイヤ改正では「つばさ」の一部列車が東京駅まで乗り入れるようになったほか、1年間限定で、元祖特急用気動車であるキハ81系の先頭車が「つばさ」に使用されるようになります。
ブルドッグと呼ばれる先頭形状が特徴的な車両です。

著作者:Gohachiyasu1214 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76865554による
新型車両でも越えがたい板谷峠
キハ82系は板谷峠で補助機関車を連結していましたが、自力で登坂できるようにするために、1970年に新型車両のキハ181系気動車が「つばさ」に投入されました。
上野駅~秋田駅間の所要時間が8時間15分程度と多少短縮されて、従来の7両編成から10両編成への増車もされています。
翌1971年には、さらに増結されて12両編成となりました。

著作者:Spaceaero2 – 自ら撮影, CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2002979による
ところが、キハ181系にとっても板谷峠の自力登坂は荷が重く、夏季を中心にエンジントラブルが多発します。
結局「つばさ」が電車に置き換えられるまでは、再び補助機関車を連結して板谷峠を越えることになりました。
「つばさ」は電車特急に
1975年に、奥羽本線全区間の電化が完了(※)し、電車が走れるようになりました。
そこで「つばさ」は、485系電車12両編成による、電車特急列車に改められました。
485系電車は、1,453両も製造された、国鉄を代表する車両の1つです。

上野駅~秋田駅間の所要時間は約7時間35分、板谷峠を越える福島駅~米沢駅間の所要時間は約40分に短縮されていて、当時の気動車と電車の性能の差がうかがえます。
1978年10月のダイヤ改正では、所要時間が若干増えたものの、1日3往復に増発されました。
※奥羽本線は、山形県と秋田県をまたぐ区間である新庄駅~院内駅間が、2025年より非電化に戻っています。
詳しくはこちらの記事でご覧ください。
東北新幹線開業に伴う変遷
1982年6月に、東北新幹線が大宮駅~盛岡駅間で開業します。
これに伴い11月には、東北新幹線と並行する東北本線で、在来線特急列車の運行形態が大幅に変更されました。
もちろん「つばさ」も例外ではありません。
11月のダイヤ改正前の「つばさ」は上野駅~秋田駅間で1日3往復運行されていましたが、
- 上野駅~秋田駅:下り1本、上り2本
- 福島駅~秋田駅:下り3本、上り3本
- 山形駅→秋田駅:下り1本
以上のように改められました。
東北新幹線と並行する上野駅~福島駅間を走行する列車は、1日1.5往復に減らされたのです。
これまでの「つばさ」の、東北地方内の始発・終着駅は秋田駅と(ごくわずかな期間だけ運行されていた)盛岡駅のみでしたが、福島駅と山形駅が新たに加わっています。
また、12両編成から9両編成への減車も行われています。
減車の理由は、おそらく「つばさ」を秋田駅まで利用する人が減少するためです。
東北新幹線が開業したことによって、福島駅~秋田駅間を移動するには「つばさ」に乗るよりも、盛岡駅で東北新幹線と特急「たざわ」を乗り継いで利用する方が、所要時間が短くなりました。
福島県や首都圏から秋田へ向かう人たちは「つばさ」ではなく、盛岡経由のルートを利用するようになったのでしょう。
1985年3月には東北新幹線が上野駅まで延伸開業します。
このときのダイヤ改正では
- 上野駅~秋田駅:1往復
- 福島駅~秋田駅:3往復
- 福島駅~横手駅:1往復
- 福島駅~新庄駅:1往復
- 福島駅~山形駅:2往復
- 山形駅~青森駅:1往復
となりました
(上野駅と山形駅を結んでいた「やまばと」は、このダイヤ改正で廃止されました)。
始発・終着駅のラインナップに、新たに横手駅、新庄駅と青森駅が加わっています。
なお、上野駅発着の列車が1往復だけ残されたのは、福島駅での新幹線と在来線の乗換を省略できるという利便性よりも、特急「あいづ」(上野駅~会津若松駅間で運行)と車両を共通運用(使い回し)していたという要因の方が大きいと思います。
使用される車両についても、列車によって9両編成だったり、グリーン車のない6両編成だったり、かと思えば季節によってはグリーン車ありの9両編成になる列車もあったりして、複雑な様相を呈していきます。
翌年1986年の11月のダイヤ改正では、青森駅までの運行がわずか1年半あまりで取り止められ、山形駅~秋田駅間の運行に短縮されます。
この列車は両数も3両編成(季節によっては5両編成)にまで減らされました。
その後は運行区間の延長や増発が何度か行われています。
その過程で、始発・終着駅ラインナップに秋田県の大曲駅が加わっています。
山形新幹線の開業に伴い運行終了
1990年より、奥羽本線の福島駅~山形駅間に、山形新幹線を通すための工事が始まります。
なお、山形新幹線が開業することとなった経緯については、以下の記事でご覧ください。
翌1991年には「つばさ」の福島駅~山形駅間での運行は終了します。
上野駅・福島駅を発着していた列車は、山形駅で方向転換して、仙山線(仙台駅と、山形県の羽前千歳駅を結ぶ路線)を経由して運行するようになりました
(【上野駅】東北本線経由【仙台駅】仙山線経由【山形駅】奥羽本線経由【秋田駅など】)。
この変更に伴い、福島駅発着だった列車は、仙台駅が始発・終着駅に変更されました。
「つばさ」はこれで、東北地方6県の県庁所在地の駅全て(秋田・盛岡・山形・福島・青森・仙台の各駅)を始発・終着駅としたことのある列車になったのです。
そういう意味では、東北地方の列車を代表するほどの存在感を示した特急列車だったと言ってもよいのかもしれません。
1992年7月1日に山形新幹線が開業し、東京駅~山形駅間での運行を開始しました。
この新しい列車に「つばさ」の愛称がつけられ、在来線特急の「つばさ」は運行を終了しました。
ただし、新幹線の「つばさ」は愛称こそ引き継いでいるものの、運行区間が山形県内までなので、在来線特急の「つばさ」が果たしていた、秋田県へのアクセスを担う列車という役割は失われています。
繰り返しになりますが、かつての列車名で例えるならば「つばさ」というよりは「やまばと」に近い存在なのです。

著作者:spaceaero2 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7808984による
一方、在来線の「つばさ」が運行されていた山形駅~新庄駅・秋田駅間では、新たに特急「こまくさ」が運行を開始しました。
しかし、1999年に山形新幹線が新庄駅まで延伸開業すると「こまくさ」は新庄駅以北の運行に改められたうえで快速列車に変更。
2002年には快速「こまくさ」も廃止されています。
おわりに
在来線特急の「つばさ」は、首都圏・福島県と山形・秋田県を結ぶ役割を長年果たしてきました。
昔はこのような列車があったのだということを、記憶にとどめていただけたならば幸いです。