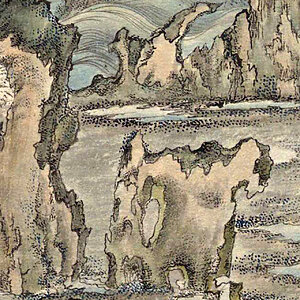青森下北のお盆は豪快!墓前で花火をして先祖を迎えるって本当?
目次
お盆といえば、迎え火を焚いて静かに先祖を迎える——そんな姿を思い浮かべる人が多いはず。しかし、青森の下北地方では独特の風習でお盆を迎えます。「ここでそんなことをするの!?」という驚きの風習もあるので、ぜひ最後までご覧ください!
下北ならではの個性あふれるお盆の風習

下北のお盆って、ほかの地域とちょっと違う。海と山に囲まれたこの土地は、昔から漁師町と農村が入り混じって暮らしてきた場所。そのせいか、音や光を使って先祖を迎えるという、どこか豪快でにぎやかな風習が残っています。北海道との距離も近く、行き来の中で取り入れられた文化もあるのではないかな、と感じます。
たとえば、こんな風習があります。
- 夜に墓前で花火を上げて先祖を迎える
- お盆飾りはとうろうという派手な飾り
- ハマナスの実で作った数珠をお供えする
どれも、この地域ならではの景色。夏の夜、お墓に上がる花火と子供たちの歓声を聞くと、「帰ってきたなぁ」という気持ちになるんです。
墓前で花火?夜空を彩る下北のお盆の光景
墓前での花火が豪快過ぎる!

「墓前で花火」と聞くと、手持ち花火や線香花火で静かに先祖を偲ぶ。そんな情景を思い浮かべる人が多いでしょう。ところが、下北のお盆はまるでお祭りのように賑やか。ドラゴン花火や噴き上げ花火など、派手で音も大きいものが次々と打ち上がります。夜の墓地一帯が光と音に包まれ、しんみりというよりも華やかで豪快な雰囲気に。地元の人にとっては、それこそが「先祖を盛大に迎える」何よりの方法なのです。
墓参りと花火が同時に行われる理由
こうした豪快な花火は、ただ賑やかさを演出するためだけではありません。下北地方の一部では、夜に墓参りをしながら花火を打ち上げる風習があり、その理由として「花火の光と音で先祖の霊に家の場所を知らせるため」と語られます。もともと漁師町では、出漁や帰港の合図に花火や松明を使う習慣があり、その文化が盆行事にも受け継がれたのではないかとも言われています。迎え火や送り火のように、光で先祖を迎えるという意味合いが、下北では花火という形になって残っているのです。
一般的な”とうろう”とは違う!?カラフル過ぎるお盆飾り
可愛くて派手なとうろう
下北のお盆で欠かせないのが、飾られる「とうろう」です。一般的に「とうろう」と聞いて思い出すのは明かりをともす照明器具ですが、実はモナカの皮のような素材で出来た飾りなんです。見た目はカラフルなお菓子のようで、津軽地方でも使われています。
仏壇や墓の盆棚に吊るしたり、棒に渡した縄に飾るとうろうには実は様々な種類が存在します。花や野菜、果実を模したデザインが多く、昔は採れたものを供える代用品として考案されたともいわれます。色も鮮やかなピンクや緑、黄色など、供養というよりまるでお祭りのよう。
家ごとに異なる飾りつけ
飾るものはとうろうだけとは限りません。とうろうだけを下げる家庭もあれば、同じ紐に盆せんべいをつるしたり、ささぎや青リンゴを下げる家庭もあります。幼いころに親戚の家へ行くととうろうの自分の家のとうろうとの違いに驚いたものです。現在は簡略化されてとうろうだけどつるす家庭も増えているそうですが、こうした地域色豊かな文化は後世にも残していきたいですね。
ハマナスの実で作る数珠供え

下北地方では、お盆になるとハマナスの実を18個使って数珠を作り、仏様にお供えします。この「18」という数は、煩悩の数(108)の六分の一にあたることからきているとされ、厄除けや先祖供養の意味が込められています。鮮やかな赤い実が並ぶ姿は、美しくもどこか神聖な雰囲気を漂わせます。
数珠づくりが家族団らんの行事に
ハマナスの実は海沿いに多く自生しており、お盆前になると家族そろって実を摘みに出かけます。その実を糸に通して数珠を作るのは、子どもから大人まで参加できるお盆ならではの行事。こうした作業を通じて、風習や思いが次の世代へと受け継がれていきます。最近では、手作りが難しい家庭向けに、完成品のハマナス数珠が販売されることもあります。
【番外編】下北の人はお盆休みをずらす?

下北地方では、お盆の時期と重なる8月18日~20日に「田名部まつり」が開催されます。華やかな山車が町を練り歩くこの祭りは、地域最大級の夏のイベント。
地元出身者の中には、帰省をお盆期間ではなく田名部まつりに合わせる人も多く、久しぶりに会う家族や友人と祭りを楽しむ光景があちこちで見られます。お盆の静かな供養とは対照的に、町全体が熱気と活気に包まれる3日間です。
Information
- 名称:田名部まつり
- 開催期間:2025年8月18日〜20日
- 開催場所:むつ市田名部地区(田名部神社周辺)
- WEBサイト:むつ市「田名部神社例大祭」
まとめ
下北は海と山に囲まれ、漁師町や農村としての歴史が残る地域。出漁や帰港の合図に花火や松明を使ってきた漁師文化や、自然の恵みを大切にする暮らしぶりが、独自のお盆の風習を生み出したのでしょう。静かに先祖を偲ぶだけでなく、光や音、鮮やかな色で先祖を迎える下北のお盆は、訪れる人の心にも強く刻まれるはずです。






![【かまくらの謎】秋田県の冬の風物詩[かまくら]は鎌倉幕府に関係がある? 横手4_旅東北1000](https://jp.neft.asia/wp-content/uploads/2025/08/a2674c8c7497fa159899e9b2a761c38f-150x150.jpg)