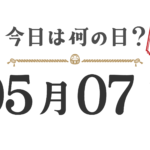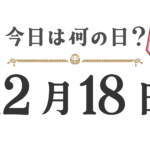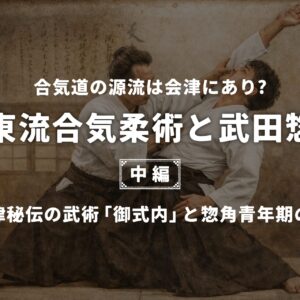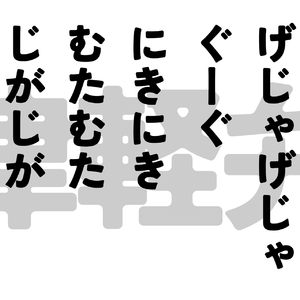昔は東北の日光と呼ばれていた?会津の守護神が眠る土津神社【福島県猪苗代町】
目次
福島県耶麻郡猪苗代町に鎮座する土津神社(はにつじんじゃ)は、会津藩初代藩主・保科正之(ほしなまさゆき)の墓所であり、神として祀る神社でもあります。
でもなぜ会津地方の守護神とされている人物の墓所が、お城のある会津若松ではなく猪苗代にあるのか?本記事ではその辺の疑問も含めて土津神社を解説します。
会津の守護神と呼ばれた名君「保科正之」
徳川秀忠の庶子として生まれ、保科家に養子入りした保科正之は、徳川家光の信頼を受けて幕政を支える一方、会津藩の初代藩主として藩政の礎を築きました。

質素倹約と仁政を重んじ、会津家訓十五箇条の制定、年貢の適正化、社倉制度、養老扶持などにより文治政治を推進。特に「会津家訓十五箇条」では、君主は奢ることなく、民を第一に思い、学問と忠義を重んじるよう記されており、後の会津武士道にも大きな影響を与えました。
また、正之は学問の重要性を理解しており、学問や教育を奨励する姿勢を藩内に浸透させました。また、暦学にも関心を寄せており、渋川春海を会津に招いて暦理を講じさせるなどその才能を高く評価しています。
保科正之が与えられた霊号に由来する「土津神社」の名前

土津(はにつ)という名称は、神道に傾倒していた保科正之が、寛文11年(1671年)に神道家・吉川惟足(よしかわこれたり)から神道の奥義を授けられた際に与えられた霊号「土津」に由来します。
「土」は五行思想における大地・宇宙の根源、「津」は会津の「津」、つまりは会津藩主を意味する言葉とされ、万物の理を体得した君主としての正之の在り方が表されています。
祭神とその神格化について

土津神社の主祭神は会津藩初代藩主・保科正之で、生前に「死後は磐梯山の神を祀る磐椅神社の末社となって永遠に神に奉仕したい」と本人が望んでいたことから「土津霊神(はにつれいしん)」の神号を賜り、自身も神として祀られるようになりました。
本人の遺言通り、土津神社は磐椅神社の末社となっています。
また土津神社は鶴ヶ城のある会津若松から北東(鬼門)に位置し、立地の上からも「鬼門封じ」の役割を担い、会津若松を守護しているといわれています。
相殿神と客神について
土津神社では、主祭神である保科正之に加え、会津藩歴代藩主のうち、仏式で葬られた二代藩主・正経を除く七名の藩主が相殿神として祀られています。
ただし、二代藩主保科正経(ほしなまさつね)から九代藩主松平容保(まつだいらかたもり)までの歴代藩主とその側室や子どもたちの墓所は、会津若松市東山町大字石山にある院内御廟(いんないごびょう)になります。
相殿神
- 松平正容(徳翁霊神)|会津藩三代藩主
- 松平容貞(土常霊神)|会津藩四代藩主
- 松平容頌(恭定霊神)|会津藩五代藩主
- 松平容住(貞昭霊神)|会津藩六代藩主
- 松平容衆(欽文霊神)|会津藩七代藩主
- 松平容敬(忠恭霊神)|会津藩八代藩主
- 松平容保(忠誠霊神)|会津藩九代藩主
なお、保科正之は幕府から松平姓と葵紋の使用を勧められていたにもかかわらず、養育してくれた保科家への恩義を忘れず、保科姓を生涯通しました。その後、三代・正容の代から松平姓と葵紋が使用され、親藩としての格式が整えられました。
また、相殿の客神としては「高良玉垂大明神」が祀られています。これは、記紀神話に登場する伝説上の忠臣・武内宿禰(たけしうちのすくね)の神号とされ、応神天皇から数代にわたり歴代天皇に仕えた忠義の象徴的存在です。
高良玉垂大明神は、地元の磐椅神社の祭神でもあり、土津神社がその末社とされていることや、正之とその家臣たちの忠義心に重ねられて祀られたと伝えられています。
かつては「東北の日光」と呼ばれるほど絢爛豪華だった土津神社
保科正之が延宝元年(1673年)に死去した後、二代藩主・保科正経の命により仮殿が建てられ、延宝3年(1675年)に社殿が完成。
古来の正式に則った荘厳な神殿造りの社殿に、感時門や回廊、透塀などが整った土津神社は、日光東照宮と比較されるほどの絢爛豪華な建物だったことから後に「東北の日光」「奥日光」「裏日光廟」などと呼ばれるようになったといわれています。

しかし、戊辰戦争により社殿は焼失し、現在の建物は明治13年(1880年)に再建されたものです。それでもなお、神社全体には往時の気配と格式が漂っています。
奥の院(保科正之公墓所)

奥の院にあたる保科正之の墓所は拝殿脇から山道を500mほど登った場所にあります。
墓所のすぐ近くまで車道が通っているので、一度駐車場まで引き返して車で近くまで行くこともできます。クマ注意の看板もあるので無理はしないほうがいいかもしれません。

墓所脇には2~3台ほど駐車できそうなスペースがあり、ここからならもう目の前に墓所が見えます。

墓所には柵が張り巡らされていて立ち入り禁止となっており、門の脇から少しだけ中の様子を見ることができます。墓石には「会津中将源君之墓」と刻まれています。
後ろに見える小高い丘のようなものが保科正之の墳墓で、山頂部には「土津神墳鎮石」と刻まれた鎭石(しずめいし)が鎮座しています。

周辺にはいくつもの「立入禁止」の看板が。神聖な土地であることがひしひしと伝わってきます。
土津神社<Information>
- 名 称:土津神社(はにつじんじゃ)
- 住 所:〒969-3102 福島県耶麻郡猪苗代町見禰山3
- 電話番号:0242-62-2160
- 公式URL:https://hanitsujinja.jp/