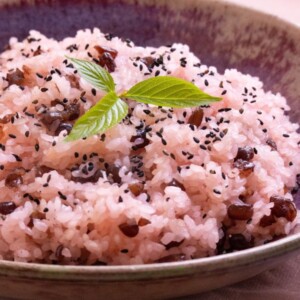泣いたら「モッコ」がくる!?津軽の子供たちのトラウマの謎を追ってみた【青森県】
目次
「泣けば山からモッコがくるぞ」
青森県の津軽地方を中心として昔から使われているというこのフレーズ、子どもを泣き止ませるための「しつけ文句」だそうで、現在でも青森県出身者に話を聞いてみると、けっこうな高確率で「小さい頃モッコの話で親に脅された…」という人が存在します。
実際に青森県の旧木造町(現つがる市)周辺には「モッコ」が登場する子守唄も伝承されています。
「モコ」「モッコ」「モーコ」と若干の違いがあるものの、秋田県の北部や岩手県の一部地域にも共通する存在のようです。でも実際モッコって何なんでしょうか?
おばけ?妖怪?それとも何か別の存在…?
今回は、この「モッコ」という謎めいた存在について、色々な説を紹介しながら津軽の歴史と伝承に迫ってみます!
モッコ=蒙古(もうこ)説
音を聞いて「もしかして」と思う方も多いと思いますが、最も語られることの多い説のひとつが、「モッコ」=「蒙古(もうこ)」ではないか?というものです。
しかもこのモッコ=蒙古(もうこ)説はさらに二つの説へと分岐します。
元寇の際の対馬・壱岐からの避難民の口伝説
鎌倉時代、元(モンゴル帝国)は1274年(文永の役)と1281年(弘安の役)の2度にわたって日本に侵攻してきました。

元寇(げんこう)と呼ばれ、日本史の授業でも習う大きな事件ですが、その際、現在の長崎県に属する対馬や壱岐は離島だったことから防衛の最前線となり、村落が焼かれ、多くの住民が虐殺されたといわれています。
さらに津軽地方には「對馬(対馬)」姓を名乗る家系が多く存在しており、「元寇の被害から逃れた対馬の人々が北に漂流し、辿り着いた津軽に定住したのでは?」ともいわれています。
つまり、対馬から津軽に辿り着いた避難民が語った「蒙古軍の恐怖」が、やがて「泣く子をさらう山の化け物」という形で語り継がれるようになったのが「モッコ」ではないか?という仮説です。
元(モンゴル帝国)の樺太侵攻の避難民からの口伝説
元(モンゴル帝国)は13世紀後半に北方にも軍を派遣しています。
日本への第二次侵攻である弘安の役(1281年)後の1284年から、3度に渡って樺太(サハリン)への侵攻が行われていたようです。
この遠征により樺太(サハリン)のアイヌ系住民が土地を追われ、北海道、さらには本州へと避難したという可能性から、対馬・壱岐からの避難民と同様に、樺太(サハリン)から津軽に辿り着いた避難民が語った「蒙古軍の恐怖」が、「モッコ」という形で地域に定着した…とするのが二つ目の説です。
説得力はあるが、どちらの説にも明確な証拠はない
どちらの説も明確な証拠などがあるわけではなく推察の域はでないのですが、一定の説得力はありますよね。
もしかしたらどちらとも事実で、南から避難民が来たと思ったら数年後には北からも。
「南でも北でも猛威を振るう蒙古軍というのはいったいどれだけ恐ろしい存在なんだ?」と、津軽の人々の恐怖心を煽ったという可能性もあります。
そうして津軽の人々の心に深く刻まれた「モッコ」への恐怖心が、数百年たった今でも色褪せることなく語り継がれる原動力になっている…というふうにも考えられますね。
他にも存在する様々な説
モッコの由来には他にも様々な説が存在します。しかし全ての説において「かもしれない」という推察の域はでませんのであしからず。
山の霊的存在説
古来日本では「山には神や霊が宿る」と信じられてきたことから「山の神に連れていかれる」という言い伝えは日本各地にあり、「泣けば山からモッコがくる」というのは、そうした自然信仰の影響と考えることもできます。
擬音・感情表現由来説
「モッコ」という言葉自体が意味を持つものではなく、「音としての怖さ」を意識した擬音語ではないかという説もあります。つまり、「モッコ」は音の響きだけで子どもに恐怖を与える「しつけ言葉」として生まれたという説です。
アイヌ語・北方語源説
「モッコ」は北方言語、たとえばアイヌ語から転訛したものではという言語学的な視点もあります。津軽地方には古くからアイヌ文化との接触があったとされる地域もあり、その文化の一端が伝承に影響を与えた可能性も否定できません。
「なまはげ」のような制裁者の象徴説
秋田の「男鹿のなまはげ」のような、津軽のどこかの地域、または村落に伝わっていた風習の中の「教育係」として「モッコ」と呼ばれた存在がいたのでは?という説もあります。
まとめ
津軽地方は青森県の日本海側に位置し、津軽平野の豊富な産品と引き換えに海を利用した交易が盛んだった地域でもあります。南北の多様な文化が行き交う中で「モッコ」のような、色々な記憶が混ざった存在が生まれたのかもしれませんね。
結局、モッコの正体は「これだ!」というのはわかりませんでしたが、様々な説を通じてみえてくるのは
「モッコ」は、地域に残る“恐怖”や“戒め”の象徴
だということですね。
もしあなたが津軽を旅して、ふと「モッコくるぞ…」という言葉を耳にしたら、それは数百年前の記憶が今もそっと語りかけてきているのかもしれません…。