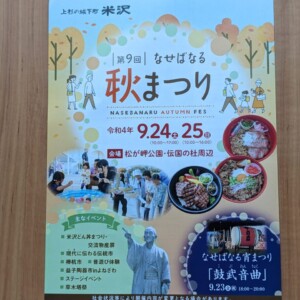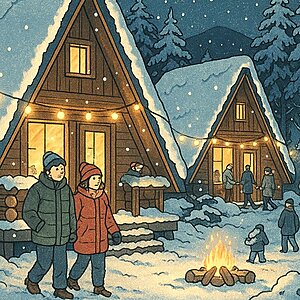青森県のりんご収穫量は年間37万トンで日本一!でも37万トンってどれくらい?
目次
青森県の特産品がりんごであることは、たとえ東北地方にお住まいでなくても多くの方がご存知かと思います。
2023年に青森県で収穫されたりんごの量は実に「374,400トン」です。
多いということはわかっても、どれくらいの量なのか想像がつかないと思います。
そこでいったい37万トンとはどれくらいの量なのかを示すとともに、青森県のりんごについて簡単に紹介します。
青森県のりんご収穫量は日本一!
2023年の全国のりんご収穫量は「603,800トン」です。
この内、青森県で収穫されたりんごは「374,400トン」なので、「国内のりんごの62%は青森県産」で、当然ながら都道府県別収穫量では日本一です。
なお、2位もりんごの産地として有名な長野県ですが、その収穫量は106,900トンで、青森県の4分の1強しかありません。
そして、3位は岩手県の31,600トン、4位は山形県の30,300トン、5位は福島県の18,500トン、6位は秋田県の16,300トンなので、東北地方だけで8割近くを占めていることになります。
青森県産のりんごのおよそ半数の品種は「ふじ」です。
そして「つがる」「王林」「ジョナゴールド」がそれぞれ約1割となっています。
「つがる」以外の3品種は貯蔵性に優れていることが特徴で、通年で味わえることが青森県産のりんごの強みとなっています。
大型トラック24,155台分のりんご
りんご園で収穫されたりんごは、各地の卸売市場へ運ばれていきます。
青森県外への出荷量の内およそ4割が関東地方への出荷で、これに次いで近畿地方、中部地方への出荷が多く、この3地方の合計で全体の75%ほどを占めています。
青森県産のりんごの約9割は、トラックで運ばれます。
そういうわけで、374,400トンのりんごが、トラック何台分になるのかを考えてみましょう。

Ypy31 – 投稿者自身による著作物, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70313266による
日野プロフィアFRという大型トラックは、1台あたり15.5トンの貨物を積載できます。
すると、374,400トンのりんごを運ぶには、24,155台の大型トラックが必要ということになります。
そして、プロフィアの全長は11,990mmとあります。
大型トラックの全長は12m以内と定められているので、ギリギリを狙ったと思われる長さです。
ここではキリのよい数字、12mということにして計算しましょう。
24,155台の大型トラックを車間距離ゼロで並べると、289.96kmです。
青森市にある青森インターチェンジから東北自動車道に並べたならば、青森県から出てしまうのはもちろんのこと、秋田県小坂町・鹿角市、岩手県を抜けて、宮城県栗原市にある築館インターチェンジまでが288.3kmなので、これを越えてしまいます。
※東北自動車道はほとんどの区間で片側2車線以上ですが、1車線に並べる想定としています。
これでもなかなかの長さだということがわかると思いますが、しかし車間距離ゼロで並べるという前提は非現実的です。
高速道路を走行するトラック同士には、それなりの車間距離が必要です。
車間距離を88m(もっと車間距離がほしいかもしれませんが、計算の単純化のためこの数字にしています)、つまりトラック自体の全長と合わせて1台あたり100mの道路を占有するものとしましょう。
すると、24,155台の大型トラックの車列の長さは、2,415.412kmということになります。
青森インターチェンジから、鹿児島県鹿児島市にある鹿児島インターチェンジまでを結ぶ高速道路の長さがおおむね2,000kmですから、それよりも長い車列です。
青森県で1年に獲れるりんごの、恐るべき量がイメージできたでしょうか。
貨物列車なら749本分
記事をご覧のとおり鉄道ファン 兼 元・鉄道関係者である筆者としては、貨物列車で運ぶことも考えたいところです。
貨物列車でよく使われるタイプの12フィートコンテナは5トンの貨物を積載でき、コンテナ貨車1両にコンテナを5個積載できるので、1両あたり25トンのりんごを載せられます。
これを20両まとめて、東北本線の貨物列車をけん引しているEH500形電気機関車にけん引させることにしましょう
(日本最長のコンテナ貨物列車は26両編成ですが、東北地方では運行されていないと思います)。

EH500の全長は25m、コンテナ貨車は約20mなので、全長は425m、積載量は500トンです。
374,400トンのりんごを運ぶには、74,880個のコンテナ、14,976両のコンテナ貨車が必要なので、実に749本もの貨物列車を運行する必要があります。
749本の貨物列車の全長は318.325kmです。
これを、北日本の貨物輸送に活躍する東北本線(旧・東北本線である、いわて銀河鉄道線・青い森鉄道線を含む)に、青森駅から並べることを考えます。
青森駅(青森県青森市)→青い森鉄道線(121.9km)→目時駅(青森県三戸町)→いわて銀河鉄道線(82.0km)→盛岡駅(岩手県盛岡市)→JR東北本線(112km)→石越駅(宮城県登米市)
以上で315.9kmなので、貨物列車で運ぶ場合もやはり青森県から岩手県北部まで列車が数珠つなぎになるということになります。
列車間の距離を考慮するなら、最短でも600m、現実的には1km以上間隔を空けて走ることになると思いますので、列車1本あたり1,500mを占有すると仮定すると、貨物列車749本で1,122.425kmです。
これは青森駅から、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、JR東北本線・武蔵野線・東海道本線を経由、県名で言えば、青森・岩手・宮城・福島・栃木・茨城(古河市のみ経由)・埼玉・東京・神奈川・静岡・愛知の都県を経由して、愛知県北西部の稲沢市にある清州駅ぐらいまでの長さです。
トラックの場合は車間距離を考慮すると鹿児島まで行ってしまいましたから、それよりは短くなりましたが、やはり途方もない長さと言えるでしょう。
人間よりもりんごの木の方が7倍多い

りんごの収穫量が多い青森県には、当然のことながらたくさんのりんごの木があります。
正確な本数までは把握されていないと思いますが、青森県のりんごが栽培されている土地の面積が約24,100haであることから推計すると、りんごの木の本数は約839万本とのことです。
あえて比べるならば、青森県の人口は2020年10月の国勢調査の時点で1,237,984人ですので、人間よりもりんごの木の方が7倍ほど多いということになります。
青森県ではなぜりんごの生産が盛んなのか?

現在日本で食べられているりんごは、明治初期の1871年に日本に導入されたものです。
青森県では1875年に国から配布された3本の苗木が、青森県庁の敷地内に植えられたことから栽培が始まりました。
その後、青森県内でりんごを栽培する農家が順調に増えていき、1909年には全国で一番りんご畑が多い県となりました。
りんごは涼しい気候に適した果物で、気温の観点では、東北地方で育てるにはうってつけの果物でした。
そのことは、東北地方の各県や北海道での収穫量が多いことからもうかがえます。
他にも、りんごが青森県の農家にとって他の作物よりもよい収入源になったこと、冷害で米が獲れないような年でもりんごならば育てられることなど、りんごの栽培方法や、害虫から守る方法などを熱心に広めた人物がいたことなど、青森県でりんごが盛んになった要因がいくつかあります。
青森県のりんごをおいしく食べよう

りんご収穫量日本一を誇る青森県では、観光資源としてもりんごが欠かせません。
りんごの風情が楽しめる弘前市のアップルロード、弘前市りんご公園、浪岡市にあるりんご収穫体験ができる道の駅なみおか「アップルヒル」など、たくさんのりんごにまつわる観光スポットがあります。
そして、りんごは見るだけでなくおいしく食べたいところです。
当メディアでもいくつかの青森りんごの楽しみ方を紹介しています。
ぜひ参考にご覧ください。